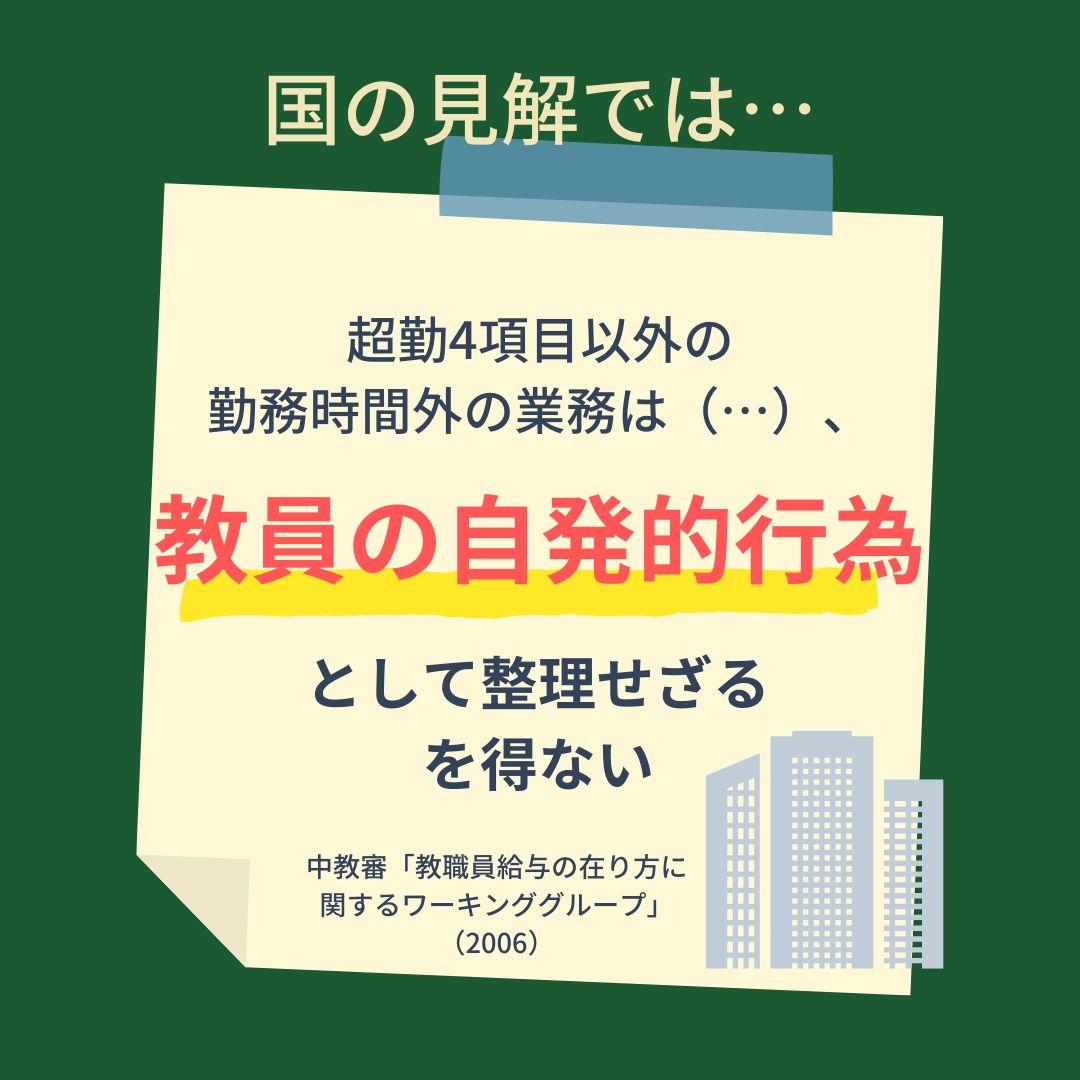
公立学校の教員の給与に関し、月額給与の4%に相当する「教職調整額」を上乗せする代わりに、残業代を支給しないとしている給特法ができてから半世紀になる。この間、給特法を巡って何も問題提起がされてこなかったかといえば、そうではない。3回に分けて給特法の基本を知るポイント解説の第2回では、給特法を巡る裁判に着目し、これまでの議論を振り返っていきたい。
まず、前回のおさらいをすると、給特法は、公立学校の教員の職務と勤務態様の特殊性を踏まえ、その給与について、月額4%を基準とした教職調整額を支給する代わりに、労働基準法で定められている労働時間外の勤務に対する割増賃金、つまり残業代は支払わないとしている。また、原則として超勤4項目を除いて時間外勤務を命じないこととされている。
しかし、実態として公立学校の教員が勤務時間外に超勤4項目以外の仕事も行っていることは事実だ。では、これらの業務は学校でどのように扱われてきたかというと、あくまで教員の自主的・自発的な行為であるとされてきた。例えば、2006年に行われた中教審「教職員給与の在り方に関するワーキンググループ」の第8回会合で文科省が示した「教員の職務について」という資料では、「現行制度上では、超勤4項目以外の勤務時間外の業務は、超勤4項目の変更をしない限り、業務内容の内容にかかわらず、教員の自発的行為として整理せざるをえない」と強調。「このため、勤務時間外で超勤4項目に該当しないような教職員の自発的行為に対しては、公費支給はなじまない」と説明している。
そして、こうした国の解釈を巡り、これまでも教員が原告になった裁判を通じてさまざまな異論が唱えられてきた。
ここでは、代表的なものをみていきたい。
1988年に名古屋地裁で判決が出た「愛知県立松蔭高校事件」のケースでは、原告はクラブ活動の引率指導に対して、労基法に基づく残業代が支払われるべきだと主張。その判決では、その業務が教員の自由意思を極めて強く拘束するような形態でなされ、そのような勤務が常態化しているなどの判断基準を示し、原告の場合はこのような基準には該当しないとして、原告の主張を認めなかった。この判断基準はこの後の同様の裁判でも採用されている。
また、2011年の「京都市公立学校事件最高裁判決」では、京都市立小中学校の教員をしていた原告は、超勤4項目以外の業務を黙示の職務命令などで従事させられていたと主張。校長の安全配慮義務違反があったとして、国家賠償法に基づく損害賠償を請求した。
しかし、判決で校長は明示的に時間外勤務を命じておらず、黙示的に時間外勤務を命じたと認めることもできないとし、給特法には違反していないと原告の訴えを棄却している。
このように、公立学校の教員の時間外労働に対して、残業代を支払うべきであるという訴えや、超勤4項目以外の業務も従事させられているとする主張は、極めて高いハードルとなる判断基準が示される形で、原告が敗訴し続けてきた。
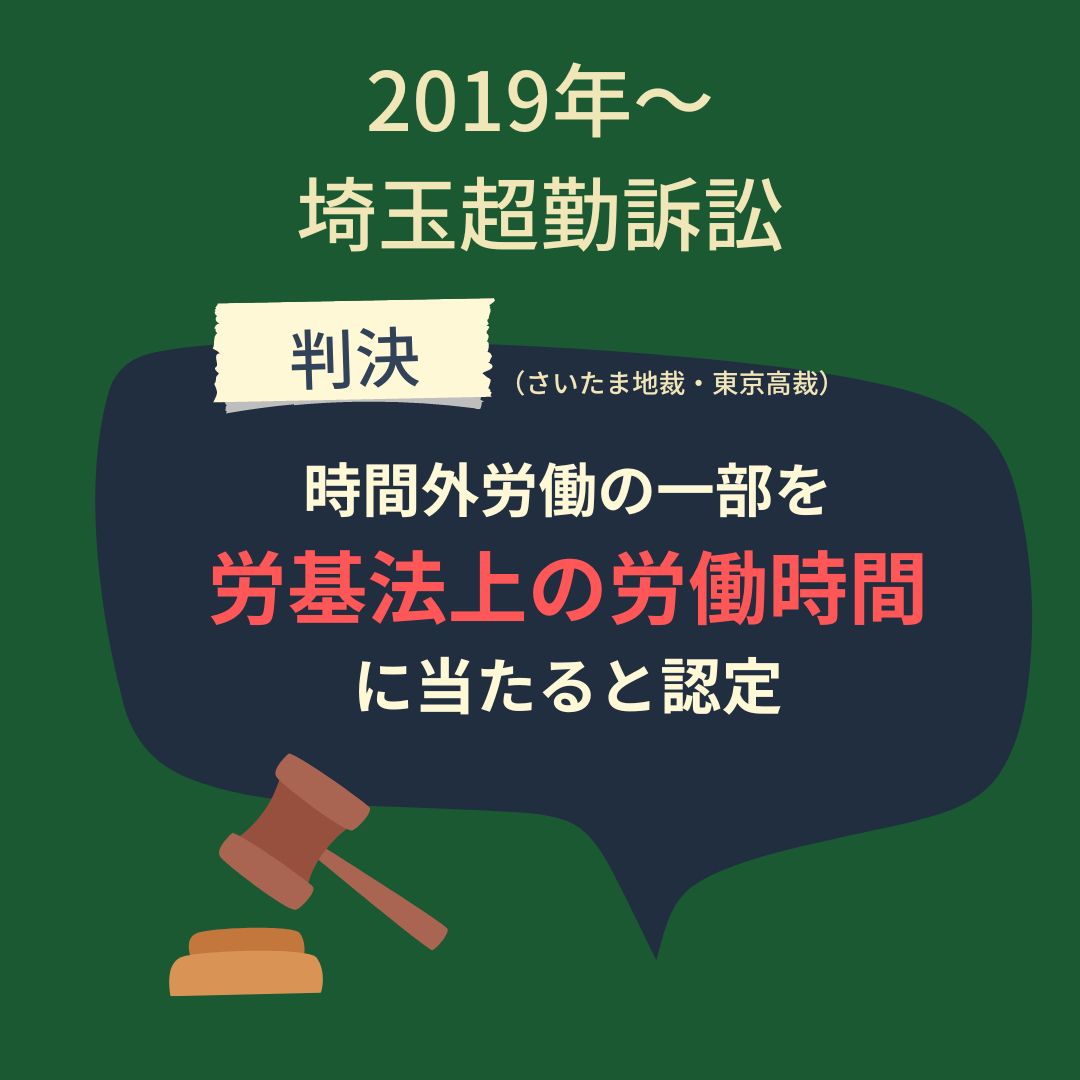
給特法に関連する裁判ではもう一つ、まさに今進行中のものがある。それが、埼玉県内の公立小学校に勤務する原告の教員が訴えた「埼玉超勤訴訟」だ。
これまでの裁判と違い、埼玉超勤訴訟は「教員が勤務時間外も校内で長時間の業務をしているのは、1日8時間、週40時間を超えて残業させてはならないとしている労基法32条違反になる」と指摘する。もしこれらの業務が労基法32条で規制対象とされる「労働時間」に該当するならば、時間外労働に対して残業代を支払うべきであり、それが認められなかったとしても、時間外労働を強いられたことに対して国賠法に基づく損害賠償を請求できるはずだと訴えた。
昨年10月に下されたさいたま地裁の判決では、原告の教員が提出した時間外労働の一部を労基法上の労働時間に当たると認定。時間外労働が長時間にわたり、かつ常態化しており、校長に労基法32条違反の認識があり、必要な措置を怠っているといった場合は、国賠法に基づく損害賠償責任を負うと踏み込んだ。
しかし地裁は、教職調整額は超勤4項目以外の業務も含めた時間外労働の手当に代わるものとして支給されているとして、残業代の請求を退けるとともに、原告の教員のケースでは長時間の時間外労働が常態化しているわけではないとして、損害賠償の請求も認めなかった。
そして今年8月、地裁判決を不服として原告が控訴した東京高裁が下した判決もこの地裁判決を踏襲する形となり、原告は最高裁に上告することを決めた。
このように、公立学校の教員が超勤4項目以外の業務を勤務時間外に行っていることは、あくまでも自発的行為であるとされ、裁判を起こしてもよほど深刻な状況が明らかでない限り、残業代や国家賠償請求は認められない。それが、「定額働かせ放題」と指摘されるゆえんとなっている。埼玉超勤訴訟は教員の時間外勤務を「労基法上の労働時間」に該当すると認めた点で風穴を開けたと言えるが、残業代や損害賠償を請求するための壁は厚い。
さいたま地裁での埼玉超勤訴訟の一審判決では、判決文に「給特法はもはや教育現場の実情に適合していないのではないかとの思いを抱かざるを得ず、原告が本件訴訟を通じて、この問題を社会に提議したことは意義があるものと考える」と異例の付言が添えられている。
半世紀という時間の中で溝がどんどん大きくなっていった給特法と学校現場の状況をどう埋めればいいか。政府や国会、そして社会全体に、その議論が委ねられている。