9月に、毎年通っている祭りがある。岩手県大槌町の、大槌まつりだ。私だけでなく、震災後に「コラボ・スクール大槌臨学舎」の立ち上げに参加し、今は東京や別の場所で働く元職員らも、その祭りの日には大槌に集結する。カタリバのメンバーたちが白い服と鉢巻きを身に着け、地元の人たちに紛れて600kgほどのみこしを担いでいるのを見ると、「私たちが被災地で取り組んできたことは、つながりをつくる支援だったんだ」と改めて思う。

今でこそ、いろいろな場所の災害支援に携わっているが、私にとって初めての災害支援は、東日本大震災だった。ノウハウもつながりもなかったが、報道を目にして「何かしなければ」と体が動き、被害の大きかった宮城県沿岸部へ単身で向かった。「子どもたちの居場所を作りたい」と教育委員会と話をする中で、2011年7月には宮城県女川町、同年12月には岩手県大槌町でコラボ・スクールを開校した。
災害の被害にあった子どもたちは、日常を突然奪われ、心身ともに疲弊する。体育館や親戚の家などでの避難生活では落ち着いて過ごせず、受験生であったとしても勉強もままならない。復旧作業で忙しい大人たちの姿を見て、「家族や先生に迷惑を掛けたくない」と、不安定な精神状態のまま我慢し続けることもある。大きな災害が起きた時には、子どもが集まって安心して過ごし、遊んだり学んだりできる居場所が必要になる。
大槌町のコラボ・スクールは、10年で647人の子どもたちが居場所として利用してくれた。子どもたちと接してきたのは、カタリバの職員をはじめ、大勢のボランティアだ。大学生がボランティアとして飛び込んでくれて、地域の方々とコミュニケーションを取りながら、成長する姿もたくさん見てきた。ボランティアをきっかけに東北へ転居して活動を続ける人も、第2の故郷として毎年通い続ける人もいる。また、当時小学生や中学生だった被災した子どもたちが、大学を卒業してカタリバに就職してくれることもあり、つながりを大切にしながら関わりを続けてきた。

こうした東北での経験があったからこそ、その後の災害でも、早期に支援活動に入ることができるようになった。16年の熊本地震をはじめ、18年の西日本豪雨、19年の令和元年東日本台風、20年の熊本豪雨、21年の熱海市伊豆山土石流、佐賀豪雨、22年の新潟村上豪雨…。近年では毎年のように日本各地で災害が続く。カタリバも各現場に入りながら、子どもたちの居場所づくりをサポートしてきた。
毎年夏ごろは、「ひどい被害にならないでほしい」と祈るような思いで豪雨のニュースを見る。それでも一定規模の災害になってしまったら、学校や避難所などの現地のニーズを調査しながら、現場に入る。臨機応変に動けるのが強みのカタリバだからこそ、取り組まない理由はない。そんな気持ちで自然と動いている。
東北の災害支援では私自身も現地に住み込んで、女川と大槌に自宅を構えながら拠点を行き来するような生活を続けていた。しかし災害が各地で起きるようになり、自分自身が子どもを育てるようにもなると、私があちこちの現場に毎回常駐することはままならない。カタリバとして少しずつ体制を整え、19年には「sonaeru」という災害時子ども支援の仕組みを改めて作った。
災害支援の1番の難しさは、いつ起きるか分からない、ということ。sonaeruチームに所属する職員は、平時は別の職務をカタリバの各地の拠点で担っているが、有事の際は被災地に迅速に入って、災害支援に当たれるようにした。人が抜けてしまい各拠点で業務が回らなくなることのないよう、普段から余裕を持った人員配置と仕事の共有を行っている。20年以降は、コロナ禍の中で感染対策をしながら支援活動をしなければいけないというハードルもあったが、少しずつノウハウをためた。
迅速に地域に入るためには、災害発生前から自治体と関係性があった方が早く動けることもあり、各地の自治体と平時からアライアンス(提携)を結ぶことにも取り組んでいる。
「災害時の行動には、平時の関係性が大きく影響する」というのは、何も自治体との関係づくりに限らない。学校の中の関係づくりも必要だと、痛感している。
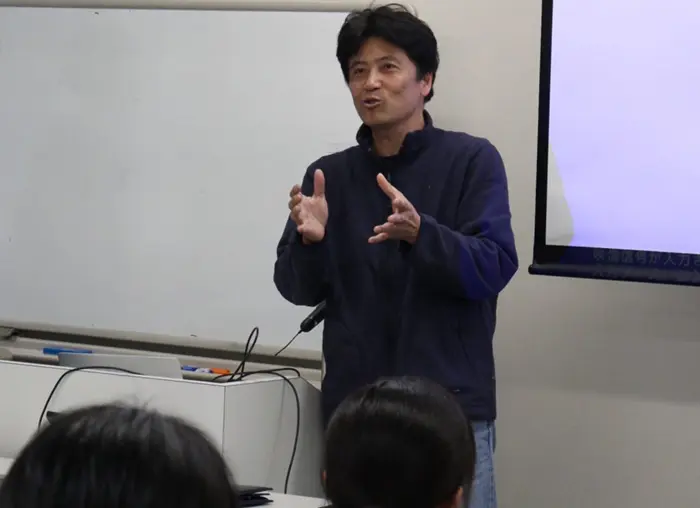
東日本大震災を通して私が出会い、学ばせてもらった方の一人に、佐藤敏郎さんがいる。元中学校教諭の敏郎さんは11年に宮城県石巻市立大川小学校が被災した際、そこに通っていた小学校6年生の次女を津波で失った。同校の避難行動について、「職員室の日常の関係性が、津波が押し寄せようとしている中で、避難開始の判断の遅れを招いた」と指摘する。敏郎さんによると、同校では40分以上の待機時間があったにもかかわらず、避難を開始したのは津波到着の1分前。教職員らは学校のマニュアルに従って、津波が迫る高台方面へと向かい、学校にいた子どもたちの9割以上が犠牲になった。
平時から教職員一人一人がリーダーシップやオーナーシップを持って判断し、行動できるような関係性があったならば、結果は全く違っていたのかもしれない。緊急時の素早い意思決定は、カタリバなどの外部団体が支援に駆け付けることよりも、ずっと大きな意味を持つ。マニュアルを踏襲するのでなく、「早く避難しよう」「津波の反対側にある裏山に逃げよう」と教員同士で話して決められていたら、子どもたちを亡くすことなく、全員で避難を実行できていたかもしれない。敏郎さんは、「小さな命の意味を考える会」を立ち上げ、今も語り部として日本各地で講演などを行い、この経験を次世代につなぎ続けている。
日頃からできる災害対策というと備蓄などをイメージするかもしれないが、先生同士の対話的な関係性づくりや職場の心理的安全性を確保することも、大切な一歩になる。前例にとらわれず「この校則は変なのでは」「そこまで怒鳴らなくてもいいのでは」などと、若手も含めてお互いに意見し合えたり、フラットに雑談ができたりするような職員室をつくること。そういう関係を日常的につくることこそが、災害時の適切な行動につながるのではないかと考えている。