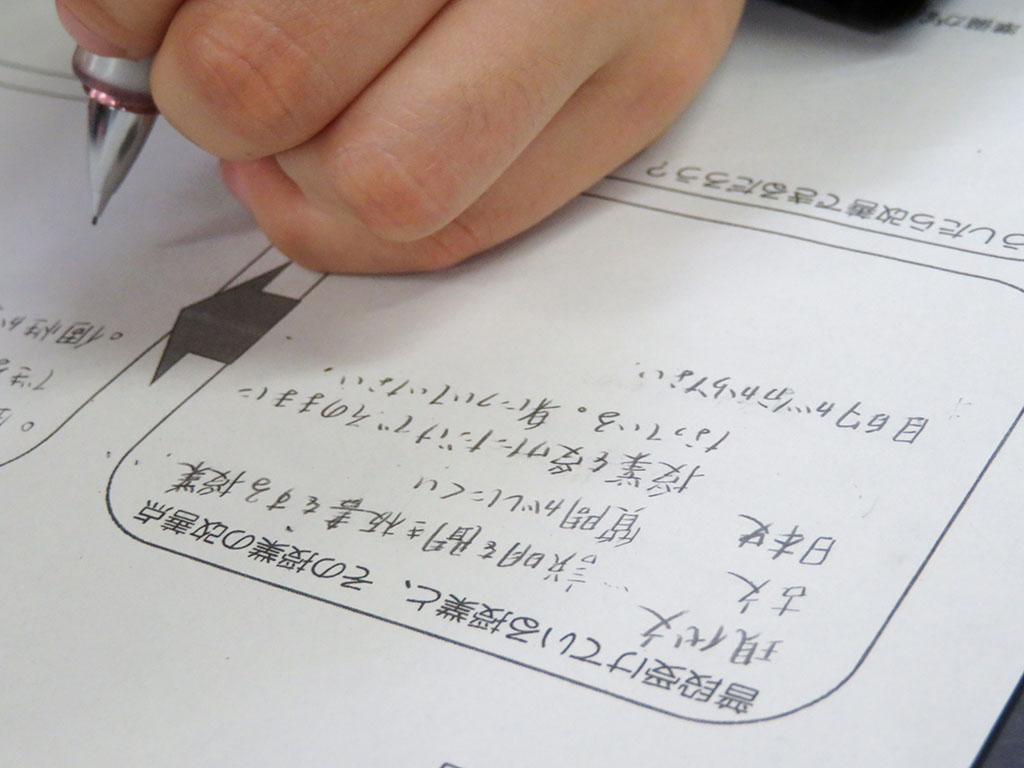東京都立国際高校で「生物」を教える佐野寛子教諭は、京都大学大学院医学研究科で研究活動に従事していたことがあり、獣医師免許も所持する、教師としては異色の存在だ。佐野教諭がなぜ教師になろうとしたのか、その経緯などから、教師の役割を問い直す。
東京都武蔵野市にある日本獣医畜産大学(現・日本獣医生命科学大学)で学び、獣医師免許と教員免許の両方を取得しました。教員免許を取ったのは、母親の勧めがあったからです。
自分自身が先天性股関節脱臼症であるので、骨や関節の再生について研究したくて、京都大学大学院医学研究科の博士課程に進みました。再生医科学研究所(現・ウイルス・再生医科学研究所)で研究しており、2階下には、iPS細胞でノーベル生理医学賞を受賞した山中伸弥教授がいました。当時はノーベル賞を受賞するかどうかで毎年マスコミが殺到して取材のスタンバイをしており、風物詩の一つでした。

研究を進める傍ら、近くの動物病院で獣医師として研修やアルバイトをしていました。診察していると、飼い主からネグレクトや虐待を受けている疑いの動物が運ばれることもありました。十分な餌を与えられず、低血糖で倒れてけいれんしている犬もいました。
どうしてここまで放置したのだろう。そう思って飼い主に聞くと「この子は食べないし、ほえるので近づけなかった」と説明します。雪が降り、気温がマイナスになる2月の京都で、その犬は暖房のきかない車のガレージに置かれ、犬の様子がおかしいと子供が病院に連れていきたいと言って、来院したそうです。
子供への虐待事件が問題になっていますが、動物にも同じことが起きています。言葉を話せない動物はSOSも出せません。人間の倫理観に疑問を強く感じました。
ちょうどその頃、京都大学の動物福祉サークルの学生らと共に、動物保護のための展示やイベントをしていました。しかし、足を止めて話を聞いてくれるのはもともと動物が好きな人たちで、動物に興味がない人たちにその声は届きません。
その点は、獣医師も同じで、病院に運ばれてこない動物たちは救えないし、飼い主が望まなければ治療も無理に進められません。処分場に送られる動物の数を減らすにも、該当者に直接声を届けられません。そこで、そのサークルには法学部の学生が多かったこともあり、法律や条例、制度を変えて動物を救おうと、弁護士や行政とともに活動をしていました。
私自身、実際にどうすれば動物を助けられるのかと考えると、「やはり人間の倫理観を上げなければならない。そのためには教育だ」と思いました。それが教師になったきっかけです。
国民の生命に対する倫理観を上げるには、「生物」の授業はぴったりです。生物の科目ほど、命とは何かを問われる科目はありません。加えて高校生は、これからいろんな進路を目指して、さまざまな職業に就く前の段階にあります。命の大切さを伝えることができれば、社会に出た後、何かしらの形で仕事に生かしてくれるかもしれない。さらには、親として次の世代に伝えてくれるかもしれない。
だから、研究職から進路変更して、高校で生物の教師になりました。
教師はこれから、生徒の資質・能力を引き出す役にシフトすると思われます。授業では、あくまでも生徒のサポーターやファシリテーター、空間づくりに徹していく。
自分の知識や経験や人脈を生かし、現場で出た意見をつなげたり、深い学びへと課題をその場で再提案したり、地域や企業、研究者など本物の課題を生徒とともに考える場へとつなげたりする形で、ファシリテートする必要が出てくると思います。
もちろん、知識がないままファシリテートをしても、意見の価値に気付けなかったり、話題を広げたり集約できなかったりして、生徒の深い学びを引き出せませんし、方向性を見誤ります。生徒と共に教員も学び続けている身であることを自覚し、知識や教養など常にアップデートし続ける必要があります。
「チョークジャック」については現在、生徒が主体となって、他校にも広めようと動き始めています。年輪のある日本の木材をブランド化し、地元の児童館でつながりを広げている生徒たちのように、主体的に行動して社会を動かしていく生徒を育てたいです。
そのためには、教科の学びも必要ですが、授業や学校行事を教科横断的に関連付け、地域とつながりをもつ「カリキュラム・マネジメント」を実施し、実社会や地域に根差して展開していくことが大切です。生徒を実践的活用の場へとつなぐことで、学びの確かな実感になります。
この方向性は2022年度から施行される新学習指導要領にもありますが、現場で実践するには教員一人だけでは負担が大きく困難です。教科横断的な取り組みを行うには他教科との擦り合わせも必要で、学校経営方針とも合わせなければならない。そして、地域や企業とのつながりを探す必要があります。
生徒が主体的に行動し始めれば、自分たちでつながりを開拓し、他の教員とかけ合うので、生徒と教員が互いにサポートし合う関係になりますが、生徒が動き始めるまでは教員側で準備することになります。
課題は、教員同士のつながりや、教育改革への方向性の理解です。それをどうするか。
東京都には模範的な授業をする「指導教諭」という役職がありますが、都内でも科目ごとに数人しかいません。そこで、指導教諭が学校カリキュラム・マネジメントのコーディネーターを担い、校内教員への理解を図り、学校組織マネジメントの運営を促進する仕組みを作りたいと私は考えています。
教科横断的な取り組みや地域との連携は、手持ちのリソースの中ですでに実践している教員は多いのですが、組織的な取り組みではないのが課題です。各学校にコーディネートできる指導教諭を1人以上配置し、組織的に運営することで実現可能ではないかと考えています。
現在、「チョークジャック」のワークショップなどを通じて、生徒の可能性に気付いた教員が徐々に増えてきています。私にとって、みなさんが同志です。全国のいろんな地域で仲間を増やしていき、日本の教育をよりよく変えていきたい。それが私の構想です。