「けテぶれ」や「NKS」などの多彩な実践を展開し、著書がベストセラーになるなど注目を集める葛原祥太・兵庫県西宮市立夙川(しゅくがわ)小学校教諭。次から次へと生み出されるユニークな実践の原点は、どこにあるのか。そして、葛原教諭が感じる日本の学校教育の不自然さとは何なのか。問題意識のルーツをたどる。

実を言うと、大学は経済学部で、そのときは教師になろうなどとは全く思っていなかったんです。教員免許も大学院に進学してから取得しました。20歳の頃の自分に「お前は10年後には教師をやっているぞ」と言っても、絶対に信じないと思います。
大学時代はずっとダンスをやっていて、舞台関係の仕事がしたいと思っていました。そのため、就職活動はテレビ局を中心に受けていましたが、軒並みどこも落ちてしまったんです。
すっかりやる気を失い、改めて自分を見つめ直したときに、ふと、高校生の頃に教わっていた予備校の講師がすごく格好良かったことを思い出しました。自分も勉強自体は嫌いではなかったし、「教える仕事っていいかもしれない」と思って予備校の就職説明会に出てみたら、昼夜逆転の生活であることが分かりました。私は朝型なのでそれだけは受け入れられなかったんです。
そこで、朝から教える仕事は学校の教師だと思い、教員免許を取ろうと考えました。そんなときに、たまたま兵庫教育大学の教職大学院のパンフレットが目に入ったんです。そこには、小学校教員を養成するコースがあって、「小学校の先生か。まあいいか」と思いました。
そうなんですよ。でも、大学院に入って教育学を勉強し始めたら、これがとても面白かった。論文を書くのも楽しくて、実を言うと「NKS」は大学院の頃にまとめた「算数の文章問題をどうやって解かせるか」という研究テーマが着想の原点になっています。
大学の頃はダンス漬けだった自分が、大学院に入ってがらりと変わりました。毎日のように図書館に通って、時には「人って何だろう」などと哲学的なことを考えてみたこともありました。大学院での3年間の学びは、自分にとって本当に大切な期間でした。
ところが、教師として採用されて、いざ学校現場に入ると、ものすごく違和感を覚えたのです。
学校文化が思考停止の塊のように見えたのです。「なぜ、体育座りをさせなければならないのか」「なぜ、文房具に名前を書くことを徹底するのか」「なぜ、文房具の貸し借りをしてはいけないのか」「なぜ、名札を全員付けなければいけないのか」……。学校の当たり前に対する「なぜ」の嵐が、私の頭の中で巻き起こりました。加えて、そうした疑問を他の教師にぶつけても、誰もまともに答えてくれませんでした。
授業を見てもらっても指摘されるのは、「あの子は椅子に座っていなかった。あの子は机の上に水筒が置いてあった。なぜ注意しないのか」といったことばかり。今ではそうした指導の重要性も理解できるようになりましたが、当時は「どうして授業について何もアドバイスしてくれないのか」「なぜ、子供が机以外の場所で学んでいるのがだめなのか」と思っていました。正直、1~2年目は毎日のように「教師を辞めたい」と考えていましたね。
振り返れば、私はもともと自分の頭で考えることが好きだったのです。それに気付いたのは大学院時代で、子供の頃は学校の授業で自分の頭で考えることの楽しさを感じたことがありませんでした。小学校の頃に友達と一緒に過ごした楽しい思い出は残っていても、学校の授業で教師に言われた印象的な一言は何も残っていなかったんです。
だから、どうせ辞めるならそういうことをやってから、惜しまれながら辞めてやろうと思いました。つまり、大学院で私が体験したような、「どっぷりと学びの世界に浸る経験」を、目の前の子供たちにさせてやろうと思ったのです。

「けテぶれ」や「NKS」を宿題だけでなく、授業やさまざまな活動で自分の学びそのものを常に意識することにより、子供たちは自分で学びを深める楽しさを味わっています。これまでのように、プリントをひたすらこなすだけで時間が過ぎていく、インプットだけの授業をしていてはだめです。
これから先、学びのコンテンツは飛躍的に増えます。今もすでに、YouTube上で分かりやすい授業動画が山のように配信されています。塾に行かなくても、学びのアンテナが高い子供は、そういうコンテンツに自らアクセスして、知識を獲得していきます。そんな子供が増えていく中で、教師が既存の学習方法しか認めないようなことをしていたら、公教育はあっという間に崩壊するでしょう。みんな学校を捨て始めると思います。
とはいえ、現状で学校というハード的な基盤がこれだけ整備されているのに、それを使わないのはもったいない。だからこそ、学校でどのような学びを生み出すかがとても大切になると思います。
どのような学びを生み出すかは、誰かに言われるものではなく、個々の教師が自ら考え出さなければなりません。「学ぶとはどういうことか」。この問いに対する教師の思考が絶対的に足りておらず、教師自身の「主体的な学び」が問われています。
子供が成長する姿を見て「これまでできていなかったことができるようになった」「行動が変わった」というくらいは、誰にでも分かります。そうした成長は氷山の一角にすぎず、教師が見なければいけないのは、本人も気付いていない海中の奥深くに隠れている部分です。それを言語化して本人に渡していく必要があります。その子供にとって、隠れていた部分が海の上に上がってくれば、氷山の標高は高くなり、さらなる高みを目指していくことができます。
私は子供たちの学びを考えるときに、どういう姿が教室での学びとして一番適しているのかを常に考えるようにしています。「全員に課すに値する内容とは」「個々人が自分で考え、選択すべき内容とは」という問いです。学校は特殊です。その地域に住んでいる子供が問答無用で集められ、同じ年齢でランダムにクラス分けされて、担任は1年間変わらないし選べない。そういう特殊な状況を、私一人では変えられません。それならば、その空間を任された者として、子供たちに提供すべき学びとはどのようなものか、常に考え続けなければならないと思います。
「虎の威を借る狐」ということわざがありますが、「誰かが言っているから」ではなく、「あなたはどう考えるのか」ということです。人文科学はエビデンスよりもエピソードに影響されます。教育学を語る上でエビデンスも大事ですが、それは判断材料の一つにすぎません。大切なのは、それを踏まえてどう考えるのかです。
そして、公立学校の教員である以上は、学習指導要領の理念を具現化する上で、有効な方法なのかという視点を外してはいけません。学習指導要領を再現するために、教師は教室にいるのですから。
「けテぶれ」はおかげさまで、多くの人に手に取ってもらえました。しかし、「けテぶれ」はテクニックではなく考え方です。私の著書を読んで、自分なりに考えて、その結果として実践が「けテぶれ」とは全く別のものになったとしても、それが本人の思考の先に表出されたものであるならば構いません。
そうした自身の思考や考えを、一人一人の教師がしっかり語れなければいけません。誰に語るのかといえば、真っ先に子供たちです。子供たちと一緒に目標を共有し、学びを通じて付けるべき力が本当に身に付いていることを子供たちが実感できなければ、意味がないと考えています。
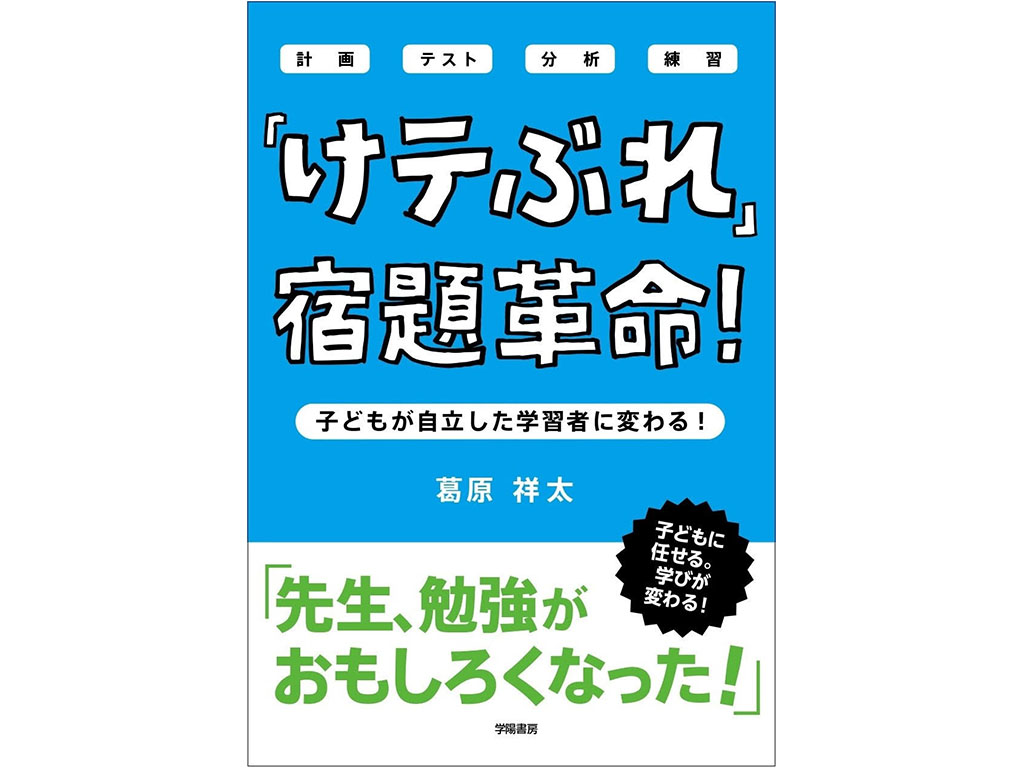
葛原祥太(くずはら・しょうた) 兵庫県西宮市立夙川小学校教諭。1987年、大阪府生まれ。同志社大学を卒業後、兵庫教育大学大学院に入学。卒業後、赴任した兵庫県の公立小学校で「けテぶれ」をはじめとするユニークな実践を展開。SNSなどを通じて広まり、話題となる。著書に『「けテぶれ」宿題革命!』(学陽書房)。趣味はカフェでくつろぎながら思索にふけること。