最近のビジネス界で、チームの生産性を向上させるためのキーワードとして注目を集める「心理的安全性」。学校においては、子供たちの学びに対するレディネス(心理的・物理的に学ぶ準備が整っている状態)に寄与するものと考えられている。組織開発ファシリテーターとして、長年にわたりビジネス現場や教育現場の組織開発を手掛けてきたナガオ考務店代表取締役・長尾彰氏に、第2回では心理的安全性といじめの関係性について聞いた。(全3回)
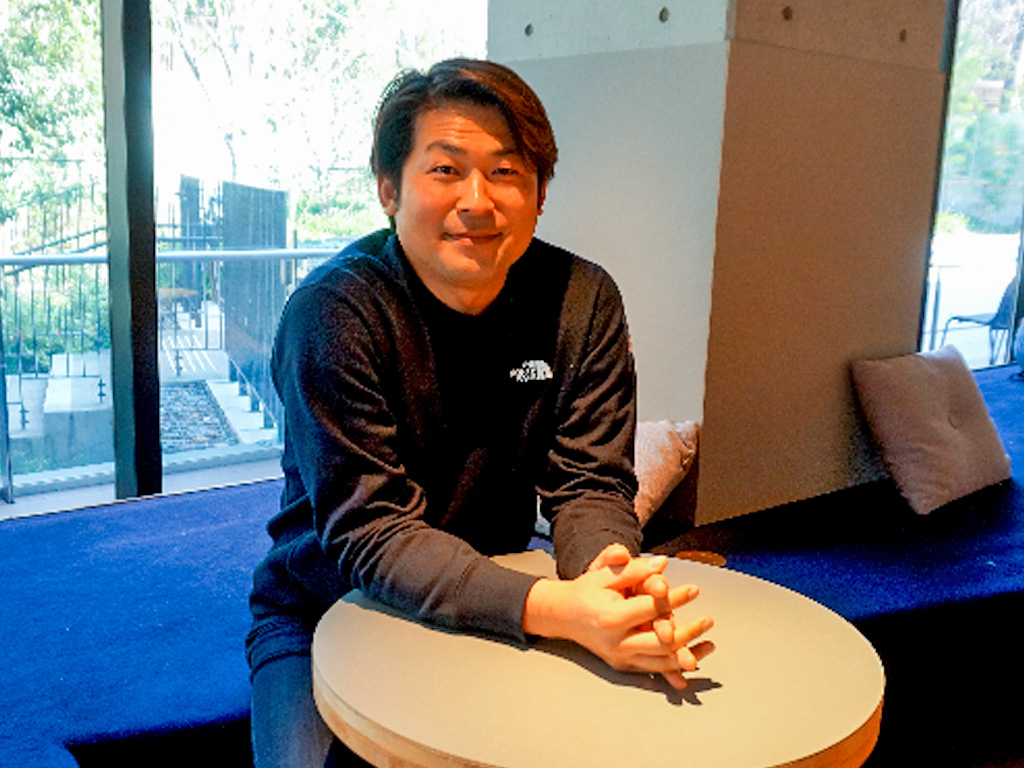
人は異質なものと出合えば不安が生まれますから、心理的に安全な状態をずっと保つのは難しいと思います。大人であれば、自分が属する環境はある程度自分で選ぶことができますから、職場が嫌になったら転職するという選択もできるかもしれません。しかし、子供が所属する「学校」や「学級」という組織は簡単には変えられないので、固定的な人間関係の中で心理的不安が生じるとつらいものがあります。
異質なものと共存していくのが社会だとすると、子供たちは社会に出るまでに、心理的安全性の築き方を学ぶ必要があります。異質なものに出合ったときに、自分の心がどのように動いて、それに対してどういった行動を取り、どう対処していくかを考えて学ばせることが、学校という場の役割の一つです。
自分自身がどんなことに対して不安を感じるか、自分自身で気付けることは重要です。人間は何に対して怒っているのか分からずに怒っていることもある。怒りの理由が分かれば途端に怒りの感情が消えていくこともあるし、不安を感じる理由が分かれば、不安に対処していくことができるようになります。
一方で、自分の気持ちを自分の言葉で話すのは、簡単なことではありません。僕は大人と子供の違いは、「言葉を持つか持たないか」だと考えています。つまり、自分のことを自分の言葉で話せるのが大人、できないのが子供です。20歳だから大人ではなく、60歳でも自分の言葉で話せない人には「子供っぽい人だ」と未熟さを感じることがありますね。
教員の役割は、子供たちが自分のことを自分の言葉で説明できるようにサポートしていくことだと考えています。教育基本法の第1条には、「教育の目的は人格の完成を目指す」とありますよね。その「格」は何で作られていくのかというと、「言葉の豊かさ」なのかなと。言葉は本当に大事だなと思います。イエナプランの学校が毎日を対話の時間で始めているのは、言葉を使ってお互いの状態を理解し合う練習、つまり「聞く」「話す」の練習をする必要があるとの考えに基づいているからだと思います。

僕が理事を務める学校法人茂来学園大日向小学校(長野県)は、日本初のイエナプランスクールの認定校で、「誰もが、豊かに、そして幸せに生きることのできる世界をつくる」という建学精神の下、さまざまな取り組みによって個を尊重し、協働して学ぶ教育を実践しています。
しかし、どんなに個を尊重する教育を実施していても、どんなに教員や子供たちがお互いにオープンであることを心掛けても、人間が生き物である以上、いじめを撲滅することはできないと僕は考えています。
誰の中にも、いじめが起こることに対する不安はあると思います。でも、いじめが起きても、対処できる体制を築いておくことが、学校の心理的安全性につながります。
ささいなトラブルを見過ごさず、当事者と先生の間で終わらせるのではなく、子供、先生、保護者など学校に関わる全ての人が「自分事」として捉えることができる仕掛けや設(しつら)えが必要だと思います。
いじめは学校全体の問題であり、その人の尊厳に関わる問題。誰が誰をいじめたのか、なぜ起きたのか、これから起きないようにするためにはどうしたらよいかなど、みんなで真剣に考えることが大事です。いじめた側を叱り、いじめられた側を慰めるだけではなく、大日向小学校では子供たち一人一人が「他人に起きた出来事ではなく、自分たちの学校の中で起きたことである」と捉えられるような体制づくりを試行錯誤しながら進めています。このプロセスが、学校全体の心理的安全性を生み出すことにつながると信じています。
加害者からすれば「たかが上履きを隠しただけ」かもしれない。でも、被害者にとっては大きな傷になった。これを学校全体で「おおごと」にしていくと、今度は加害者が傷ついていきます。つまり、被害者も加害者も傷を負うことになりますが、その傷を周囲のみんなが認知していくことで、「傷ついた人に対して自分は何ができるだろうか、どうすべきだろうか」と、それぞれが自分自身の関わり方を考えて行動できるようになるのではないでしょうか。被害者だけでなく、加害者の立場にも立って考えていく。これは、子供たちのみならず、大人にとっても重要な学びです。
一人一人がかけがえのない存在ですから、学校という組織として、どんなささいなことも見過ごさない、軽んじないことが、全員の心理的安全性につながると思います。
僕は今、「エア社員」という肩書で全国十数の企業に籍を置き、さまざまな組織課題に携わる仕事をしています。発生している問題について、関係者にインタビューしながら詳しく調べていくと、「怒られたくない」と思ってついやってしまったことが発端になっていたり、部署間のコミュニケーション不足の問題であったり、原因も解決手段もさまざまです。しかし、僕が月に数回企業を訪問することが、組織全体が問題に向き合うきっかけになっている所もあります。問題が起きても、解決していく仕組みがあるということが、学校だけでなく、どんな組織の心理的安全性にも必要なものだと思います。

長尾彰(ながお・あきら) ナガオ考務店代表取締役、(一社)プロジェクト結コンソーシアム理事長、茂来学園大日向小学校理事。日本福祉大学卒業後、東京学芸大学で野外教育学を研究。冒険教育研修会社、玩具メーカー、人事コンサルティング会社を経て独立。企業、団体、教育、スポーツの現場など、約20年にわたって3000回を超えるチームビルディングを実施。現在は複数の法人で「エア社員」の肩書のもと、事業開発やサービス開発、社内外との横断プロジェクトを通じた組織づくりをファシリテーションする。著書に『宇宙兄弟「完璧なリーダー」は、もういらない。』『宇宙兄弟 今いる仲間でうまくいく チームの話』(ともに学研プラス)がある。