普段は公立小学校で教壇に立ちながら、女子ラクロスU19の日本代表ヘッドコーチも務め、一斉休校中には2000人規模のオンラインイベントを主催するなど、その活躍に注目が集まる東京都調布市立多摩川小学校の庄子寛之指導教諭。次々と新たなことにチャレンジし、成果を生み出しているが、これらは全て庄子教諭の「とにかくまずやってみる」行動力によるものだという。インタビュー最終回は、その行動力の源や、これから必要な教員の力について迫った。(全3回)
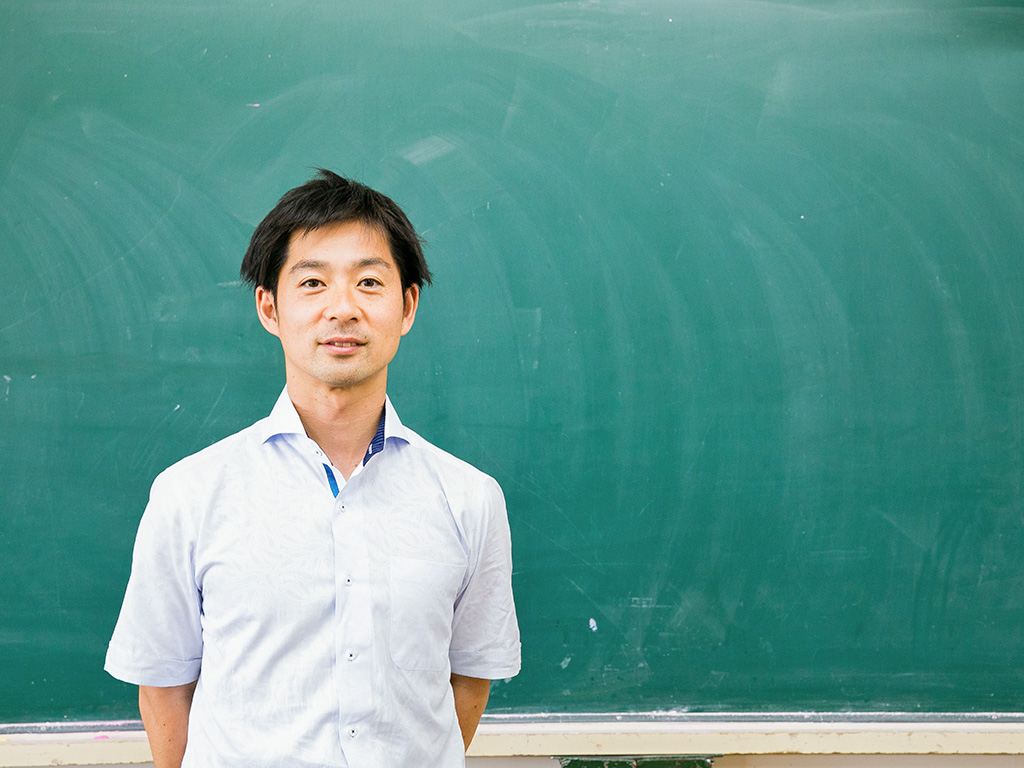
子供とか大人とか関係なく、私は人が大好きです。人と話すことでたくさんのことを学んでいます。だから、いろいろな人に会っているというのが大きいかもしれません。
人と会うのは教育のためにしているわけではなく、基本的には自分のためです。何事も「人のため」と思ってやっていると苦しくなってしまうので、「自分のためにやることが、人のためになればいいな」と思っています。
具体的には、教育関係のいろいろな研究会に参加したり、興味がある人がいたら自分から会いに行ったりしています。例えば、「この本、面白い!」と思えば、その著者の講演会などに行きます。いろいろなセミナーに参加することで新たな縁も生まれ、自分が行動するきっかけにもなっています。
こうしてすぐに会いに行く、すぐにやってみるというのは、大学生時代からやっているラクロスの影響が大きいですね。
私は高校時代まで野球部で、大学に入ってからラクロス部に入部しました。といっても、最初は部員が3人しかいませんでした。ラクロスは1チーム10人で行うスポーツなので、当然、成り立ちません。
ラクロスはマイナーなスポーツなので、他のスポーツと比較しても他大学との横のつながりが強く、いろいろな大学に行って一緒に練習させてもらうことができました。大学3年からは社会人チームに入れてもらい、そこで日本一も経験させてもらいました。
日本代表クラスの選手たちと一緒に練習をすることで、良い意味で「日本代表の人も、普通の人なんだ」と分かりました。それからは、どんな立場の人にもためらわずに会いに行ったり、話したりすることができるようになりましたし、やはりすごい人ほど努力をしているということも、身をもって知りました。
はい。教員1年目は、まだ休日は社会人チームでプレーもしていたので、ものすごく忙しくしていました。いつも午後6時からはラクロスの練習があったので、必然的に学校からは早く帰っていましたね。
その頃、ちょうど母校の大学の女子ラクロス部からコーチも頼まれました。当時は女子ラクロスのコーチを男性がやるのは珍しかったのですが、そこから大学リーグで4部から1部まで昇格するなどの実績を残せたことで、昨年は女子ラクロスU-19の日本代表ヘッドコーチをやらせてもらい、カナダで行われた世界大会にも出場しました。
ラクロスのおかげで世界各国に行けたし、教員以外のいろいろな企業の方たちと出会い、話す機会が持てたと思っています。

視野です。視野が広がると、指導法も変わります。「こうあるべき」「ねばならない」が圧倒的に減るんです。
例えば、教室で「○○をやりましょう」と言ったのに、やっていない児童が目の前にいたとします。その児童に対して、「やりなさい」と注意しなくなりました。
たいていの場合は「どうしたの?」ですね。その子がどうしてやらないかが分かっている場合は、放っておくこともあるし、その子が「やらない理由」を探すようになりました。やることがベストだとは思わなくなりました。
教師が指示したことをやらないことに関して、人に迷惑を掛けなければ、そんなに問題はないと思うのです。むしろ、その子に「やりなさい!」と強引にやらせることによって、周りの子に迷惑が掛かったり、学級崩壊につながったりするようなケースもあると思います。
言う通りに子供たちを動かせるのが「良い教師」なのではありません。子供たちは一人一人バラバラでいいし、何よりも「生きることが楽しい」と思えることの方が、今の時代には大切です。
家でお母さんに怒られてばかりだったり、塾通いで大変だったり、子供たちは一人一人、いろいろな事情や背景を抱えています。そういう背景を分かろうとするかしないかでは、大きく違うのではないでしょうか。
だからこそ、子供が寝ていたら「なんで寝ているんだ!」ではなく、「昨日、何かつらいことでもあったのかな?」と想像する。視野が広がることで、より子供の背景を見ようとするようになりました。
私は子供が好きで教員になったわけではありません。子供が嫌いだとかそういう意味ではなく、子供を子供として見ていないからです。実際、大人よりも子供の方が柔軟な発想を持っているし、誰にでも忖度(そんたく)なく接します。奇麗事ではなく、日々、私は「子供から学んでいる」と感じています。
だから、他の教師と比べて「教えている」時間が、圧倒的に少ないと思います。とにかく対話して、子供と一緒に面白がる。
学校教育で何ができるのかを考えると、我慢とか忍耐ではなくて、希望であってほしい。だからこそ、「ねばならない」を極力減らして、自分一人の行動で「クラスが変わる」「学校が変わる」「社会が変わる」と思えるような子になってくれるよう、自由に、良い意味で「ゆるく」やっています。
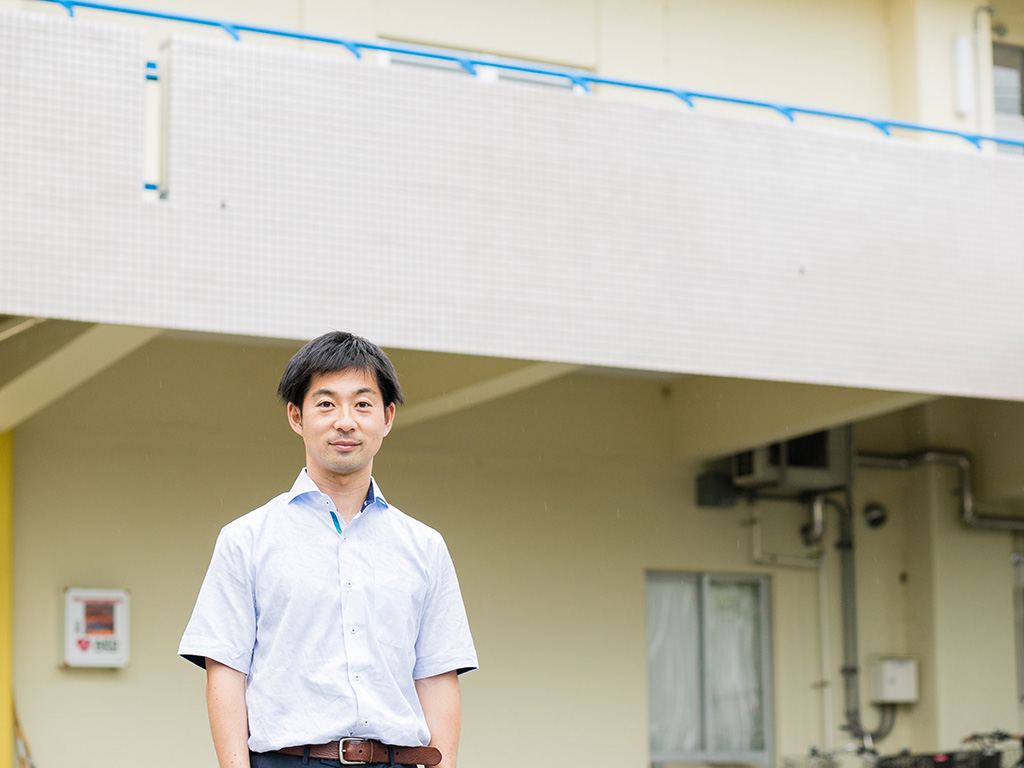
ラクロスの社会人チームに入った頃からコーチングを受けていて、今でも毎年目標を立て、定期的に振り返るようにしています。
自分なりの目標を持つと、何かやろうと誘いを受けたときに、自分の目標と照らし合わせてすぐに「イエス」か「ノー」かの判断ができます。「すぐやる」ためには、自分がやりたいことを明確にしておくことがポイントだと思います。
まず、なんでもやってみることです。やってみると、必ず問題や課題が出てきます。でも、その分、成果もある。やってみないと分からないのに、動かないことの方が問題だと私は思います。
私は、その過程が「ワクワクする」と思ったものは、すぐにやります。やってみて結果が出ようが出まいが「ワクワクする」と思うものは、やるようにしています。
コロナも含め、時代が大きく変わることをみんな感じています。今までの教育が悪かったということではなく、時代が変わる中で、今までと同じ教育をしていてはいけないということです。
そのためには、自分とは違う教育を受けてきた世界の人たちや、自分とは考えが全く違うような人、教師以外の仕事をしているいろいろな人と対話する。そして今、自分の中にある「ねばならない」を手放し、固定概念を捨て、アップデートしていく必要があると思います。
庄子寛之(しょうじ・ひろゆき) 東京都調布市立多摩川小学校指導教諭。前女子ラクロス19歳以下日本代表監督。2019世界大会日本史上最高タイ5位入賞。学研教育みらい道徳教科書編集委員。みずほフィナンシャルグループ金融教育プロジェクトメンバー。文部科学省がん教育教材作成ワーキンググループ委員。著書に『学級担任のための残業ゼロの仕事のルール』、共著に『before&afterでわかる! 研究主任の仕事アップデート』、編著に『Withコロナ時代の授業のあり方』(いずれも明治図書)など多数。