福井県立若狭高校で生徒主体の探究活動を支え続けてきた小坂康之教諭は、自身も大学院で「へしこ」の研究に取り組むなど、探究的な活動にまい進している。そうした研究活動と日々の教育活動を通じ、高校教育の在り方について考えるようになったと話す小坂教諭に、インタビューの最終回では自身の研究活動を通じて感じたこと、地域に根差した公立高校の在り方などについて聞いた。(全3回)
――大学時代に食品の研究をされていたそうですね。その経験は今に生きているのでしょうか。
大学時代、研究はしていましたが、現場での実践経験がなく、どこかしっくり来ないところがありました。福井県に来て漁師さんと関わる中で「この魚を利用しようと思っても水分が多くて」とか、「食品の製造過程で、こういう問題が発生するんだけれど、どうしたらいいでしょう」などと聞かれて、うれしく思うと同時に答えられない自分がいて、「これはマズイな」と思っていました。
ちょうど福井県には学校に籍を置きながら福井県立大学に2年間派遣してくれる制度があったので、それを使って研究させていただくことにしました。そこで、食品化学の研究をされている大泉徹教授から、地元の名産の「へしこ」の研究をしないかと声を掛けられたのです。
実は、教員になって地域に通い始めた頃、先輩教員から「へしこ製造の授業をしてみて」と言われたことがありました。へしこづくりが盛んな小浜市の川崎地区へ行き、加工業者を訪ねて作り方を教えてもらいました。
へしこはサバを2週間ぐらい塩漬けして作ります。その時の塩の量について「どれぐらい入れるのですか?」と聞くと、「両手ごっぽり(いっぱい)」と言うんです。何グラムとかじゃなく、感覚なんですね。実際に両手いっぱい分を量り取ってみたら、おおむね魚体の20%ぐらいだったんです。その他にも製造におけるさまざまな鉄則があったのですが、なぜそうするかを業者の方に聞いても「分からん」とのことでした。へしこの作り方は口頭伝承で伝わってきていて、科学的にはまとまっていなかったんです。
そこで指導教官の大泉教授の下、へしこに含まれるうま味成分がどうやって出てくるのか製造過程における原理を明らかにすることを目的に研究を始めました。派遣期間2年が終わった後も後期課程に進み、学校が終わって夜9時から夜中の12時頃、時には朝方まで論文を書くような生活を3年ほどしていました。
先行研究では微生物がうま味を作り出すと考えられていたのですが、実は微生物は環境を整えているだけで、うま味を作り出すこと自体には関係が少なかったことなど、新しい発見をすることができました。私自身も生徒と同じように、思い切り探究させてもらうことができたのは大きな経験でした。
――先生のそういう姿を見た生徒たちからは、何か反応がありましたか。

食品加工系や水産系の会社に就職している卒業生の中には「先生、また一緒に研究しましょう」みたいに言ってくれる人もいました。在校生の中にも、自分たちの先生が同じように研究していることを喜んでくれる子がいました。
へしこの研究活動を通じ、学問の面白さや奥深さを痛感しました。化学的なことだけでなく、物理的なことも学び直さなければいけなかったし、海外の論文を読むために語学もやり直しました。でも、目的をもって学ぶことや学問そのものの楽しさを改めて実感して、その楽しさを生徒たちにも味わわせたいし、何より主体的に取り組ませるようにしたいと改めて考えました。
――探究は、生徒が楽しく夢中になって取り組むことが大事なのですね。
米国の高校を訪問した際に衝撃的だったことがあります。私が「何のために学ぶの?」と質問すると、日本の高校生の多くは「将来のため」「お金を稼ぐため」「大学に進学するため」などと答えますが、米国の高校生は大半が「楽しいから学ぶんです」と答えたんです。とても感銘を受けて、「うちの生徒もそう言えるようにしなければ」と思いました。
――これからの目標について教えてください。
統合の時から続いている目標設定の会議があり、海洋科学科ができて10年ほどがたっているのでそろそろ設定をし直した方がいいと考え、関係者に集まってもらいました。その時に、漁師の方や地域のNPOの方から、「この地域で生きて行くことの意味」や「幸せ」などの言葉が出てきたんです。以前は、思考力や興味関心といった言葉が目立っていたのですが、「この地域で生きていくことの幸福」というような発言が、議論の中で相次ぎました。
そこで、OECDの「ラーニング・コンパス」にも出て来る「ウェルビーイング」のための資質・能力とは何だろうかと考え、生徒を含むいろいろな人に幸せについてインタビューをしました。そして、「幸せの在り方」は人それぞれだけれど、「幸せになるための力」は同じではないかと感じました。
そこで現在は「幸せになるための資質能力」についていろいろと検討し、そのためのカリキュラムづくりに取り組んでいます。私たち学校関係者は、何のために生徒の資質・能力を育てているのかと言えば、やはり「みんなが幸せになるため」です。これを目標に据え、いろいろな人と対話して明らかにしていくことが大事だと感じています。
だから、今の目標は「一番幸せな学校をつくる」ことです。生徒たちが本校に来たら幸せになる、そういう学校づくりをしたいなと思っています。そのためには「生徒だけではなく教員も幸せにならないと」とも考えています。
私自身は今年度から進路部長をしていまして、生徒たちには自分のやりたいことや興味関心をベースに、第一志望の「分野」を目指すように呼び掛けています。探究を通じて自らと対話し、自分の好きなものが見つかり、それを世の中で起きていることと結び付けることで進みたい分野を考えていくのです。そうすることで、主要教科の学力も上がるんです。
私は水産の出身なので経験が浅くて進学指導がよく分かりません。だからこそ、まずは目の前にいる生徒の模試の結果や日頃の学校の成績の分析を根拠に対応することを大切にしています。そして、何よりも本人が本当にやりたいことを明確にし、そこに進もうと思ったときに必要な能力ややるべきことを、対話を通じて自発的に気付かせるようにしています。生徒自身が「これをしているときに価値を感じる」という部分を一緒に探す。共有することが大切だと考えています。
並行する形で、生徒の「キャリア観」や「勤労観」を学校全体で育てていくための指導体制づくりも進めています。最近は「個別最適化された学び」が叫ばれ、ICTの活用を進める動きもありますが、そうしたツールに頼るだけでなく、担任や科目担当の教員がコミュニティーをつくり、目の前にいる生徒が社会を生きていく上で何が必要かを考えていくことが大事だと考えています。
――教職員同士のコミュニティーの在り方は非常に重要ですね。
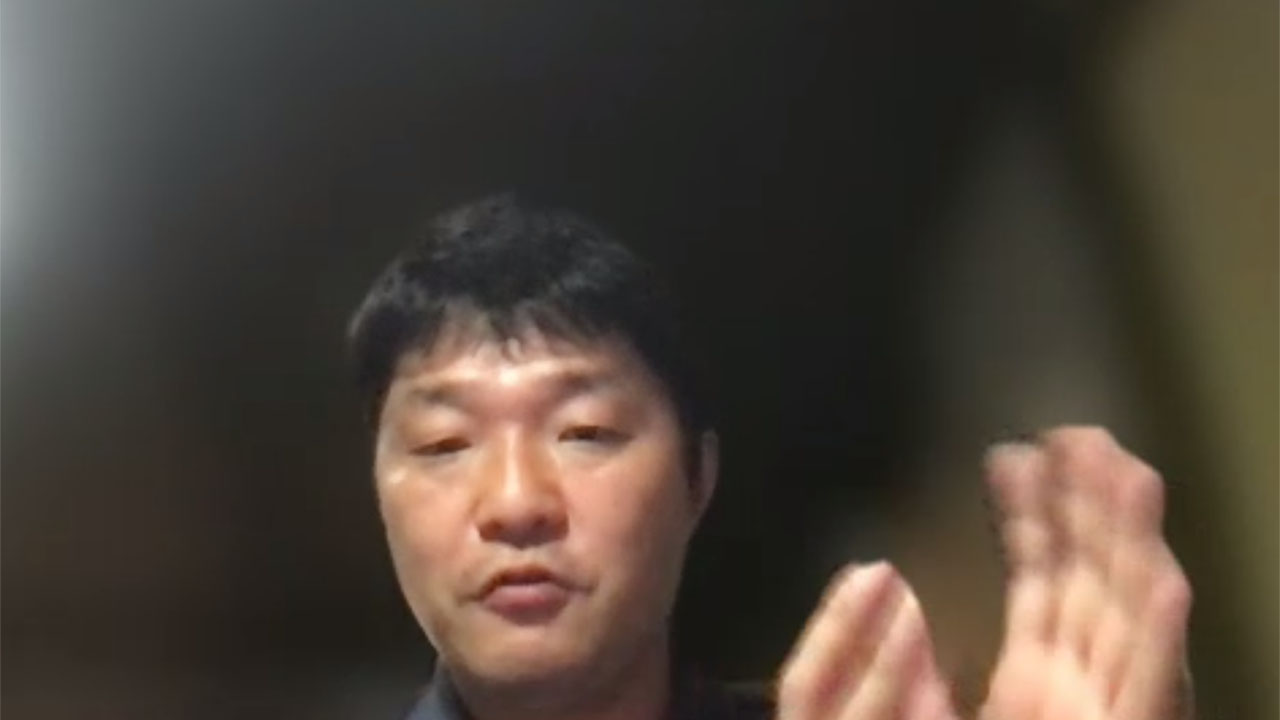
本校は目標を明確にし、それを共有して授業づくりしているため、授業研究がとても盛んです。教科・科目の枠を超え、毎日どこかの教室で授業を見せ合っているような雰囲気があります。探究の方向性も、そうした関係性の下で対話を重ねながら決めています。
本当にたくさんの多様な考え方を持った教員がいるのですが、そうした交流の中でお互いを認め、生徒を通じて思いを重ねられた瞬間に、大きな幸せを感じます。だから、やっぱり幸せな学校をつくる上で教員間の対話の場は重要ですし、教員の多様性を担保する上でも大切だと思います。別に、飲み会なんかしなくてもできるんです。
――今の高校教育について、課題に感じていることはありますか。
私自身は今年度、初めて普通科の主任もしています。ただ「普通科」という名称に違和感があって、最近は全国的にも「探究科」みたいな名称に変更しつつあります。普通科にいる生徒は、実は皆「普通」じゃないんですよね。活発な子もいればおとなしい子もいて、実際には「多様科」なんです。
海洋科の場合は、「海が好き」という点で共通項がありますし、文理探究科の生徒はトップ層の学問的な楽しみを知っていて、似た雰囲気があります。でも、普通科には本当にいろいろなタイプがいて、全く普通じゃありません。このことを認識した上で「普通科」の生徒をサポートしていくには、やはり教員の多様性をいかに保つかだろうと考えています。まだまだ実践は続きます。
【プロフィール】
小坂康之(こさか・やすゆき) 福井県立若狭高校海洋科学科教諭。博士(生物資源学)、通称へしこ博士。「楽しいから学ぶんだ!」をモットーに海の教育、探究的な学習に取り組む。今までに地域と連携した海の再生活動や地域食材を利用した商品開発などを指導。文部科学大臣優秀教職員、福井県優秀教職員、授業名人。東京水産大学水産学部卒業、福井大学教職大学院、福井県立大学大学院生物資源学研究科修了。