教員が無意識に子どもの心を傷つけている場面を目にしたことはないだろうか。体罰やわいせつ行為のように、明白に「あってはならない」ものではなくても、決して適切とは言えない言動。東京都立矢口特別支援学校の川上康則主任教諭は、そうした教員の行為を「教室マルトリートメント」と名付け、学校現場に警鐘を鳴らす。公認心理師、特別支援教育士スーパーバイザーでもある川上教諭に、その実情や子どもに与える影響を聞いた(全3回)
──教員の不適切な指導を定義した著書『教室マルトリートメント』が注目を集めています。「教室マルトリートメント」とは、具体的にどんな行為を指すのでしょうか。

分かりやすい例では、事情を踏まえない頭ごなしの叱責(しっせき)、子どもを委縮させるような威圧的・高圧的な指導などを指します。これらは「心理的虐待」に類似する指導だと捉えています。
他にも、「教科書やノートを忘れた子どもを一定時間許さない」「漢字の『とめ・はね・はらい』に不必要なほど駄目出しする」など、子どもの意欲を失わせる指導も当てはまると考えています。
――学校現場ではこれまで黙認されてきたような行為も該当するのですね。
本来、子どもの成長や発達を応援する立場にある教員が、それを阻害しているような場合は、基本的に「教室マルトリートメント」として見ています。ですから、「褒めるべきときに褒めない」「子どもの話を聞かない」「必要な支援を行わない」「子どもにとって危機的状況が起こっているのに関与しようとしない」などは、教員という立場を放棄しているのと同じですから、「ネグレクト」に類似した指導と考えています。
「マルトリートメント(mal=悪い)+ (treatment=扱い)」という言葉は、基本的に親子関係の養育において使われている概念で、子どもに対する「不適切な養育」「避けたい関わり方」といった意味で使われます。
学校現場でも、家庭における「心理的虐待」や「ネグレクト」に類似した指導が日々行われています。子どもを深く傷つけるこうした指導はこれまで見過ごされてきましたが、見つめ直さなければいけません。
――著書『教室マルトリートメント』を執筆したきっかけを教えてください。
ある特別支援学校で強い圧をかける指導が横行していたのを見たのが、きっかけの一つです。特にベテランの教員が非常に高圧的で、少しでも枠を外れた行動をする子どもがいたら、大声で怒鳴ったり、力ずくで抑圧したりするなどの指導を繰り返していました。

困ったことに、そうした指導が学年全体にも浸透して、若い教員がベテランの模倣をしていました。「こうすれば子どもが言うことを聞く」と、若手が誤った成功体験を積んでいるような状況もあったのです。さらには、「ベテランが子どもに暴力を振るう前に、自分が厳しく指導して子どもを守ろう」とするような対応も見られました。
子どもに笑顔はなく、パニックに陥る子どもや登校をしぶる子どもが続出しました。当の子どもは、教員の対応による苦しさを訴えられません。「登校しぶりは親が甘やかすせいだ」と今度は保護者が責められ、事態は改善されないまま時間だけが過ぎていきました。
――そうした状況はどのくらい続いたのでしょうか。
私が知る限り、3年くらいは壊滅的な状況が続きました。ただ、その後は積極的に改善に取り組み、教員の異動などもあって、徐々に落ち着いていきました。
ここまでひどい状況ではないにしても、圧の強いタイプの教員が教室にいるだけでそうした雰囲気を醸し出し、無自覚に子どもをコントロールしているようなケースは多々あります。こうした教員は、体罰ほどではないからと見過ごされたり、「子どものため」などと指導の名の下に肯定されたりしがちです。
私は、子どもを支配して教室の雰囲気を不穏にさせる教員の言葉を「毒語」と名付けています。「何回言ったら分かるの?」という問い詰めや、「じゃあ◯◯できなくなるけど、いいんだね」などの脅し、「駄目って言ったよね」と責任をなすりつける声掛け、「じゃあ、もういい」と見捨てる言葉などがその例です。
――こうした指導が続くと、子どもにはどんな影響が出るのでしょうか。
特別支援学校の中学部で担任をしていて、小学校の特別支援学級から入学してきた子どもを受け持つと、フラッシュバックを起こして攻撃的・破壊的な行動に至るケースがあります。その際、必ずと言っていいほど、過去に教員から投げ掛けられた言葉が出てきます。二次障害としての強度行動障害も、「教室マルトリートメント」に近い対応から生まれているのではないかと疑念を抱くようになりました。
家庭か学校かという場を問わず、不適切な関わり(マルトリートメント)は共通して子どもたちに以下の3つの影響があると考えています。
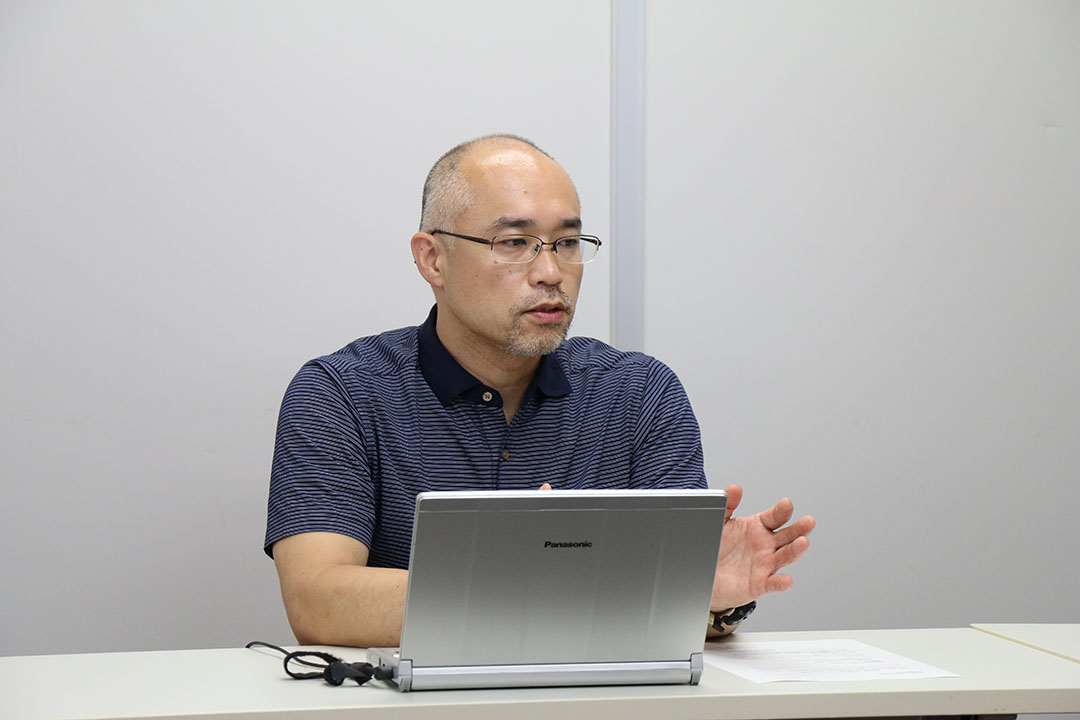
第一に、子どもは極度のストレスを感じた際、「何とか適応しよう」と行動してしまうこと。第二に、マルトリートメントとは残虐性の高い行為ではなく、日常的に起こっている、曖昧で地味なものであること。こうした点からも、マルトリートメントは家庭での出来事に限定されず、学校現場の日常と重なるところが大きいと考えています。
そして第三に、大人の行為が「子どもの将来を思って」「今のうちに何とかしておかないと」などといった使命感に基づくものであるケースが多いこと。この部分も、やはり学校現場に当てはまります。子どもをよく理解しないまま、「直そう」「変えよう」と強い使命感で動いている教員は少なくないでしょう。
――そこで「教室マルトリートメント」という言葉を作り出したのですね。
この言葉は、出版社の編集者さんとの雑談から生まれたものでした。「教室で子どもがマルトリートメントに近い指導を受けている」という問題意識から、そうした言葉を考えつきました。
私は特別支援教育コーディネーターの立場で、通常学級の支援もしています。そうした日々の中で学級崩壊に近いケースを見ることも多く、子どもよりも教員の在り方に問題があると気付きました。前年度の担任が高圧的な指導で子どもにものを言わせない学級をつくった場合、担任が変わって圧が変化した時、学級が荒れるというケースが実に多いのです。
一見、統率されているように見える学級が、実は家庭でのマルトリートメントに近い状態になっているのではないかという懸念が、問題意識の出発点になっています。
【プロフィール】
川上康則(かわかみ・やすのり) 1974年、東京都生まれ。東京都立矢口特別支援学校主任教諭。NHK「ストレッチマン・ゴールド」番組委員や一般社団法人日本授業UD学会理事などを歴任。『教室マルトリートメント』(東洋館出版社)、『〈発達のつまずき〉から読み解く支援アプローチ』(学苑社)、『こんなときどうする? ストーリーでわかる特別支援教育の実践』(学研プラス)、『通常の学級の特別支援教育 ライブ講義 発達につまずきがある子どもの輝かせ方』(明治図書)など著書多数。