秋田大学からバイオマスプラントを移設し、校内で出る食物残渣と栽培したバジルを利用して「バイオバジルオイル」を生産・販売する三重県立相可高校生産経済科。活動の背景には、長年取り組んできた園芸福祉の活動と、NPO法人の設立で培ってきたソーシャルビジネスの取り組みがあった。同校の新谷和昭教諭へのインタビュー2回目では、生徒によるNPO法人設立後の活動について聞いた(全3回)。
――園芸福祉の活動では運営資金が課題となる中、生徒から「NPO法人を設立したい」との話が持ち上がったとのことですが、実際に設立するとなると大変そうです。
「園芸福祉」の活動の流れからNPO法人の設立へと動き出したのですが、「設立しよう」と言った生徒たちは3年生でした。そのため、理事長や理事は2年生に任せて、3年生は「社員」として設立することとし、2006年の11月に自治体から認証されました。
名称は園芸福祉の植物を植えることで美しさが続くといった気持ちとウェルビーイングを掛けて、生徒たちが「植える美ing」と名付けました。とはいえ、三重県ではNPO法人を高校生が主体となって設立するのは初めてですし、ましてや高校生が役員を務めるNPOは全国的にも珍しいので、当然ながらすんなりとはいきませんでした。

まず、県の担当者から「成人ではないから無理です」と言われました。でも、法律にはどこにも成人に限るとは書いてないんです。そうして何度も県とやりとりする中で、私を含む2人の教員が役員に入ることで、どうにか認可されました。
ただし、NPOの所在地として、県立の高校を使うことができないんです。それで、取りあえず法人の所在地は私の自宅にしています。ですので、厳密に言えばNPOは学校下の組織ではないんです。
――高校生がNPOを設立したことによるメリットや効果はありますか。
NPOを立ち上げた大きな理由の一つが、「園芸福祉」の活動内容にあります。どこの農業高校でも高齢者施設で農業ボランティアみたいな形で園芸作業をしていますが、結局、学校で余った花などを使うわけです。でも、私たちには自分たちのお金で何とかしたい、ボランティアという立場から脱したいとの思いがありました。
また、生産経済科は多くの生徒が卒業後に就職することもあり、生徒が社会とつながりを実体験できる機会にもしたかったんです。教員以外の大人と交流することで、学ぶこともたくさんあるだろうと。
とはいえ、会社をつくって継続的に経営していくのは難しいものがあります。その点、NPO法人は民間の非営利団体ですから、園芸福祉の活動と相性が良いし、大人と対等に話もできます。設立後は、高校生のNPOということで話題になり、各方面から声も掛かるようになりました。
――NPO法人の中には、資金繰りに苦労している所も少なくありません。その点はいかがでしょうか。
そうなんです。高校生が運営するだけに、他のNPO以上に資金がなく大変でした。それがある時、高校生レストランを立ち上げた町役場の方から電話があって、「多気町に本社がある万協製薬という会社と共同で、高齢者向けのハンドクリームを作りませんか」と言われたんです。生徒に話すと「やりたい」と言うので、万協製薬に伺って社長さんと対面することになりました。
当初、先方からは高齢者向けのハンドクリームの開発と言われていましたが、生徒たちは松浦信男社長と対面して、「自分たちが使えるものを作りたい。よく売れている市販の商品に勝つようなハンドクリームを作りたいんです」と主張したんです。加えて「モンドセレクションを取りたい」と。
その話を聞いて、万協製薬としても本気で付き合わなければいけないと思ったみたいです。そうして開発したのが「まごころteaハンドジェル」です。商品の中身やデザインなどは全て、企業の人たちと一緒に研究・開発を進めました。

ネーミングにあたっても、いろいろなやりとりがありました。実は高校生レストランが「まごの店」と言い、「まごころ」ではまねをしているようで嫌だという思いも生徒たちにはあったようです。でも、松浦社長から「売れているものに乗っ掛ることも大切な経営的な手法だよ」と言われたんです。経営者のリアルな考え方を聞けたことは、生徒たちにとって貴重な経験だったと思います。その後、この活動を知った近江兄弟社さんとも協力して、リップクリームや日焼け止めクリームなどを商品化してきました。
――なぜ、農業高校の生徒がコスメ商品を作ったのでしょうか。
その点は皆さんから聞かれます。実は大いに関係があって、商品には地元の名産品である伊勢茶の他にミカンや柿、ラベンダー、小豆などが入っているんです。また、食物調理科の生徒たちが手荒れで悩んでいたので、その悩みを解消したいという思いもありました。
端的に言えば「みんなで植物を育ててみんなで幸せになろう」というのが園芸福祉の理念なんです。コスメ商品を作ることによって地元の農家も、商品を製造する万協製薬も、私たち高校も、買っていただく方も、みんな幸せになる。それこそが農業だということです。コロナ禍の前までは、生徒たちが一人住まいの高齢の方を訪問して、一緒にバラを育てたり、マッサージをしてあげたりしていて、そのときに「これ、僕たちがつくった商品ですよ」なんて話をしていました。
生徒の中には、園芸福祉をやりたい生徒もいれば、バイオマスを調査したい生徒、大豆を商品化したい生徒もいます。地域の伊勢茶の会社が協力的で、研修させてくださるなど、園芸福祉を起点に活動が広がり、世代間交流も生まれています。
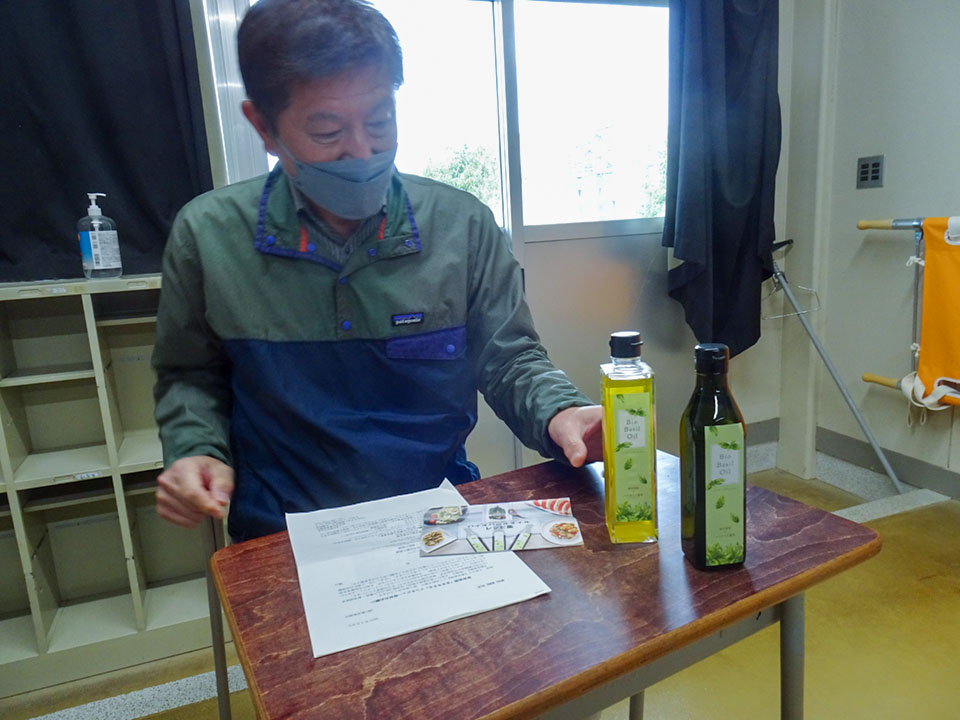
万協製薬の松浦社長は当初、生徒たちの園芸福祉の活動をただほほ笑ましく見ていただけだったと言います。でも、保育所に花を植えたりお年寄りと野菜を育てたりするとなれば、プランターの購入費だけでも、それなりの金額になります。それを自分たちで何とかしたいと思い、「売上の3%を園芸福祉に回してほしい」との話をしたんです。
話を聞いて、松浦社長は「ほほ笑ましく見ていた自分が恥ずかしかった」と話しておられました。そして、高校生が保育所の子どもたちや高齢者施設の方のために活動しているのに、自分たち企業が支援しないでどうするのかと思ってくださりました。一企業の経営者にそう感じさせるほど、高校生の活動には力があったのだと思います。
【プロフィール】
新谷和昭(しんたに・かずあき) 1965年生まれ。三重県出身。三重県立相可高等学校において生産経済科園芸を担当。高校生によるNPO法人「植える美ing」の理事を務める。園芸福祉士、園芸福祉コーディネーターの資格を所有。