過去3年にわたり、「学校風土調査」の結果と脳科学のエビデンスに基づく授業改善を進めてきた東京都国立市立国立第二中学校の黒田宏一校長。取り組みは全てが順調だったわけではなく、全教員の理解を得る過程では困難もあったと語る。インタビューの第2回では、調査結果をどのように分析し、授業改善が必要だと判断したかを聞いた。(全3回)

――「エビデンスに基づいて不登校・いじめ対策をすべきだ」との考えで、「子どもの発達科学研究所」と連携して学校風土調査を実施したとのことですが、その結果から見えてきたことを教えてください。
着任2年目に得られたデータの中で特に注目したのは「安全」「教えと学び」「関係性」「環境」の4つの指標から見た学校風土の数値を学年別に表したグラフです。この調査では生徒のアンケートから得られた結果を偏差値で示します。全国の調査実施校の平均を偏差値50とし、「+1」を偏差値60、「-1」を偏差値40とします。
一般的にこの手の調査では、1年生が肯定的な回答をすることが多く、2年、3年と学年が上がるにつれて肯定の値が下がります。この値を学校の全体平均だけで見てしまうと、2~3年生で下がっている状況が把握しにくくなります。そこで、学年ごとで示されたデータに注目したのです。
すると、やはりどの偏差値も学年が上がるごとに下がっていて、特に「教えと学び」の下がり幅が極端に大きいことが分かりました。1年生では57だったのに、2年生では53、3年生では50にまで下がっていました。他の指標と比較しても、その下がり具合は顕著でした。
――「教えと学び」の質問はどのようなものなのですか。
この調査では、一つの指標ごとに5~8の質問が設定されています。「教えと学び」では、「授業に集中できる」「授業は楽しい」といった授業に関する質問のほか、「けんかやいじめなどの問題を解決する方法を学んでいる」など、心の教育に関する質問があります。
全校平均で見ても、「授業は楽しい」の値は49と、調査校の平均を下回っていました。この他に「私は学校が好きだ」の値も47と低かったのですが、一方で「生徒と教員の関係性」の質問である「いじめなどをしっかり注意してくれる」「困っているときに助けてくれる」の値は55以上と高く、教員に対して否定的な感情を抱いているわけではないと感じました。
その他のデータも見た上で、全校的な授業改善で不登校といじめの解決につなげていこうと決意しました。そして、授業改善の在り方についても、エビデンスに基づいて手だてを精選しようと考えました。

――教員が個々に取り組むのと違って、全教員が共通の手だてで授業改善を図るというのは、授業に自信のある教員からは反発もあったのではないでしょうか。
その通りでして、「必要性が分からない」「自分なりに実践を重ねてきたものがある」という考えから、型にはめられるのをよしとしない人もいました。授業改善は校内研究部の教員に相談しながら進めたのですが、その中心的な役割を担っていた教員が矢面に立たされるような場面もありました。
でも、私は一部の教員だけが取り組む「代表選手型の改善」は想定していませんでした。「学校ルールの見直し」や「いじめ撲滅」など、一部の教員や生徒会役員が主導するような取り組みでは、他の教員や生徒は意思表示をするのみで、主体的に関わることはなく、抜本的な改革にはつながりにくくなるからです。
学校で教員が生徒に指導する場面には、授業だけでなく生活指導や部活動、学級経営、道徳などがあります。でも、生徒が学校で過ごす時間のほとんどは授業です。そして、全ての教員が授業をします。全教員が共通認識を持って授業改善をすることが、学校風土を高めると考えました。
そうして立てた仮説は、「授業環境を整えることで生徒が授業を楽しいと感じ、学習意欲が向上して主体的に学べるようになれば、達成感を得て自己肯定感が高まり、不登校やいじめの克服につながるのではないか」というものでした。個別の教育相談や特別活動、道徳教育の充実などはいったん脇に置いておくことにして、全ての教員と生徒が関わる授業の改善を図ることで、学校全体が変わると考えたのです。
教員人生という観点から考えた際にも、身に付けた授業力はどのような学校に異動しても武器になります。「楽しい授業」という目的を生徒と教員、双方の未来を見据えて設定しました。
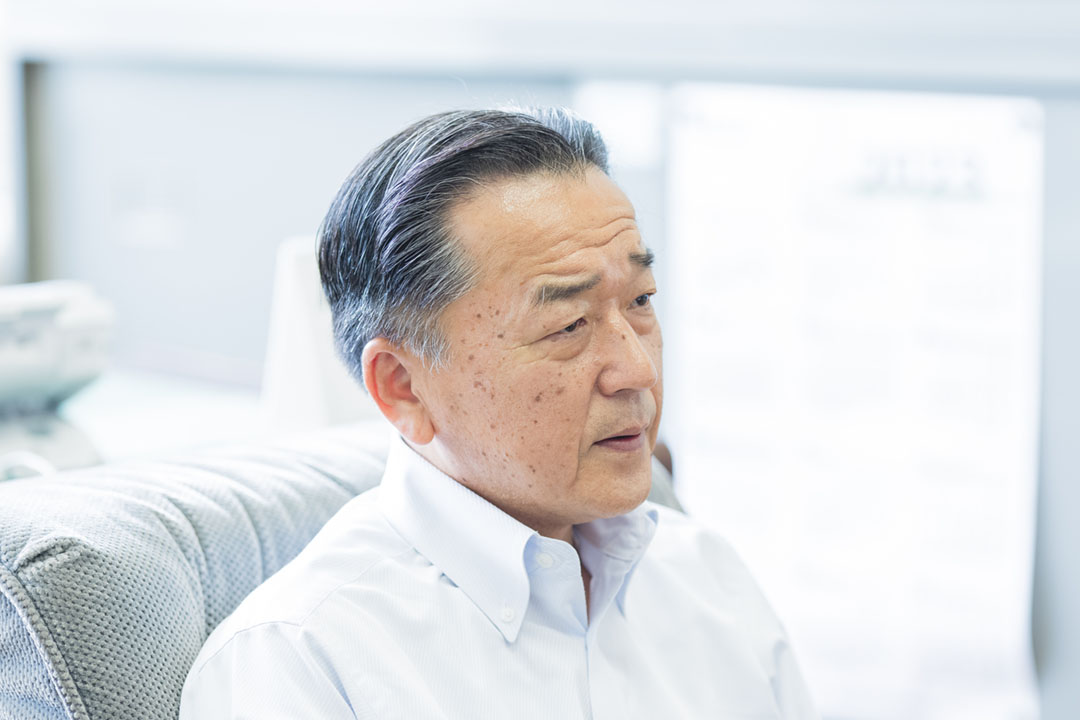
――授業改善も「子どもの発達科学研究所」と連携しながら進めたのですか。
研究所にこちらの考えを伝えたところ、「不登校・いじめ対策を授業改善でというのは斬新だ」と言われ、「連携して取り組みを進めましょう」との提案を受けました。そうして始まったのが、脳科学を取り入れ、そのエビデンスに基づいた授業改善です。
研究所の先生方を学校に招いて、「疫学統計学」「脳機能モデル」「行動科学」の3つの視点から脳科学に関する講義をしてもらい、実施すべき授業の在り方について意識改革を進めていきました。また、実際の授業を見学してもらい、助言を受けながら新たな授業改善を推進していきました。
【プロフィール】
黒田宏一(くろだ・こういち) 1985年、東京都の中学校数学科教員として教員生活をスタート。町田市、稲城市、多摩市の教諭や主幹教諭を経て、2008年に副校長として国立市に着任。12年4月に国立市立小学校に校長として着任。14年4月から中学校長として勤務し、現在に至る。