ChatGPTをはじめとする生成AIの利活用は、北欧の教育現場でも大きな議論になっている。授業や学習、または公務での活用が期待されている一方で、試験でのカンニングが懸念されている。スウェーデンのウプサラ大学では、今年2月にChatGPTを使ったカンニングが発覚し、その不正行為を行った学生は訓告処分を受けた。基礎学校(日本の小・中学校に相当)や高校でも、学校の成績や、それに影響を与えるナショナル・テストでの不正行為を防ごうと、さまざまな対策が講じられている。
生成AIに関するガイドラインでは、リスクを先に書くか、メリットを先に書くかで、各機関のスタンスが透けて見える。スウェーデンの基礎学校から高校までを管轄する学校教育庁は、ウェブサイトに「生成AIについて知るべき重要なこと」という見出しを先に出し、教師向けに3点の注意点を挙げている。生成AIを使ったカンニングのリスクが高まること、生成AIが書いた文章は間違っていたり適切でなかったりすること、そして生成AIに対して個人情報などの重要な情報を打ち込まないことである。
テストでのカンニングについては、ChatGPTが広まる以前から注意喚起がなされていた。基礎学校最終学年や高校では、学校での成績が進学に直接利用されるので、成績に影響するカンニングには厳重な対応が取られるためだ。
スウェーデンでは、成績づけのために、筆記テストに加えてレポート課題が課されることもある。近年の生成AIは学校で教えられる内容のほとんどについて質の高いレポートを書くことができる。そして、生徒が書いたか生成AIが書いたかを判別することは困難である。そのため学校教育庁は、実際に生徒が書いたという確証を得られない場合には、レポートを成績の根拠に含めないようアドバイスしている。また、宿題でのレポート課題はChatGPTが書いたかもしれないため、提出後に内容について口頭で議論するなどして、本人の知識であることを確認する必要がある。
生成AIの利用を制限するのではなく、生成AIに対応して評価の方法を考え直すことが求められている。
学校教育庁は、こうした注意点の他に、授業をはじめとした教職員のさまざまな仕事での活用法に触れるとともに、技術の発展に応じて通知内容も見直していくと表明している。
各学校で教師が成績をつける際には、ナショナル・テストの結果も参考にされる。高校3年生の国語(スウェーデン語)テストでは、事前に配布される文章を自宅などで読んでおき、試験当日に4時間にわたる論述問題に取り組む。そのため、ChatGPTを使って事前配布資料を読解したり、論述の準備をしたりすることは難しくない。
こうした新しいカンニングへの対策を明確にするため、今年はテスト自体を休止すべきという意見も出された。しかしながら、その影響を知るためにはテストを実施する必要がある。また、全国規模の評価情報は多くの教師が参考にしているため、実施しないわけにはいかない。
学校教育庁は、カンニングを阻止するために、論述筆記の後に行われる口述試験をより重視することを検討しているという。ただし、ChatGPTのためにテストの構成などを全体的に見直す予定はない。
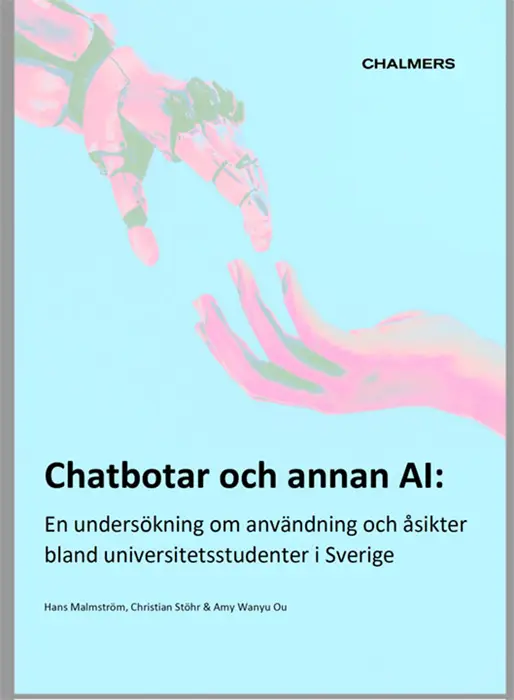
チャルマーシュ工科大学が今年春に実施したアンケート調査では、半数以上の大学生が生成AIの利用に前向きであることが明らかになった。この調査では、スウェーデンの大学に通う学生6000人弱の対象者のうち、ほぼ95%がChatGPTを知っていると回答し、3分の1以上が普段から使っていると回答した。約半数の学生が生成AIは自分の学習に効果的だと回答したが、生成AIの利用が成績を向上させるかという問いには17%しか同意しなかった。
調査では自由記述欄もあったが、そこでは、生成AIが対話型の学習源として、メンターや教師のような役割を果たしたり、分からない箇所を説明したり、課題の手助けをしてもらう形で活用しているという回答も多かった。また、障害のある人にとって効果的な補助ツールになるだろうという意見もあった。
興味深いことに、学校教育庁などの「教える側」の懸念は大学生などの「教わる側」にも共有されていて、62%の学生が生成AIをレポート課題や試験に利用することは不正だと考えていた。それでも、60%の学生は教育での生成AIの利用を制限すべきではないと考えていた。授業と試験では使い分けるべきだと考えているのかもしれない。
スウェーデンの教育機関はこれまでもICT活用には積極的に取り組んできたが、発展途上の新技術に、教員や学生はどのように向き合っていくのだろうか。