国内の約2人に1人が所有するなど、欠かせない移動手段となっている自転車。一方で、全体の約2割を占める乗用中の交通事故は大きな問題となっている。そんな中、道路交通法の改正で、4月から自転車乗車時のヘルメット着用の「努力義務」化が始まる。普及を進める上で、課題になっているのが高校生。使用頻度が高く、自転車事故による負傷者も最も多いが、着用率は中学生以下と比べて低いのが現状だ。下校中の事故で息子を亡くした遺族の義務化への思い、高校生へのヘルメット着用を推進する取り組みを行う学校や企業を取材した。
「やっとそういう流れになったか――」。努力義務化が始まることについて、こう話すのは松山市に住む自営業・渡邉明弘さん。2014年12月、当時高校1年生だった長男・大地さんを交通事故で亡くした。自転車で下校中、信号のない横断歩道を渡っていたところを4トントラックにはねられた。

仕事中だった渡邊さんは妻からの電話で大地さんが事故に遭ったことを知り、病院に駆け付けた。意識不明で搬送された大地さんは集中治療室に入り、すでに予断の許さない状態。「(大地さんに)対面する前に、主治医からどんな状況か頭のレントゲンを見せられた。右側に円形にひびが入っていた。脳内から出血していて、今は触ることができないと聞いて、なんとなくこれは駄目かなと、ずっと泣いていた」と振り返る。
意識が戻ることなくこの世を去った大地さん。高校では写真部に所属。猫や鳥などの動物、海や夕日といった自然の写真を撮るのが好きだったという。普段、大地さんが学校に行く前は、渡邉さんがハイタッチをして送り出すが、この日は遅くまで寝ていたため、気付いた時には家を出た後だった。「次会う時にこんな姿だなんて、想像もしていなかった」。


事故当時、大地さんはヘルメットを着用していなかった。渡邉さん自身、帽子が嫌いで学生時代に制帽をかぶることも苦手だったといい、「自分自身も正直、ヘルメットを着用しないことに対して疑問を持っていなかった」と話す。
警察庁によると、21年の自転車乗車中の交通事故による死傷者は6万8114人。このうちヘルメット非着用は全体の88.5%に当たる6万306人だった。死傷者数は減少傾向にあるが、年齢区別にみると15~19歳は1万2155人。他の年齢区分に比べて、圧倒的に多い=図表①。また、死亡者数に限ると、361人のうちヘルメット非着用は336人。非着用率は93.1%と死傷者数に比べ、高くなった。
さらに、au損害保険が中学生と高校生の保護者各250人に調査したところ、自転車利用時にヘルメットを着用している子供は中学生39.2%、高校生はわずか12.0%だった=図表②。さらに、保護者の約8割が道交法改正で年齢問わずヘルメット着用が努力義務になることを知らないと答えるなど、自転車の安全に対する意識は自動車と比べて、低いと言わざるを得ない現状だ。
大地さんの事故などを受け、愛媛県では15年7月から全ての県立学校で自転車通学時のヘルメット着用が義務化された。だが、渡邉さんは当初、義務化に反対だったと話す。「車を運転している大人が気を付けていないのに、どうして生徒に無理やりヘルメットをかぶらせるのか。まるで生徒が悪いみたいで、順番が違うじゃないかって」。
その考えを変えたのが、義務化された翌年に松山市であったひき逃げ事故。自転車を運転していた女子高生が酒気帯び運転の自動車にひかれ、一時意識不明に。しかし、意識が戻り、一命を取り留めた。「ヘルメットをかぶっていたから、頭に損傷がなくて助かったとニュースで聞いた時に、義務化されていなかったら、この子は亡くなっていただろうなと思った。その時に初めて義務化してよかったと思った」と話す。
渡邊さんは大地さんが亡くなった4年後の18年から、「命の授業」と題して県内の高校で講演活動を始めた。自身の体験を交え、ヘルメット着用の重要性を訴える。その際に大事にしているのは、参加者の配置。必ず教職員が前。その後ろに生徒と決めている。
「大人たちが何もせずにいきなり子供にああしろ、こうしろと言ったところで、自分が子供だったら聞かないなと思った。大人たちが意識を変えようとしているという姿を見せられた時に、初めて子供が考え始める気がした」と話す。こういった取り組みのかいもあってか、愛媛県警によると、同県の高校生のヘルメット着用は99.1%にも上っている。昨年12月には香川県の高校でも講演するなど、その輪は県外にも広がり始めている。
08年度の(一社)自転車協会の調査で、自転車保有率全国1位となった埼玉県。「じてんしゃ王国 埼玉」を掲げ、サイクリングイベントの開催や、県民から県内の名所を巡るサイクリングルートの募集を行うなど、自転車を活用した町おこしを行っている。
一方で、問題になっているのが、やはり自転車事故だ。埼玉県警によると、同県内の21年の自転車事故による人身事故件数は4880件。死亡者数は交通事故による死亡者全体の約3割に当たる34人で、全国最多だった。また、死亡した全員が運転時にヘルメットを着用していなかったという。
これを受け、埼玉県警が昨年9月に始めたのが、「自転車ヘルメット着用モデル校」制度。自転車通学の割合などを基準に指定し、ヘルメット着用を通した交通安全意識の向上を図っている。埼玉県警交通総務課の中村聡課長は制度の狙いについて、「高校生が被害に遭う事故のほとんどが自転車によるもの。高校生からヘルメット着用の輪を広げることで、全体の自転車事故が減るのではないかと考えた」と説明。2月現在で、▽県立熊谷高校▽県立三郷高校▽県立所沢商業高校▽県立桶川高校▽埼玉栄中学・高校(さいたま市)――の計5校に委嘱している。

このうち、最も活発に活動していると埼玉県警が太鼓判を押すのが、県立熊谷高校(加藤哲也校長、生徒954人)。生徒の9割が自転車通学という同校では、JAF(日本自動車連盟)を講師に招いた出前教室を行ったほか、生徒会がヘルメット着用のプロモーション動画を独自に制作し、YouTubeで公開した。
同校生徒会長の井上晴太さん(2年)は、動画制作の理由について、「学校に紙で掲示もしているが、それを見る人はあまりいない。YouTubeだったら、SNSやQRコードなどを使ってみんなに広げられると思った」と説明する。動画は約1分。自転車事故の7割が頭部を損傷していることや、頭部は損傷した際の死亡率が他の部位に比べて約15倍高いなどのデータを用いて、ヘルメット着用の有効性を井上さんが解説する内容となっている。「あまり堅過ぎると見てくれないと思ったので、最初は少しコミカルに、最後にデータを使って有効性を示そうと思った」と井上さんは語る。
2月15日には、埼玉県警と共同でPR動画を撮影。井上さんを含めた生徒会の役員8人が日常シーンやメッセージなどを通して、ヘルメット着用の重要性をアピールした。同じくモデル校の埼玉栄中学・高校のシーンと合わせて、30秒程度の動画になる予定。3月中旬の完成を目指しており、埼玉県内の商業施設にある大型ビジョンや埼玉県警の公式YouTubeチャンネルで公開される。
先に上げたau損害保険の調査で、着用していない理由として高校生で最も多かったのが「学校の校則で定められていないから」で47.3%。一方で「かっこ悪い」や「友人など身近な人がかぶっていないから」などの理由も2割以上あり、見た目も敬遠する一因になっているようだ=図表③。
そんな中、愛知県一宮市でプラスチック製品の製造・販売を行うクミカ工業が21年に開発したのが、見た目にこだわったおしゃれなヘルメット「ドルフィン」だ。同県は21年10月施行の条例改正で、自転車保険の加入義務化とともに、ヘルメット着用も努力義務となった。
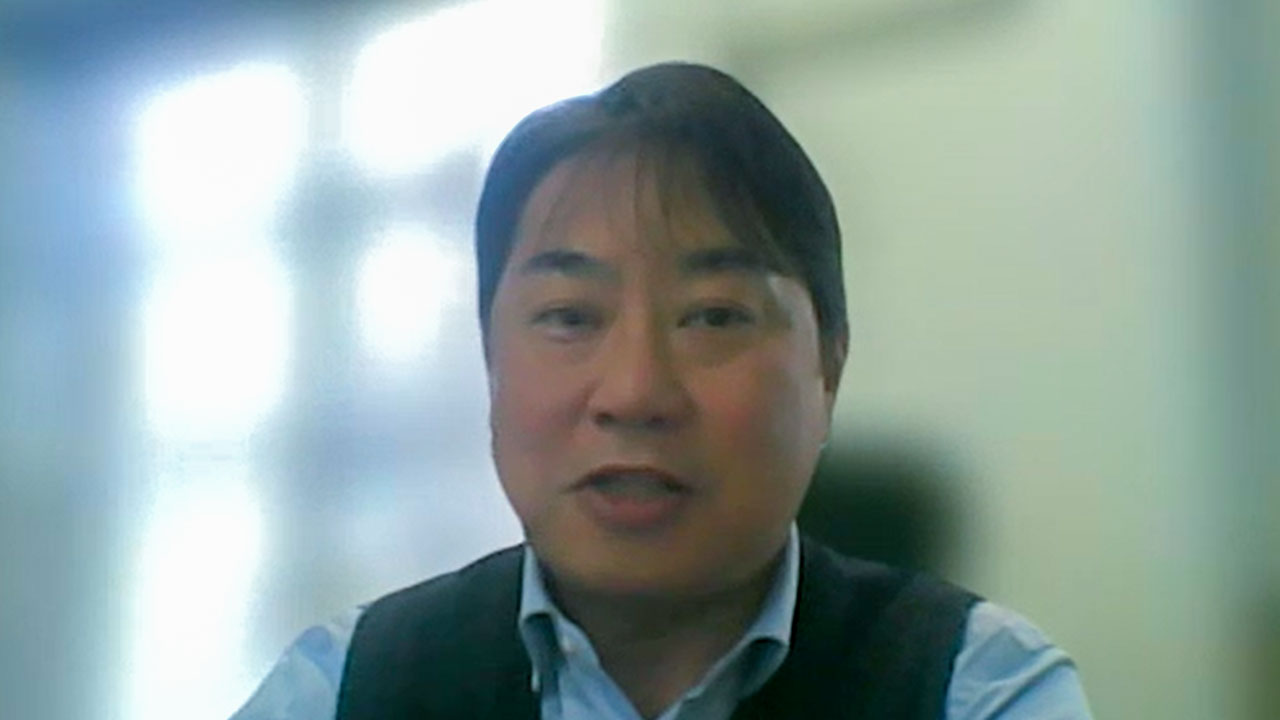
開発にあたって特に力を入れたのがデザイン性。西川正一郎社長は「普段もかぶっていないと困る。学校に来る時だけにかぶるようなヘルメットはもういいと、警察の方にも言われた」と話す。休日の外出にも使えるようにシンプルでベーシックな見た目。ブラックやマスタードなど用意した5色には、いずれもマット加工を施し、おしゃれ感を演出した。この春、さらに色を増やす予定だという。
できる限り「煩わしさ」をなくすための工夫も凝らした。後頭部には髪の毛を通す「ヘアポケット」を搭載。結んだ髪やセットした髪が崩れることを防いでくれる。蒸れにくいようにするために、ヘルメットの前後に穴を開け、走行中に頭部に風が抜けるようにした。一方で、上部には穴を開けず、さらに前後の穴の角度も調整することで、雨の日でも頭がぬれにくい。さらに、フィット感を調整するアジャスターもワンタッチで操作できるようにした。
外殻は硬いものにぶつけても壊れないように、ハードシェルと呼ばれる硬質の樹脂を使用。さらに内側に発泡スチロール製のパッドを合わせた二重構造にした。安全性を認証するSGマークも表示されており、ヘルメットとしての品質も折り紙付きだ。

これまで、県内での販売や地元警察による高校での配布に加え、制服メーカーの協力で群馬県でも販売されていたが、努力義務化の閣議決定以降、学校関係者や大型量販店など全国からの問い合わせが殺到。同社によると1月の売り上げは例年の10倍にもなったという。
西川社長は自転車におけるヘルメットを「シートベルトと一緒」と話す。今となっては常識となっている自動車運転時のシートベルト着用だが、一般道でも義務化されたのは1992年。まだ30年しかたっていない。「今はシートベルトをつけないと不安。それと同じで、自転車に乗るときもヘルメットをかぶるのが習慣になってしまえば、ないことが不安に感じるようになると思う」と強調。そのためには「努力」義務にとどまらず、義務化が必要不可欠だと訴える。
2月6日、大地さんの通っていた県立伊予農業高校の生徒が反射タスキをデザインしたことに対する感謝状の贈呈式が、伊予市内で行われた。その場でも渡邊さんは1時間の講演を行った。
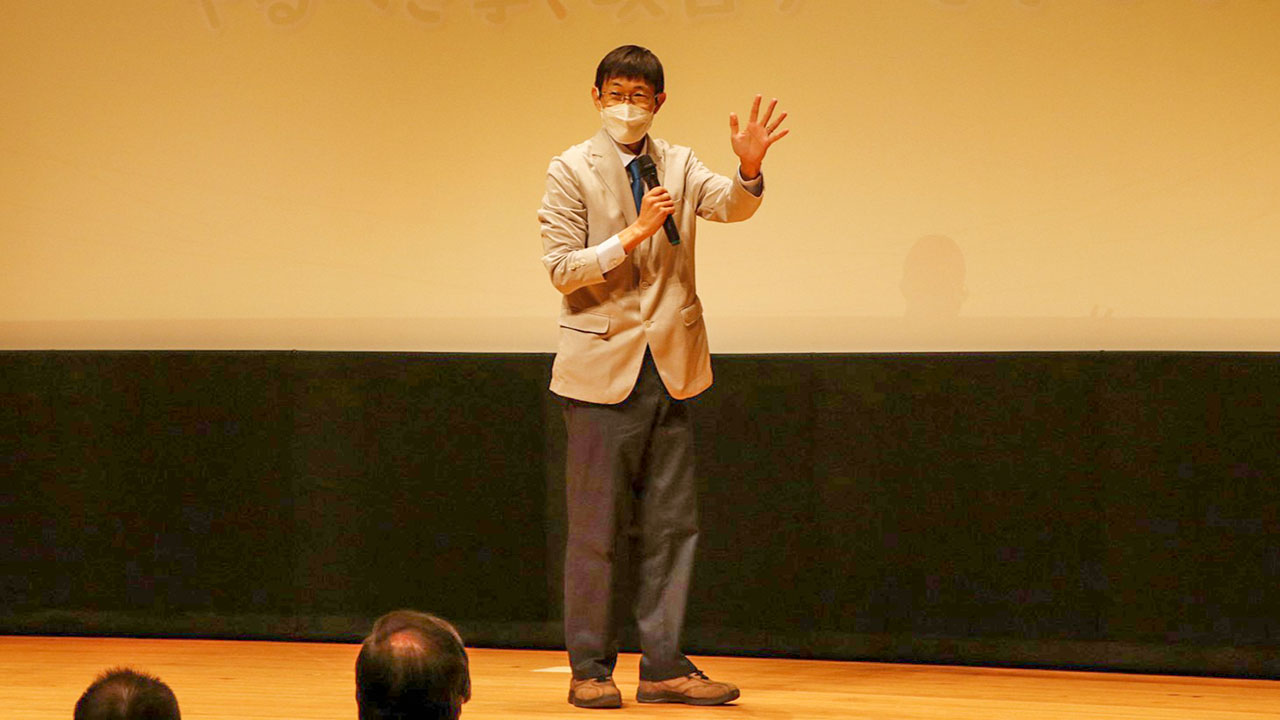
大地さんがこれまで撮影した写真のスライドショーを見せたほか、当時の事故状況や愛媛県がヘルメット着用義務化になった経緯、着用義務化に当初は反対していたことなどが渡邉さんの口から語られた。その上で、渡邉さんは「今年4月から自転車に乗る人全員、ヘルメット着用が努力義務になる。大人が率先してヘルメットを着用し、子供たちに正しい見本を見せよう」と呼び掛けた。
生徒からは「自転車を降りて信号のない横断歩道を渡るとき、手を上げられない場合はどうすればいいか」という質問があったという。渡邊さんは「信号の横断歩道に歩行者が立ち止まった場合、車は停止線で止まらなければいけない。ドライバーに向けてアイコンタクトを送る」と応えた。一方で、「現状止まらない車も多い」と大人にくぎを刺した上で、生徒には「運転免許を取ったら、周りのドライバーの見本になってもらいたい」と呼び掛けた。
渡邊さんはインタビューの最後、「高校生はかぶれと言われるのは嫌だと思う」と前置きした上で、生徒らにこう訴えた。「自分の髪が崩れるくらいの価値と自分の命の価値をはかりに掛けてみて、どっちが重いかということ。多分、みんなは自分の運転を、暴走したりしないから大丈夫だと思っている。でも、大地のように、大人が見落とすことで理不尽な事故は起こりうる。そうなった時に助かる可能性が少しでも上がるように、ヘルメットをかぶってほしい」。