「脳や神経由来の多様性」を指すニューロダイバーシティという概念は、学校教育の在り方を変える可能性を持つ一方、臨床心理士の村中直人さんは、発達障害の言い換えのように使われつつある現状に警鐘を鳴らす。ニューロダイバーシティという視点を通して、「通常学級の子どもたちも自分に合った学習方法を選択できるかどうか」が重要だと語る村中氏に、この概念で押さえるべきポイントについて聞いた。(全3回)
――発達障害者支援法ができて以降、社会的にも発達障害という言葉が広く認知されました。同じように、ニューロダイバーシティという言葉が登場したことで、教育現場や社会が劇的に変わっていくのかもしれません。
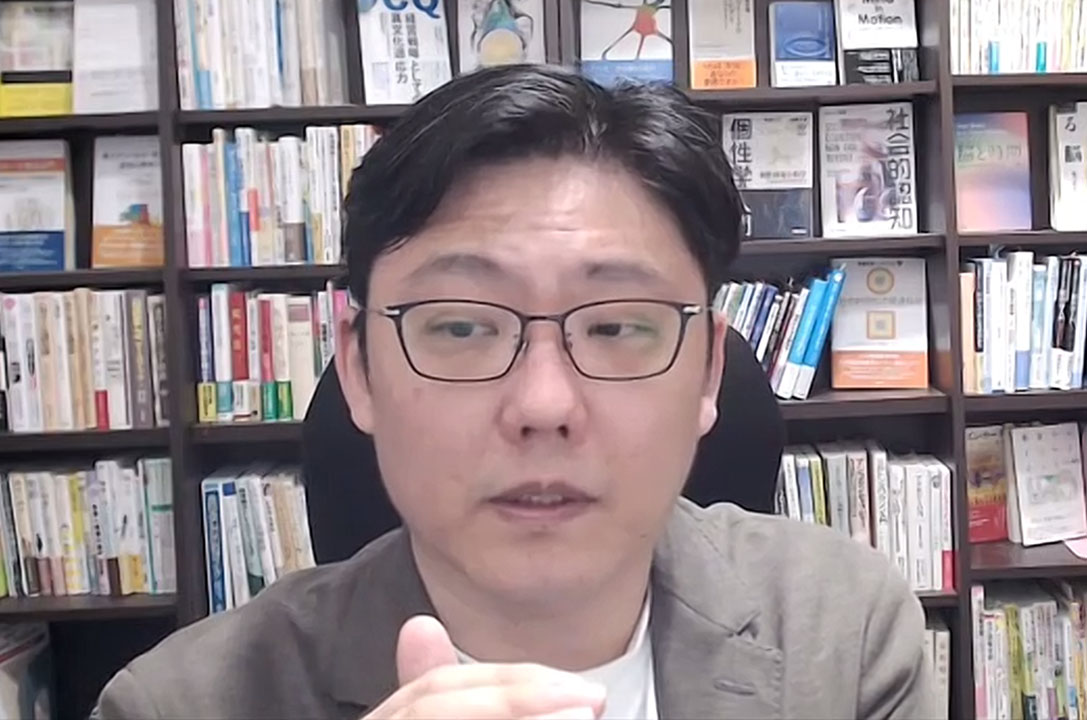
私もその期待をしています。ただ、現状の日本国内での使われ方には、とても心配をしています。言葉の本来的な意味合いと比べると、とても限定的な意味での受け止め方をされている状況があるからです。
ニューロダイバーシティという言葉は、1990年代後半に自閉スペクトラムの大人たちのコミュニティーの中で生まれ、社会運動として広がった言葉です。でも、決して発達障害の言い換えではないんです。当事者たちは「自分たちをニューロダイバーシティと呼んでください」なんて言っていません。本当にいろいろなことを考え抜かれて作られた言葉で、対義語として「ニューロユニバーサリティ」という言葉が当初から提示されています。
ニューロダイバーシティは、「人間の脳や神経の働き方は一人一人違う」と考える、基本的な人間理解のパラダイムです。一方、「ニューロユニバーサリティ」は、人間は基本的なところは一緒だという考え方、人間同士は似た存在なんだというまなざしで考えるスタンスです。つまり、人間の脳や神経の働き方は「似ている」のかどうかという話です。
ビジネス領域では、経産省がニューロダイバーシティに関する調査を行ったりしています。世界的にどう使われているかと言えば、「自閉スペクトラムの才能のある人をもっと積極的に採用しましょう」という文脈で使われているんです。
――「ギフテッド」という言葉も、近年よく聞くようになりました。
そうですね。つまり「マイノリティーの人たちをマジョリティーの中に頑張ってインクルージョンしましょう」という文脈で、ニューロダイバーシティという言葉が使われてしまっている状況があります。もちろん、インクルージョンすることは当たり前の話だし、やるべきことではありますが、それでもってニューロダイバーシティと言われてしまうと非常に困ります。そもそも人間という存在をどう見るのかという本質的なまなざしの問題であって、「発達障害の子どもたちを大事にするためのキーワード」みたいに理解されてしまっては、概念が狭過ぎます。
もちろん、特別支援教育の枠の中にいる子たちにとって、ニューロダイバーシティは大事な概念です。でも、そこだけに閉じ込められると、結局は「私には関係ないよね」「特別な人たちのための特別な考え方でしょ」という人たちが多数になり、言葉としての効力を失うんです。
――特別支援教育に限らず、誰にとっても関係のある話ということですね。
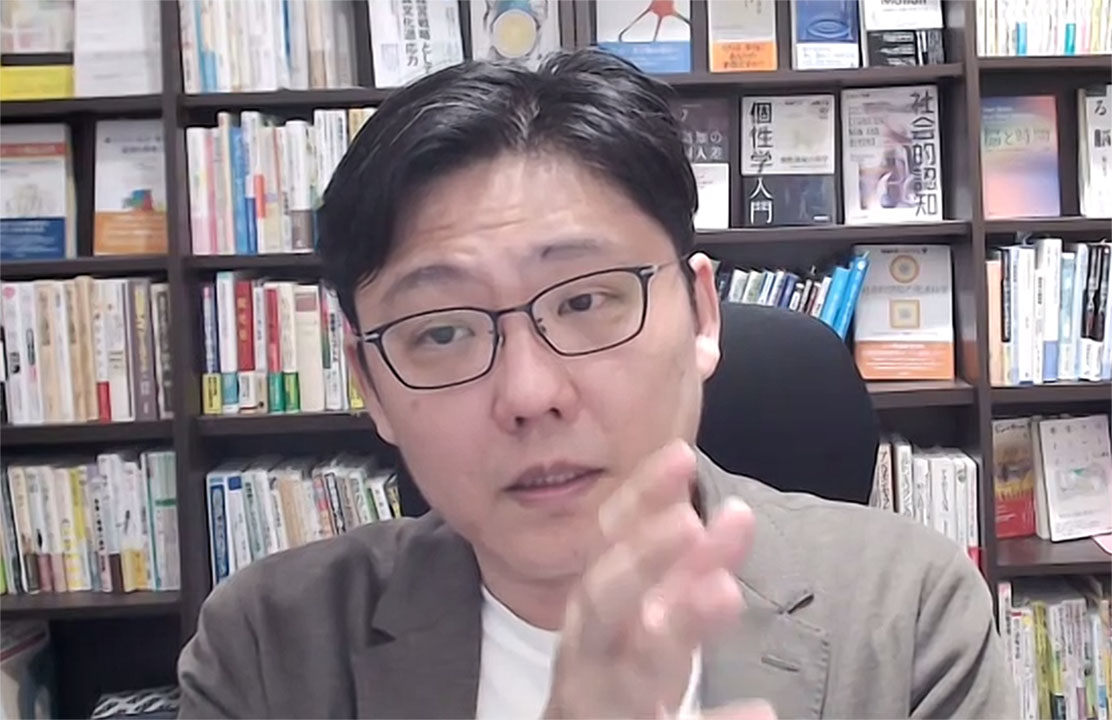
例えば、社会的に無視されている脳や神経の働き方の多様性の問題に、「クロノタイプ」があります。クロノタイプとは約24時間周期で働く体内リズムのことですが、個人差があって、遺伝の影響が大きいことが知られています。分かりやすくいえば「朝型」「夜型」があり、朝早く起きた方が調子の良い人、夕方の方が調子の良い人がいるのは、生活習慣の問題だけではなく、神経の働き方のレベルで個人差が存在しているんです。
私に言わせると、これも立派なニューロダイバーシティの一つです。何時に起きて何時に寝るのがその人の健康やウェルビーイングに適切なのかには、個人差があるという話です。しかし、現代社会は人間のクロノタイプという個人差は存在していない、あるいは小さな差でしかないという前提でつくられています。そうでなければ、朝早くに全員が一律に学校に行かなければならないルールが存在するはずありません。
そう考えても、私たちは無意識の水準で「ニューロユニバーサリティ」な価値観を骨の髄まで刷り込まれています。ニューロダイバーシティの人間理解で教育を語るならば、そもそもクロノタイプについての議論が起きるはずですが、聞いたことがありません。
海外の研究によると、ADHDとカテゴライズされている子どもたちの中に相当数、夜型クロノタイプがいるそうです。これは「卵が先か鶏が先か」という話になっていて、その子はADHDだから夜型クロノタイプなのか、夜型クロノタイプなのに朝型生活を強制されているからADHDと見られているのか、見分けがつかない状態になっている可能性があるのです。
例えば、起立性調節障害に関しても、朝起きると血圧が下がって貧血状態になって動けない子どもだけではなくて、極端な夜型クロノタイプの子どもも含まれている可能性は十分にあるのではないかと私は思うのです。不登校への対応として心理的安全性を高めることが重視されていますが、どれだけ心理的安全性を高めたところで、登校時間が柔軟にならない限り、極端な夜型クロノタイプの子は学校に来ることが苦痛でしょう。
もちろん、地域の安全性や安心して帰れる場所というのは大事ですが、大前提としてニューロダイバーシティが存在していることを無視して表面的な対応だけ考えても、根本的な解決にはならないでしょう。
実を言うと、私自身は結構な夜型人間で、朝起きられないことに対してコンプレックスを感じてきたんです。最近は「朝活」が流行したりして、朝早く起きて一日を有益に過ごしている人が「できる人」みたいな感じに捉えられていますよね。だから何度も朝早く起きる習慣を身に付けようとトライして、失敗しては落ち込んでみたいなことを繰り返してきました。でも、結局は無理なので「私が起きる時間はこれ」と開き直ってからはだいぶ楽になりました。そんなふうに考えることは誰にとっても大事なことなんです。

――そうですね、新聞記者は夜遅くまで原稿を書く仕事というイメージがありますが、私自身は午前中に原稿を書いた方がサクサク進むことに気付いて、それからは仕事のスタイルを変えた経験があります。
それは多分、朝型クロノタイプなのに夜型クロノタイプがマジョリティーの業界の中にいたから、なんとなくその文化に染まっていたんだと思います。そういうことが日本中いろいろなところで起きていて、多くの人が全然自分に合っていない生活を仕方なしにやっているんです。でも、自分のクロノタイプに合った生活をした方が、絶対良い人生を送れると思います。
内閣府や文科省などの教育改革の方向性には基本的に賛成の立場ですが、根本的な人間観が「ニューロダイバーシティ」ではなく「ニューロユニバーサリティ」なままだと感じています。圧倒的多数の普通の子どもたちの中に一部少数の特別なニーズの子たちが交ざっていて、そうした子たちがどんどん増えているという捉え方です。そうした捉え方が何に影響するかと言えば、通常学級にいる多くの子たちが、自分の学び方を選択できなくなることにつながる可能性があるのです。
現状の学校教育は、その子に合わない学び方だったとしても、問題があるレベルまで落ちない限りは「問題のない子」と捉えられてしまいます。でも、私自身はこれまで学習支援をしてきた中で、合う方法・合わない方法によって起こる格差をこの上なく実感しているんです。
【プロフィール】
村中直人(むらなか・なおと)臨床心理士・公認心理師。(一社)子ども・青少年育成支援協会代表理事、Neurodiversity at Work㈱代表取締役。1977年生まれ。大阪市立大学卒業後、京都文教大学大学院で臨床心理学を学ぶ。2008年に学習支援事業『あすはな先生』立ち上げ。現在は「発達障害サポーター'sスクール」での支援者育成にも力を入れている。著書に『ニューロダイバーシティの教科書――多様性尊重社会へのキーワード』(金子書房)、『〈叱る依存〉がとまらない』(紀伊國屋書店)。