Z世代には検索ツールとしても使われているSNS。教員の発信ツールとしても中心的役割を担いつつあるが、これを活用しながら最先端の情報を発信し続けているのが「ギガ先生」こと大阪府泉佐野市立第三小学校の柴田大翔教諭だ。教育活動においてもICTを徹底活用し、担当する3年生の教室に足を踏み入れると、そこにはスッキリとした空間が広がっている。そうした活用術を集めた書籍『今日から残業がなくなる!ギガ先生の定時で帰る50の方法』(学陽書房)が生まれたヒントが、ここにありそうだ。(全3回)
――まずは自己紹介をお願いします。
大阪生まれ大阪育ちです。小学4年生のときの担任の先生に影響を受けて小学校教員を目指しました。もともと子どもと関わることが好きで、幼い頃から教員になりたいと思っていました。大学の教育学部を卒業し、最初は大阪市の教員となりました。その後、結婚を機に和歌山に転居することになったので、大阪府の採用試験を受け直して採用されました。現在、11年目になります。

――インスタグラムやボイシ―のハンドルネーム「ギガ先生」の由来を教えてください。
最初にSNSで発信しようと思ったのがインスタなんですが、そのハンドルネームにインパクトを持たせたいと思って付けた名前です。2021年の2月に始めた頃は、まだインスタを使って発信している先生は多くありませんでした。ちょうど「GIGAスクール構想」が始まった時期だったのと、私自身がICTに関してある程度の知識があったので、「ギガ先生」としました。
――最初の発信がインスタなんですね。現在のフォロワーは1万9000人。始めたきっかけは何だったのでしょうか。
自分の学びをアウトプットするためです。ここ数年で自分の働き方が見えてきて、時間にも余裕が出てきたので、何か発信したいと思って始めたことでした。
――コンテンツはどのように作って投稿するのでしょうか。
Canvaというオンラインのグラフィックツールを使っています。「学級経営」「授業」「行事」などのテーマで、役立つヒントを10枚程度のスライドにまとめて投稿します。現在約300本が上がっています。21年当時は画像を入れるなど作り込む時間がまだあったので、初期の投稿は画像やイラストも多用しています。
この投稿を見た出版社からお声掛けいただいて生まれた本が『ギガ先生の定時で帰る50の方法』です。約300のアウトプットの中から先生方に役立ちそうなものを厳選し、自分の日々の実践も書き加える形で書籍化しました。
――第1章「月120時間の残業が激減! 今日からできる最速仕事術!」には、12のアイデアが紹介されています。第2章以降は学級経営や授業、校務のアイデアが続きます。構成で意識したことはありますか。
「今日からできる」というところです。読み始めたときに「自分には無理」という印象を与えてしまったら読む気をなくしてしまうと思いました。「これだったらできるかな」と最初に思ってもらえたらいいなと考えながら、構成しました。
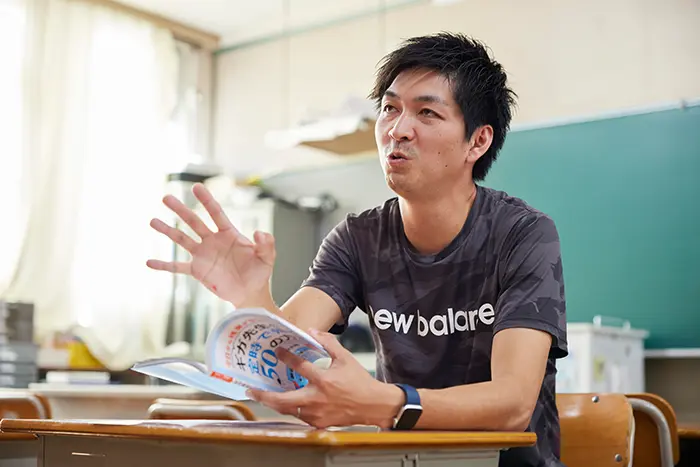
――ICTを活用したお勧めの時短術を教えてください。
まずは「どの端末からでも閲覧できるセッティング」です。私のクラスでは連絡帳を黒板に書くのをやめ、オンライン上のクラスの掲示板に入力するようにしています。子どもは端末からその日の連絡を見ることができますし、私も出張先や自宅でパソコンやスマホから確認したり修正したりできます。もし、私が不在でクラスに入れない場合も、他の教職員が私のクラスの掲示板を閲覧できる権限を持っていますから、代わりに入ってもらうときにも安心感があります。
また、教職員で共有する資料については、ほぼ紙で出力するのをやめています。会議の議事録はデータと紙の両方で残しますが、それ以外はほぼペーパーレス化しました。もちろん、紙に出力したい人は各自で行って構いませんが、「データで作成し、データで共有する」のがうちの学校では日常化しています。
――だいぶ残業時間は減りましたか。
ペーパーレス化については時短になるというより、教員の動線の無駄がなくなったと言った方が確かだと思います。「資料を取りに学校に寄らなくていい」「紙に印刷した資料を取りに職員室に移動せずとも、教室にいながら見ることができる」といったメリットがあります。
――他にも業務の無駄をなくすコツ、動線を改善するコツはありますか。
まずは「机の上はきれいに」ではないでしょうか。机の上が散らかっていたら仕事のクオリティーや生産性が下がります。いざ使いたいときに物が見つからず、探し回る時間が増えれば、これほどもったいない話はありません。
私は出勤時から勤務中、退勤時まで、机の上に不必要な物を出さない状態にしています。引き出しも詰め込まずにゆとりを持たせ、どこに何を入れるかの「定位置」を決めています。引き出しの1段目には赤ペンやはさみなど使用頻度の高いもの、2段目にはハンコ類や予備の文房具を入れています。教室と職員室の2セット分を用意して、似たようなデスク回りの環境を整えることも、業務の無駄を省くことになります。

――整理整頓が行き届いているというより、そもそも物が少ない気がします。
「要らない物は捨てる」からです。チラシや資料で瞬間的に不要だと判断したものは、その場で捨てるようにしています。
――「即捨て」は潔いですね。必要な物はどうやって保存しているのでしょうか。
後で見るなどしばらく置いておく必要のあるものは、ファイリングして取っておきます。でも、大半はデータで手に入る時代になりましたから、紙で長く保管はしません。
あと、今すぐ処分はできず、データにもなっていないような資料はタブレット端末で写真に撮って保存し、紙は廃棄します。その画像はフォルダなどにしまい込んだりせず「カメラロール」や「アルバム」に置いておき、その予定や用件が住んだら消去します。画像もためておくと、他のものと交ざって探すのに時間がかかってしまいますからね。とにかくため込まないのがコツです。
――スケジュール管理などはどうしていますか。
タブレット端末のデジタルカレンダーアプリを使っています。
――端末を忘れたり、なくしたりしたら大変ですね。
スマホと同じでいつも身に付けて持っているものですし、そもそも机には端末しか出していないので、忘れたりなくしたりする余地がないんです。
【プロフィール】
柴田大翔(しばた・ひろと) 1990年、大阪府生まれ。大阪府の公立小学校教諭に勤務。月100時間以上の残業をほぼ毎日定時に帰れるまで激減させた経験を持ち、現在は日々授業や校務にタブレットをフル活用する。時短術、ICT活用、子どもたちが笑顔になる学級経営のコツをSNSで発信中。総フォロワー数は1万9000人を超える。著書に『今日から残業がなくなる!ギガ先生の定時で帰る50の方法』(学陽書房)、共著に『小学4年 学級経営ペディア』(明治図書)がある。