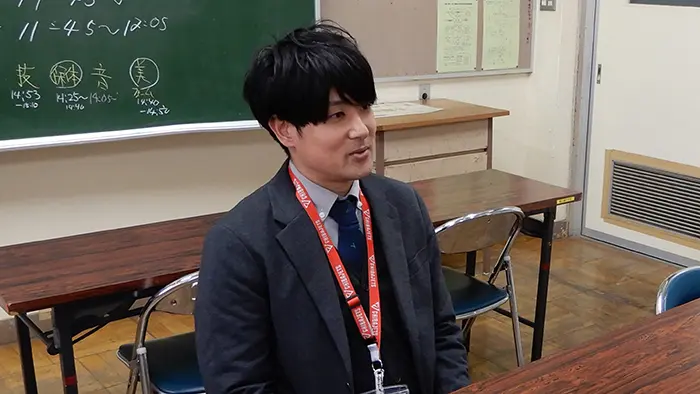学校現場での生成AIの活用はまだ始まったばかりだ。文部科学省の「生成AIパイロット校」として、全教員が授業や校務で活用を進めた千葉県船橋市立飯山満中学校(藤井武校長、生徒334人)では、さまざまな成果や課題が見えてきている。また、同校はこれまで授業改善を前提として、ICTの活用を進めてきた。教師が一方的に教える一斉授業からの脱却で見えてきた「新しい学びの姿」はどんなものなのか━━。授業を変えたことで学力に変化はあったのか、そしてこれから教員に求められることについて、同校の教員に話を聞いた。
理科の内藤亮生教諭は2022年度に飯山満中に赴任した際の印象を「学校を挙げてICTを活用するという熱量が高かった」と振り返る。自身も前任校で情報担当をしていたが「飯山満中は各学年にグーグル認定教育者レベル1か2を持つ教員がおり、分からなかったり悩んだりすると、パッと相談できる人がいた」と話す。
こうした環境は「本校に今年度赴任するまで、ほとんどICTを活用したことがなかった」と話す家庭科の道本理恵子教諭にとっても、心理的ハードルを下げる要因となった。この1年で家庭科の授業だけでなく、特別支援学級や道徳の授業、校務でも、生成AIを含め、積極的にICTを活用してきた道本教諭。「生成AIについても、本校では全教員で使おうとなったので、覚悟を決めて取り組んだ。嫌がらずにまず使ってみることが一番大事。いろいろなことを試してみている」と笑顔を見せる。

同校の「生成AI実践報告サイト」には、生成AIパイロット校に指定されて以降、23年11月から24年2月までの100の活用事例などが公開されている。内藤教諭は「知識の獲得だけでなく、生成AIに助言をもらうような形でも活用していた。教科書以上に学びを深めたいという生徒の一助にもなっていたのではないか」と授業での活用を振り返る。
進路指導主任だった内藤教諭は、授業以外にも活用事例の45番のように、高校入試の集団討論練習のガイドライン作成にも活用。また、活用事例46番のように教育論文を執筆する際に、生成AIを活用して生徒の変容を分析するなどした。「生成AIに触れる時間を意図的に作ったことは大きかった。大人が使ってみたら面白いと感じたことで、生徒にも使わせたいと思った教員が多い」と話す。
同校でこうして生成AIの活用が進んだのは、中学校の新学習指導要領が全面実施となった21年度から「授業改善」に取り組んできたからだ。教務主任の辻史朗教諭は「当時からICTの活用をメインにするのではなく、学習指導要領に合った授業改善をメインに取り組んできた。授業が変わらない中でICTを使っても、教員の負担感が増すだけだ」と指摘する。
研究主任の大川修平教諭も「生徒にこういうことを学ばせたい、こういう力を付けさせたいと考えて授業を変えていくと、必然的にICTを使うことになる。それがICT活用の正しい形だと思う」と話す。
辻教諭は自身の理科の授業について「一斉で伝える、教える、ということはほぼなくなった。学びの選択肢や環境は教員側で用意して、あとは生徒たちが自ら学んでいくような授業スタイルに変わった」と説明する。「今は検索すれば何でも出てくる。だからこそ生徒たちには、自ら学びに向かう力、学ぶスキルが必要なのだと伝えている」と語る。
数学科の大川教諭は、同校に赴任した22年度の当初はいわゆる一斉授業をしていたが、23年の年明けからは自由進度学習に移行したという。「本校にAIドリルのQubena(キュビナ)が導入されていたことも大きかった。キュビナはヒントもあるし、解説も見られる。授業に活用しない手はないと思った」と話す。
当時の1年生に「もう一斉授業はやめる」と伝えた時、生徒は「どういうことか意味が分からず、驚いている様子」だったという。そこで大川教諭は生徒に対して、なぜ自由進度学習にするのか、身に付けてほしい力について、十分な時間をとって説明した。
「それまでは、例えば『基礎問題は全員絶対にできるようにしよう』と思って授業をしていた。もちろんそれも大事だけれども、教員が教え込むのではなく、生徒自身が学びたいことを自分で決めて、自分の学びをコントロールできるような、自律した学習者になっていってほしい」と力を込める。
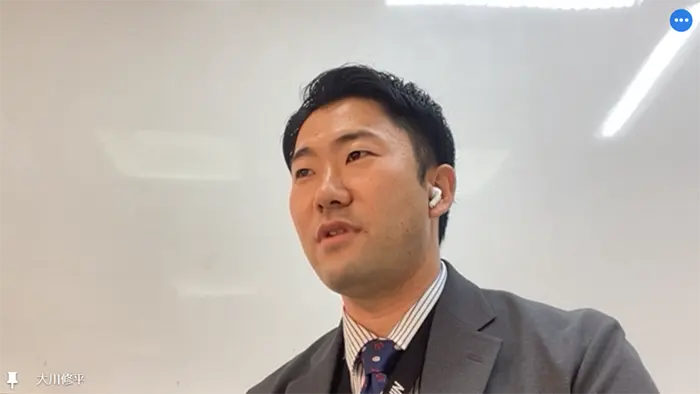
一方で、授業改善を進める中、生徒たちの学力面には変化があったのだろうか。辻教諭は「生徒の学びに向かう力は高まっていることが見て取れたが、教員が教えていないので、知識が定着しているのかという点には不安があった」と話す。しかし、外部の学力テストなどにおいても、どの教科でもマイナスな変化は見られていないという。大川教諭も「数学では定期的に小テストをしているが、その中央値は一斉授業をしていた頃と何ら変わらない」と話す。
今、子どもたちの学力は二極化の傾向が強まってきていると言われているが、辻教諭は「二極化はGIGAスクール構想スタート前からの傾向だ。本校では教員が一方的に教える授業を手放してきたが、学力的に大きく下がることはないのが分かってきた。もっと学びたいという意欲があった生徒は、どんどん進めるようになってきている」と話す。加えて、どの学力層も共通することとして「学んだことをアウトプットする際の表現の幅が広がってきている」と手応えを感じている。
授業を変えていった同校の教員らは「教員に求められることも、変わってきている」と実感している。辻教諭はこれから教員に必要な力として「未来を予測する力」を挙げる。「これまで私たちは自分の過去の経験からアクションを起こすことが多かった。それよりも子どもたちが社会に出る頃のビジョンを描けることが大事なのではないか」と話す。「例えば、人口の推移がこれからどうなっていくのかなど、社会の変化にアンテナを張り、学ぶ必要がある。そして、それを学ぶだけの余白を今の学校現場にどう生み出していくのかも、同時に考えていかなければならない」
大川教諭は「以前は『授業も生徒指導』だと思っていたところもあった。これからの教員に求められることは、子どもたちが集中しやすい、学びやすい環境を、認めたり、つくったりすることではないか」と投げ掛ける。
実は大川教諭は、空いている時には数学の授業を図書室で行っている。教室よりも広く、生徒たちは自由に席を移動したり、集中が続かない生徒は歩きながら問題を解いてみたりしている。「生徒一人一人、学び方は違う。大事なのは、子どもたちの学び方を教員が尊重すること。だけれど、それがうまくいかないときにはいつでも相談に乗るし、アドバイスをする。そういう関係を生徒一人一人と築けたら」と話す。
内藤教諭は「個人的にやってみたいことが1つある」という。「協働的な学びと、自律型学習、一斉授業の3つは、それぞれに身に付く力が違うし、この3つのバランスが大事だと言われている。教室を3分割して、違う課題に取り組みながらこれらの学びをローテーションしていくことに挑戦してみたい。ICTをうまく活用すれば、1つの教室でこの3つの学びをバランスよく行えるのではないか」と話す。「本校でも、まだ全てが変わったわけではない。だが、教育の可能性が広がっていることを実感している。既存の授業を脱却して、より面白い授業に取り組んでいきたい」と前を向く。