授業や校務など、生成AIが学校現場でもさまざまな形で使われるようになってきた。この動きは、教材コンテンツ、学習アプリにも広がり始めている。7月25日に初会合が開かれた文部科学省の「初等中等教育段階の生成AIの利活用に関する検討会議」でも、生成AIの初等中等教育段階の利用に関する暫定的なガイドラインの改訂に向けた論点案の中には、生成AIを搭載した学校向けの教育サービスの導入に際して、学校や学校設置者が留意すべきことが含まれている。私たちが気付かないうちに生成AIがさまざまな教材に組み込まれている時代は、そう遠くない未来に現実となっているかもしれない。生成AIを組み込んだ教育向けのデジタルコンテンツ、アプリなどで、どういった学びが実現し、提供する民間企業はどのような考えの下で生成AIを活用しているのか。各社の取り組みを取材した。
昨年の夏休み、ベネッセホールディングスでは、小学生向けに、生成AIとやりとりをしながら、自由研究のアイデア出しやテーマ探しに取り組める「自由研究お助けAI」を開発し、注目を集めた。その成果を生かして同社では今年も、バージョンアップした「自由研究お助けチャット」を展開している。

なぜ生成AIで子どもたちの自由研究を支援しようとしたのか。同社の開発担当者、白石健太さんは「生成AIという最先端の技術に直接触れて、驚きの体験をしてもらうこと、そして、生成AIを使うことで情報リテラシー教育もセットで行うという目的で企画を進めていた。社内でもいろいろな案があったが、自由研究のテーマが思い付かないといった子どもたちの声は以前から多く寄せられていたので、その悩みの解決に挑戦してみようと動き出した」と企画をスタートさせた当時を振り返る。
昨年に好評だったことを受けて、今年は中学生にも対象を広げる。中学生については、自由研究だけでなく読書感想文にも対応する。ちょうど生成AIが普及し始めた昨年夏ごろは、生成AIで読書感想文をつくる子どもが出てくるのではないかと懸念されていたが、その対策として長文の文章を生成しないように制限をかけ、本の読み方のこつや上手に感想文を書く方法をアドバイスする役割に徹する。子どもが作文する際に、本の内容や具体的な文章を教えるのではなく、あくまで筆が止まったときに適切なアドバイスをするような存在だ。
もう一つ、生成AIを組み込んだコンテンツとして、同社の進研ゼミでは今年の春から、小学4年生から中学3年生を対象にした「チャレンジAI学習コーチ」を開設。小学生は国語、算数、英語、中学生は国語、数学、英語、理科、社会について、疑問や分からないところを質問でき、勉強の方法にも答える。回答内容は、間違いが含まれないように、これまで同社が培ってきたノウハウを生かし、適した画像や動画が提示される仕組みになっている。
しばしば回答に間違った内容を含んでいたり、質問内容から学習して回答を変えていったりするのが生成AIの気を付けなければならない点ではあるが、既存の膨大なコンテンツと子どもの投稿内容が適切にひも付くように調整を重ね、子どもの質問内容からは学習しないようにしているという。その理由を白石さんは「子どもが個人情報につながる内容を入力して、それを生成AIが学習してしまうリスクを一番に考えた結果、現在の仕様になった」と説明する。
「読むこと」「書くこと」「聞くこと」「話すこと」の4技能のスキルを伸ばしたいが、添削や評価、そして課題づくりが大変――。そんな英語の教員が抱える悩みに応えようとAI英語学習アプリを提供しているポリグロッツは4月から、学校向けに「レシピ― for School」を正式にリリースした。
レシピ― for Schoolの機能の一つ、スマートアサインメントは、英語4技能に対応した課題作成をサポートする。
どう課題を作成していくのかというと、まずは問題構成を指定。選択問題や正誤問題といったオーソドックスなリーディングの問題だけでなく、文章を書かせる問題なども設定できる。その上で、同社が契約している英文記事を選ぶと、あっという間にその記事を題材にした課題が出来上がる。
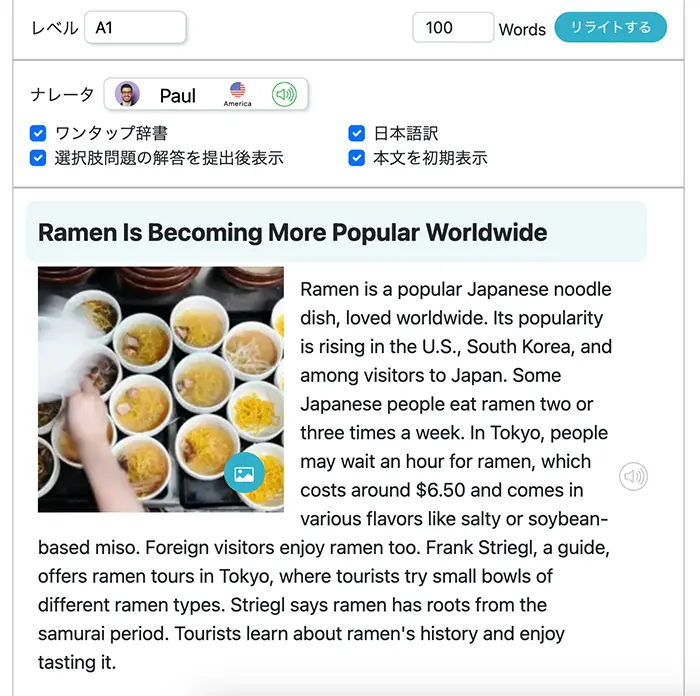
記事の英文をAIが読み上げる機能や、英文を生徒が音声入力する機能もあるので、リスニングやスピーキングの課題を出すこともできる
生徒のレベルを考えると、英文の記事が長過ぎたり、難し過ぎたりするというときは、ワード数を調整して要約したり、CEFR(セファール)に応じた英文に書き換えたりして難易度を変えることも可能。英文記事は毎日配信されるため、時事的な話題など、生徒の興味関心に合わせて探せる。スピーキングの流ちょうさや発音を評価したり、英文を添削したりすることもAIが行っている。
同社法人営業部部長の山本修久さんは「英語では4技能を統合した学びが求められる一方で、そうした課題をつくり、添削や評価までするのは、莫大な時間がかかる。英語の授業をDXし、教師の課題を解決していきながら、生徒の英語の能力を高める手助けをしていきたい」と力を込める。
気になるのは問題の精度だが、これも生成AIのバージョンを上げて以降、正解が複数あるといった難のある問題はほとんど出なくなっているという。導入された学校の教員から寄せられる声を踏まえ、より学校現場の実情に合った改善も日進月歩で進んでいる。
これなら生徒のレベルに合った課題をたくさんつくることができるし、添削や評価にかける時間もかなり圧縮できそうだ。しかし、これによって教員の仕事が奪われてしまうのではないか、という懸念も頭をよぎる。
実際にそういった反応をする教員もいるとした上で、山本さんは「テクノロジーだけでは学習は継続しない。人がいることによって学習効果が最大化できる。AIが出した結果を踏まえて、教員がこれまでの知見を生かしてアドバイスをしたり、課題に応じた授業を考えたりする。そういう時間をつくってほしい」と話す。
リスキリングなど、社会人を対象とした教育に目を向けると、生成AIの活用はさらに進んでいる。DX人材育成サービスとしてオンライン学習の教材や診断テストを提供するWHITE。同社では現在、アニメーションを利用した動画教材で、プロットやキャラクターのデザイン、音声などを生成AIで制作している。生成AIがつくったものを人間が確認し、修正を繰り返しながら完成度を高めていくそうだ。
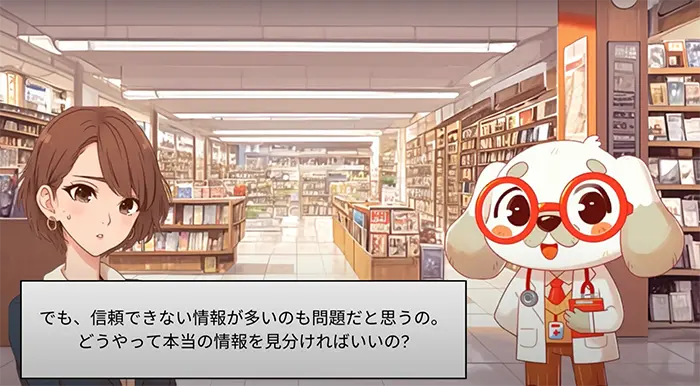
同社代表取締役の横山隆(ゆたか)さんは「手作りよりも生成AIを使った方が早いし、つくろうと思えば大量につくることもできるが、当社としては、より良いものを提供したいという考えで生成AIを使っている。教材である以上、正しい情報かつ教材としてふさわしい品質になっているかということが大事になるので、人間がちゃんと見て、チューニングしている。生成AIはあくまで、より良いものをつくるためのツールだ」と、量を生み出すことよりも、質を高めるための生成AI活用である点を強調する。
特に学習教材では、つくったものをすぐにユーザーに提供して、何か問題があれば修正して対応するというやり方は向かない。内容に間違いやうそがあってはいけないのはもちろん、この内容で本当に学習者が理解できるのかを見極め、最初からそのクオリティーに達しているものを提供しなければならない。
「だからやっぱり、編集者のような立場の人間が必要だ」と横山さん。「AIは8割、9割くらいの完成度を実現するのは得意だが、百発百中で最初から正しいものを出すことをAIにやらせるのはお門違い。どうしても残ってしまう不確実な部分は人間が担っていく必要がある」と指摘する。