行動分析学のアプローチで、発達につまずきのある子どもやその家族を支援してきた奥田健次理事長。2018年に長野県の西軽井沢に「サムエル幼稚園」を開園した後、24年春には隣接する佐久市内に「さやか星小学校」を開校し、新たな学校教育の在り方を社会に提起している。奥田理事長が目指す、今の公立校にできない教育とは。(全3回)
――「サムエル幼稚園」に続き、この春に開校した「さやか星小学校」を設立するまでの経緯を教えてください。
私が設立したサムエル幼稚園を卒園していく子どもたちが、そのまま地域の小学校に上がり、いじめや不登校といったつまずきに遭うのは見ていられないと思っていました。でも、幼稚園をつくるのに借金を背負って、さらに小学校をつくるなど無理に決まっていると思っていました。
今回、小学校を開校できたのは、隣接する佐久市内の臼田地区が4つの市立小学校を統合するのに伴い、閉校する青沼小学校の校舎と敷地の利活用を考えているというお話をいただいたからです。うちの幼稚園を卒園した子どもだけのためではなく、他の幼稚園や小学校からやってくる子どもたちも受け入れ、全国に開かれた小学校をつくりたいと申し出て、校舎と校地の購入に至りました。幼稚園の開校までに構想も含めて6年、それからさらに6年の時を経て小学校を開校することができました。今年度は1年生から4年生まで22人が学んでいます。

――さやか星小学校は、幼稚園と同じく行動分析学に基づき、さらにはデジタルテクノロジーを掛け合わせた先進教育を謳(うた)っています。どのような教育を目指しているのでしょうか。
本校は、いくつかの学校の「あたりまえ」を変えることを教育方針に据えています。
一つ目は、「子ども同士の人間関係は、子どもの自主性に委ねるべき」というあたりまえを変えていきます。子ども同士の人間関係に、教職員や保護者が果たす役割は大きいにもかかわらず、問題解決を子ども任せにすると、小さなトラブルの積み残しが深刻ないじめ問題へと発展してしまいます。他者との適切な関わり方を学ぶのも学校という場なのです。
私はこれまで臨床家として、いじめの問題にも数多く関わってきました。いじめが起きてから、不登校になってから、子どもが命を絶ってから、学校が対策に乗り出す。そんなことは専門家としては許せないのです。
そのため、「いじめ防止の3Rプログラム」を導入して安心・安全な学校風土づくりを進めています。米国で、いじめ防止の活動を行っているロリ・アーンスパーガー氏が提唱しているプログラムで、日本では初の導入となります。
3Rとは「認識すること(Recognize)」「対応すること(Respond)」「報告すること(Report)」のことです。私たちの学校では、「いじめは起きるものだ」という前提に立ちます。これは大人社会でもそうです。人の好き嫌いによる嫌がらせなどは存在する。そこをいかにフェアに乗り切っていくかを学校教育段階で学ぶのが、この「3Rプログラム」なのです。
このプログラムでは、道徳科の教科書から理解を深めようとするのではなく、ロールプレーイングを含めた実践を中心にあらゆる機会で学んでいきます。いじめる役、いじめられる役、傍観者役を台本に沿って代わる代わる演じます。その際、いじめっ子から「絶対、親や先生にも誰にも言うなよ」と脅されても、いじめられた側や傍観者役の子は、周りの大人に報告をするという練習を繰り返します。そうすることで、子どもたちは「いじめをしても大人に伝わってしまう」と知ることになりますから、一定の防止効果があるのです。
海外でも同様の実践が行われている学校があります。とはいえ、3Rプログラムを実践しても、全てのいじめが完全になくなるわけではありません。ですから、いじめ防止にはかなりの労力が必要なのです。私たちも手間を惜しまずに取り組んでいます。例えば、「ともだちどうかな」という定期アンケートを実施して、孤立している子がいないかを把握しています。
また、本校のような少人数の学校でも、大人の目の届かない空間的な死角があればいじめは起きる可能性があります。そうしたところに教員の目が届いているかを確認し、休み時間も死角をつくらないよう、遊ぶ場所を限定するなどの工夫をしています。児童数が増える来年度以降が正念場です。「3Rプログラム」は児童が一度経験したら終わりではなく、教職員も保護者も繰り返し学んでいく必要があります。

――「あたりまえ」を変える2つ目のこととして、「問題行動を減らす」を挙げています。どのように変えるのでしょうか。
前にもお話ししましたが、行動分析学において「行動を変える」とは、その子どもの「心の内側」ではなく、「環境」を変えていくことを意味します。何か不適切な行動があったときに、「〇〇しない」という目標を立てると禁止するばかりの指導になり、そんなネガティブな方法ではうまくいきません。一見うまくいったように見えるのですが、叱られないためにやるようなネガティブな育ちになってしまいます。それよりも「望ましい行動を増やす」という発想の転換と実践が必要です。多くの先生は「問題行動を減らしたい」と思っているはずですが、逆なのです。
本校が導入する「スクールワイドPBS」(School-Wide Positive Behavioral Support:学校規模ポジティブ行動支援)とは、子どもの望ましい行動を具体的に設定して、その行動ができた際に賞賛・承認をし、そうした行動が起こりやすい環境を整えることで望ましい行動を引き出す教育メソッドです。
例えば、図書館で大きな声を出してしまうADHD(注意欠陥・多動症)の子どもがいました。多くの場合、先生はその子も含めてクラス全員に「静かにしなさい」と注意をするのではないでしょうか。でも、そうした指導では、その子は何年たってもできませんでした。そうではなく「廊下では普通の声で、図書館ではささやき声で話そう」と、教員が見本を見せながら楽しく練習を重ねました。すると、図書館に入ると大きな声を出さずに話せるようになりました。
このように、「スクールワイドPBS」に基づく支援を学校全体に広めています。行動分析学を応用した本校の中核的な取り組みと言えます。
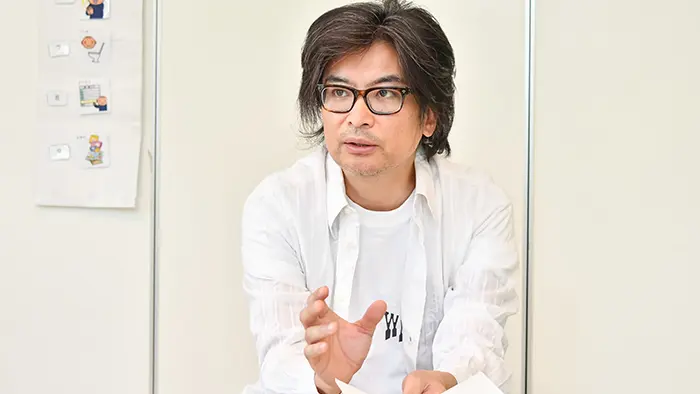
【プロフィール】
奥田健次(おくだ・けんじ) 兵庫県出身。学校法人西軽井沢学園創立者・理事長。大阪キリスト教短期大学副学長。(一社)日本行動分析学会理事、日本子ども健康科学会理事、日本場面緘黙研究会常任理事などを歴任。専門行動療法士、臨床心理士 。応用行動分析学、行動療法をもとに親子を支援する心理臨床家。全国各地からの支援要請に応えている。日本国内だけでなく、世界各地にも赴く。日本で初めて行動分析学に基づく幼稚園、小学校を設立・運営する。