小学校はこれまで、全ての教科を担任が教える「学級担任制」を基本としていた。しかし、近年、教科ごとに専門の教員が教える「教科担任制」が広がっている。背景には学習指導要領の着実な実施や、中学校に進学した際の「中1ギャップ」の解消、学校における働き方改革の推進などが挙げられる。今後は小学校高学年だけでなく中学年に拡大する見通しだ。小学校における教科担任制のメリットとデメリット、導入事例や課題を紹介する。

教科担任制とは、教員が特定の教科を担任して授業を行うことを指す。「国語の〇〇先生」「〇〇先生は理科を教えている」といったように、教員ごとに教える科目が異なる。日本では戦後の教育改革により、中学校以上の教育段階で教科担任制が導入された。学習内容が高度化する中学校や高校では、教員が一つの教科について幅広い知識や技能を持ち、授業をした方がより良い授業が可能になるとの考えからだ。
小学校では一人の担任が全ての教科を教える「学級担任制」が採用されてきたが、実は、これまでも小学校で特定の教科を学級担任以外が教える「専科指導」は行われてきた。専門的な指導の充実を図るため、中学や高校の免許状を持つ者が免許教科に当たる教科を小学校で教える「専科指導教員」が自治体の裁量で配置され、「音楽」「図画工作」「体育」「家庭」などの実技教科、「理科」「算数」などでも専科指導は広がっていた。

2022年度に本格導入された小学校高学年(5・6年生)の教科担任制は、学級担任制を根本から変える大改革といえる。21年1月の中教審答申「『令和の日本型学校教育』の構築を目指して ~全ての子供たちの可能性を引き出す、個別最適な学びと、協働的な学びの実現~」の中で、小学校で教科担任制を本格的に導入することが示され、文部科学省の検討会議は21年7月に「義務教育9年間を見通した教科担任制の在り方について」を取りまとめた。この中で、小学校高学年における教科担任制推進の方策が示された。
教科担任制導入の趣旨・目的は次の通り。
・授業の質の向上
GIGAスクール構想で整備された1人1台端末などを活用した授業や、個別最適な学びや協働的な学びの実現に向け、教科指導の専門性を持った教師が指導することで、授業の質が向上し、児童の学習内容の理解度や定着度が向上する。
・小・中学校間の円滑な接続
中学校に進学した際に、児童が学習・生活面で順応がしやすいよう円滑な接続を図る。いわゆる「中1ギャップ」の解消。
・多面的な児童理解
専科教員と学級担任の複数の教師による多面的な児童理解を通して、児童の心の安定を図る。
・教師の負担軽減
担当教科の減少、持ちコマ数の軽減で授業準備を効率化する。このことにより教員の負担を軽減する。
グローバル化やSTEAM教育の充実・強化に向けて「算数」「理科」「外国語」「体育」の4教科を優先的な対象とし、小学校高学年の教科担任制を進めることとした。24年度までの3年間で3800人の教員定数改善が行われた。
・文部科学省 義務教育9年間を見通した教科担任制の在り方について(報告)
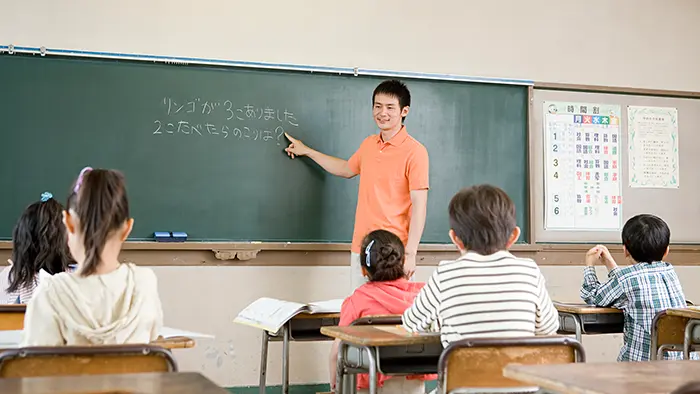
小学校の教科担任制の形はおおむね次のような類型がある。
・学級担任間で授業を交換して指導する「授業交換」
学級担任を持ちながら、他の学級や他学年の特定の教科を担当する。
・専科教員による授業
学級担任を持たず、一つ、または複数の教科を担当する。教科担任制の加配で措置される。複数の学校を兼務する場合もある。
・中学校教員による「乗り入れ授業」
中学校教員が小学校で免許相当の教科を指導する「乗り入れ授業」を行う。
どのような形を取るかは、学校規模や地理的条件などにより各自治体や学校が判断する。
また、自治体独自の取り組みが行われている場合もある。教科担任制の推進のため、文部科学省は23年3月に事例集「小学校高学年における教科担任制に関する事例集~小学校教育の活性化に繋げるために~」を公表し、教科担任制の取り組み方や教員の時間割、導入に際しての工夫を紹介している。例えば児童数700を超す大規模校では、授業交換、専科教員による授業、中学校教員の乗り入れ授業をフル活用している。一方、単学級の小規模校では、理科や図工、外国語などの専科教員が、複数の学校を兼務するなどだ。
・文部科学省 小学校高学年における教科担任制に関する事例集~小学校教育の活性化に繋げるために~(令和5年3月)

国の動きに先行して教科担任制に取り組む自治体の例から、教科担任制の効果やメリットを全国の事例から見ていこう。
横浜市は、18年度に教科担任制の一種である「教科分担制」を開始。複数の教科を分担して指導するチーム型で推進した。6年生は4人の教員が4クラスの授業を分担する、といった形だ。特徴は、学級担任を持たない学年主任「チーム・マネージャー」を配置すること。チーム・マネージャーは、自身も教科を持ちながら学年経営のマネジメントを行う。児童からは「担任以外の先生との関わりが増え、相談できる先生が増えた」などの声が上がった。この方法のメリットは、年度の途中でも分担教科を変更したり、増やしたりすることが可能なことだ。学級づくりを優先したいという声があれば、学級担任の持ち時間を増やし、2学期以降は分担を多くしていくなどだ。
関連記事:小学校「教科担任制」(下)学級経営から学年経営への意識改革
小規模校でも工夫して教科担任制を導入している例もある。19年度に教科担任制を始めた大分県の100人以下のある小学校では、担任を受け持たない教員や、特別支援学級の担任も含めた複数の教員による「ブロック担任制」を組んだ。特別支援学級の担任が通常級で教科の指導する際には、学級担任が特別支援学級の児童の個別学習にあたるなどの対応をした。実際にその学校に勤務する教員によると、複式学級や1学年1学級だと学級王国になりやすいが、複数の教員が関わることで多様な視点で子どもの成長を見取ることができるメリットがあるという。
関連記事:小学校教員に聞く(下) 高学年の教科担任制の難しさ
県内全ての公立小学校の高学年で、教科担任制を実施している茨城県では、各学校の希望を聞き、できるだけ要望に添うように専科教員の配置・派遣をする。希望の多い算数、理科、外国語(英語)を中心に、中学校の各教科の免許を持つ教員が拠点校に配置、周辺の複数校に派遣するケースもあるという。専科教員の専門性のある、系統的な質の高い指導を見聞きする機会になれば、若手教員の成長を促せそうだ。
関連記事:4月から小学5、6年で教科担任制 茨城県が方針、全国初
関連記事:小学校教員に聞く(下) 高学年の教科担任制の難しさ
兵庫県の川西市立多田小学校では、23年度から教科担任制に加え、40分授業午前5時間制、学年担任制を組み合わせた新教育課程に取り組む。「いろんな先生の教え方があって面白い」と児童にも好評だ。教員1人あたりの担当教科は3、4教科に減ったことから教材研究に集中でき授業の質が高まる、また退勤時間が早まるなど教員の業務負担の軽減につながっているという。
関連記事:【40分授業午前5時間×学年・教科担任制①】 公立小の大改革
【シリーズ】40分授業午前5時間×学年・教科担任制
関連記事:【40分授業午前5時間×学年・教科担任制②】 働き方どう変わる?
【シリーズ】40分授業午前5時間×学年・教科担任制
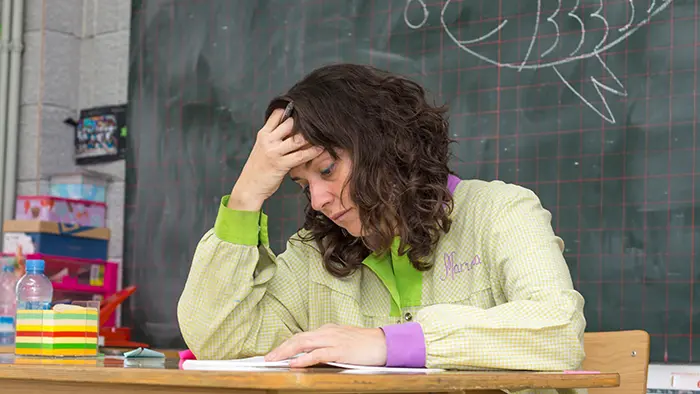
一方で、教科担任制にはデメリットも存在する。これは導入の検討段階から「留意すべき事項」として指摘されてきたことで、中教審でも従来の学級担任制での指導による「良さ」が損なわれないようにと注意を促している。
小学校では学級担任が全ての教科を教えることにより、教科横断的なカリキュラム・マネジメントによる指導が効果的に行われてきた。国語や算数で学んだことを、社会や理科などの他の教科での学びと関連付ける、また総合的な学習の時間の活動や行事、さまざまな体験活動を教科の学びと結び付けて効果的な指導を計画・展開するのは学級担任ならやりやすい。
教科担任制でこうした教科横断的な指導の視点が弱まると、授業の質は高まらず、かえって子どもたちの学びが細切れになりかねない。横浜市や川西市立多田小学校のように「チーム担任制」や「学年担任制」が教科担任制と合わせて導入されるのも、こうした学びの分断リスクを防ぐ工夫といえるだろう。
授業交換型、専科教員型、乗り入れ型のいずれのタイプを採用するにせよ、教科担任制の導入により時間割の作成は複雑化する。特に、小規模校では複数教科を担当する教員が多くなるため、教員の空き時間や教室の利用状況を考慮したスケジュール調整が求められる。
専科指導教員が巡回する場合も事前調整は必要だ。これまで学級単位で柔軟に調整できていたものが、学年単位や学校単位の調整となっている。学校行事の変更や、感染症予防のための学級閉鎖などの対応の際にも、調整が必要になり教員の業務負担が増す恐れもある。対策としては時間割作成ソフトウエアの導入など、校務のICT化を進め効率的に時間割管理ができるようにする必要がある。
「小学校は、中学校と同じことはできない」と教科担任制のデメリットを指摘する専門家の声もある。既存の教員による授業交換型の場合、一つの教科を長時間担当することで休み時間の児童管理が手薄になるといった指摘だ。中学生とは違い、教員が不在で不安になる児童もいるかもしれない、というのだ。文部科学省の事例集でも、教室移動や質問対応に教員も子どもも「5分休みでは時間が足りない」などの課題も上がっている。
関連記事:小学校の教科担任制は本当に働き方改革になるのか?(庄子寛之)
また、経験年数の浅い教員は教科の垣根を越えた授業の計画力や実践力がつきにくいのではという指摘もある。中堅やベテランでも、異動により次年度の働き方の見通しがつきにくい場合もあるだろう。異動先でどの教科を担当するのか、学級担任も持つのか、あるいはまだ教科担任制を取っておらず全ての教科を一人で教えることになるのか、などだ。専科指導教員を含む教師同士が連携不足にならないよう、管理職によるこれまで以上に積極的な情報共有やマネジメントが求められよう。
関連記事:小学校の教科担任制 「成長の場が失われる」は本当か(喜名朝博)

22年度から始まった小学校の教科担任制は今後、中学年(3・4年生)にも拡大する見込みだ。教科担任制の最新動向と今後の展開を解説する。
小学校での教科担任制は、25年度から中学年(3・4年生)でも導入される。24年5月、中教審の特別部会は「『令和の日本型学校教育』を担う 質の高い教師の確保のための環境整備に関する総合的な方策について」を取りまとめ、教科担任制を小学校中学年(3・4年生)にまで広げる考えを示した。文部科学省は25年度概算要求で「小学校における教科担任制の拡充」として2160人の定数改善を盛り込み、25年度からの小学校中学年への教科担任制を拡充する。
高学年での導入で見られた効果に加え、中学年ならではの学習環境や教員の業務負担軽減、若手教師の支援を見据えてのことだという。特別部会の報告では次のように導入の理由を挙げる。
低学年に設けられていない社会科、理科、外国語活動や総合的な学習の時間が始まり、抽象的な内容も増えるため、教育の質の向上を図る必要がある。
国の定める年間標準授業時数は3年生で980単位時間、4年生で1015単位時間となっており、小学校高学年や中学校の1015単位時間と同程度。中学年を受け持つ学級担任の持ち時間を軽減する必要がある。
近年の大量退職・大量採用に伴い若手教師が増加。新規採用教師への支援の観点から、新卒1年目は学級担任ではなく教科担任として学級副担任を担当させたり、持ち授業時数の軽減を図ったりする取り組みを教育委員会がしやすくすべき。

文部科学省が公表した「22(令和4)年度の教育課程の編成・実施状況調査」によると、22年度の小学校での教科担任制の実施率は、前回の18年度調査と比べ、優先4教科を中心に全ての教科で増加した。今後も実施率は増えてくるものと思われる。「中1ギャップ」の解消に教科担任制がどのように影響を与えるかも今後のエビデンスが待たれるところだ。
学級担任制に慣れ親しんできた小学校で教科担任制が定着するには、メリットばかりでなく、現場の声も含めたデメリットに目を向け、確実に対応していくことが必要だろう。1学年単学級の学校や複式学級のある学校では、そもそも教員数が限られており教科担任制が難しいケースもある。教科担任制を広めるには専科指導教員をはじめとする教員の加配は必須だ。自治体の財源が限られ、また、教員不足やなり手不足が深刻化する中簡単なことではないが、現場の教員個人の努力に委ねることなく、組織的に課題に向かう姿勢が求められる。