米国では学力標準テストの点数で子供を評価し、その点数で学校や教員までもが評価されている――。この話を聞いて、日本も他人事ではないと思う人も多いだろう。「米国で起こった公教育崩壊の波が、日本にもすぐそこまで押し寄せてきている」と語るのは、新自由主義の大きな流れの中で米国の公教育崩壊を捉え、研究を重ねてきた教育研究者の鈴木大裕氏だ。インタビューの2回目は、日本の公教育が抱えている問題の本質や今後の懸念点を語ってもらった。(全3回)

アメリカの教育学者のピーター・タウブマンは、「新自由主義的な教育改革を成し遂げるには、3本のくさびがある」と述べています。
1本目は、学力をテストの点数へと再定義するくさび。2本目は、教員の指導力をテストの点数を上げる能力と再定義するくさび。そして3本目は、カリキュラムの基準からパフォーマンスの基準へとすり替えるくさびです。
日本では2007年、43年ぶりに全国学力・学習状況調査が復活しました。ポイントは抽出式ではなく、あえて悉皆式であるということです。もし、本当に学力を調査することが目的であるならば、抽出式で十分なはずです。
全国学力・学習状況調査は、同時に規制緩和で都道府県別だけでなく、学校別の成績も開示可能になりました。小学6年生と中学3年生の全児童・生徒が受けていて、成績も知ろうと思えば知れるといった時点で、もうすでに市場原理は回り始めているわけです。
しかも、米国同様、学力テストがどんどん増加しました。約70%の都道府県が独自の学力調査をしていて、政令指定都市に限ればその割合は約85%にも上ります。こうしたテストへの対策に、学校や教員、子供たちが日々追われているわけです。
つまり、日本の公教育にもすでに1本目と2本目のくさびは打ち込まれていると言えるでしょう。
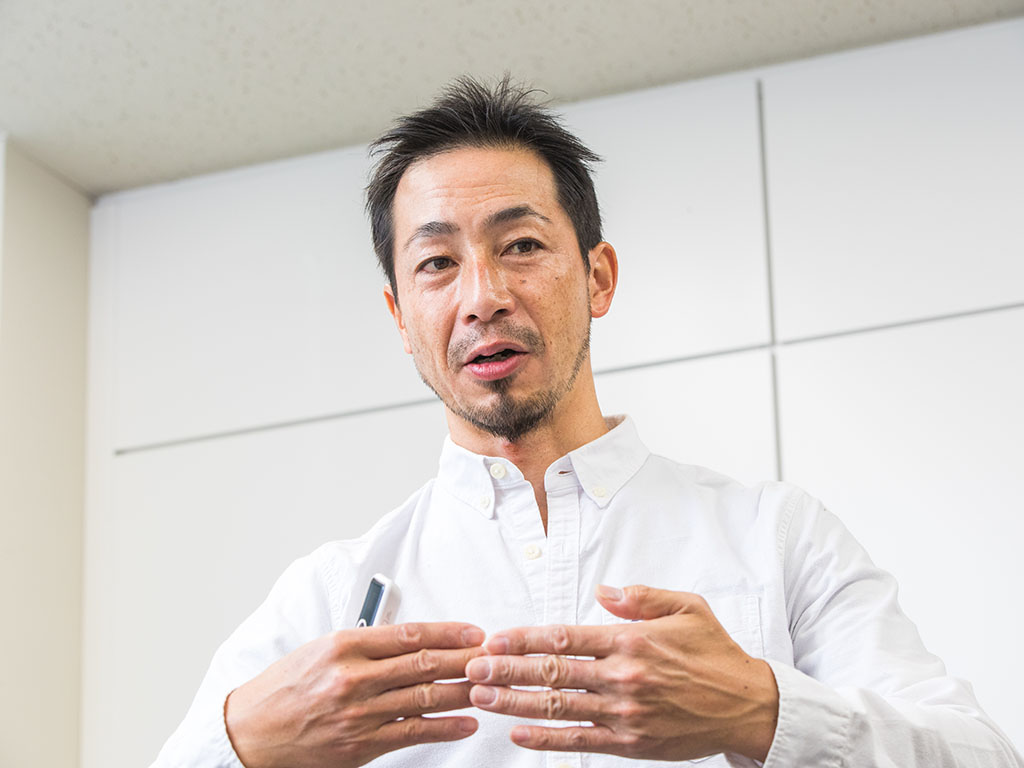
3本目のくさびも、4月から順次実施される新学習指導要領によって打ち込まれようとしています。
高校における「公共」という科目の新設や外国語教育、プログラミング教育などが注目されている新学習指導要領ですが、一つ大きなポイントがクローズアップされてこなかったように思います。
今までの学習指導要領では、「何を学ぶか」「何を教えるか」という、いわゆるカリキュラムの基準でした。それが新学習指導要領では、「何ができるようになるか」というパフォーマンスの基準、つまり学習到達度の基準へと変わろうとしています。
学力はペーパーテストの点数、教員の能力はペーパーテストの点数をいかに上げられるかになり、カリキュラムの基準はパフォーマンスの基準へと変わってしまう……。ピーター・タウブマンは、「この3本のくさびが打ち込まれてしまったら、もはやそのトライアングルから逃れることはできない」と語っています。
日本でも学校選択制が広がってきています。もはや義務教育における公立の学校も、保護者や子供がカスタマーとなって選ぶ時代になってきているのです。
学校選択制は、昔は教育の多様化を目指すものでしたが、今は完全に「市場型」学校選択制になっていると言えるでしょう。「自己責任で、身の丈に合った学校に行ってください」という状況になってきているのです。
同様に大学も、学術研究を深める場ではなく、職業教育を施す場になりつつある。「もし、あなたの学部が、地域の労働力や経済に貢献していないのだったら、そんな学部は統廃合してください」というとんでもない通知を、2015年に文科省が全国立大学に出しているのです。
要は経済界のニーズに合っていないのだったら、そんな学部はいらないということです。今ではその流れが高校にも確実に下りてきています。
今の日本の教育現場は、米国と同様、学力標準テストの点数によって徹底管理されています。都道府県や各学校が「これをやればこれだけ上がった」「これは効果がなかった」などと、どうやったら全国学力・学習状況調査の点数を上げられるかについて、活発に議論しているわけです。
でも、議論されるべきは、そもそも何をもって「学力」と呼ぶのか、ではないでしょうか。全国学力・学習状況調査で測るのは、国語と算数(数学)のペーパーテストの点数だけです(理科は3年に一度)。子供たちをそんな極端に小さな土俵で勝負させ、それだけで子供の評価を決めていいのでしょうか。
つまり、全国学力・学習状況調査を主体にした今の教育界において改革すべきは、ペーパーテストを前提にした狭く偏った「学力観」そのものです。
さらに教員の評価についても問い直すべきです。
フィンランドの元教育長官のサルベルクは、「フィンランドではどうやって教員を評価するのか」と問われた際に、「そんなこと、話もしません。その代わり、私たちはどのように彼らをサポートできるかを議論します」と答えたそうです。
つまり、米国や日本とは議論の枠組みそのものが違うのです。「教員をどうやって評価するのか」というアウトプットの問題ではなく、「教員をどうサポートするのか」というインプットの問題であり、どれだけ投資をするかの問題だと見ているわけです。

公教育民営化のきっかけづくりでいうと、「学校における働き方改革」も危ないと思っています。本来、働き方改革は良いことですが、それさえも新自由主義の波に飲み込まれてしまう危険があります。
例えば、小学校の外国語教育について、現場からは悲鳴が上がっています。すると予算がついて、民間委託が検討されます。しかし、最初は外国語教育やプログラミング教育から始まったことが、教員不足という追い風もあって、他の教科もどんどん民間委託になってしまうのではないかと心配しています。
すでに部活動は外部委託されつつあります。そうなると、今後は、運動会は地元のスポーツクラブに丸投げ、修学旅行も旅行会社に、合唱コンクールも……となりかねないわけです。
こうした官民連携がどんどん進み、公立学校が民間に依存しきったときに、国からの予算が打ち切られたら、外部委託されていた教育事業は完全に民営化されてしまいます。
そうなったら、何が起こるでしょうか。例えば、高いレベルでスポーツや芸術、音楽などをやりたい子は、今まで公教育の中でもなんとかやってこられました。しかし、公教育が民営化してしまえば、もうお金を払える家庭の子しかできなくなってしまうのです。
今は、働き方改革にかこつけて、学校の「塾化」が進んでいます。どんどん学校がスリム化して、教員がやるのは授業だけになる。
塾とは違う学校の役割とは何なのか、塾講師とは違う教員の役割とは何なのか――。「学校における働き方改革」を本気で考えるのであれば、私たちはそのような根源的な問いに、一度立ち戻る必要があるのではないでしょうか。
(先を生きる取材班)
鈴木大裕(すずき・だいゆう)教育研究者。1973年、神奈川県生まれ。16歳で米ニューハンプシャー州の全寮制高校に留学し、そこで受けた教育に衝撃を受け、日本の教育改革を志す。97年にコールゲート大学教育学部卒、99年にスタンフォード大学教育大学院修了(教育学修士)。帰国後、通信教育にて教員免許を取得し、02年から6年半、千葉市の公立中学校で英語科教諭として勤務。08年に再び米国に渡り、フルブライト奨学生としてコロンビア大学大学院博士課程に入学。16年より高知県土佐郡土佐町に移住、19年より土佐町議員。著書に『崩壊するアメリカの公教育――日本への警告』(岩波書店)など。