特別支援教育と教育工学を専門とする兵庫教育大学大学院学校教育研究科の小川修史准教授は、今年5月からスカート姿で教壇に立っている。「自分の中の多様性をアップデートしたい」と、小川准教授がファッションの世界に飛び込んだのは2年前。(一社)日本障がい者ファッション協会(JPFA)の副代表に就任し、障害の有無や性別にかかわらず着用できる巻きスカート状のアイテム「bottom’ all(ボトモール)」を開発した。ファッションの観点から多様性について考える小川准教授に、特別支援教育の現在地を聞いた。(全3回の1回目)
――ファッションに取り組み始めたきっかけを教えてください。
自分の中の多様性をアップデートしたいと思い、2年ほど前にファッション分野に飛び込みました。
私の専門は、特別支援教育のICT活用。昨今は特にニーズが高まっており、講演のオファーもたくさんいただきます。一方で、「何か使いやすいアプリを教えてください」など、解決策を求めるテーマが多いのが現状です。「どのアプリを使えば、算数や国語ができるようになるか」を優先しながら児童生徒と向き合うことは、果たして特別支援教育と言えるのだろうかとモヤモヤとした思いが募っていきました。
今の特別支援教育は、教員や保護者など大人側に「この子どもをいかに“普通”にするか」という意図が見え隠れしているように思います。その時点で、多様性を無視しているのです。
しかし、「多様性を受け入れるとは、どういうことか」と問われたときに、私自身も明確に答えられないことに気付きました。多様性の価値観をアップデートする必要性は感じていたものの、その答えが自分の中になかったのです。
――そんな中で、なぜスカートをはくようになったのでしょうか。
もしも、車いすに乗ることが当たり前の世界だとしたら、今頃どんなファッションがはやっていただろうか……。私が着用するこのスカートは、そんな視点から生まれました。
私が副代表を務めるJPFAは、障害の有無や性別、年代などにかかわらず全ての人が魅力を感じられて、機能的なファッションデザインを生み出すことをミッションに活動しています。
このスカートもJPFAで開発したものです。商品名は「bottom ’all(ボトモール)」。「全て(オール)の人にボトムスを」というコンセプトだからです。

誕生のきっかけは、ある車いすユーザーの「おしゃれすることを諦めた」という一言でした。例えば、身体障害者にとってデニムをはくのは容易ではありません。生地が硬いので足に通すだけでも一苦労ですし、腰まで上げようとすると、お尻を浮かして腕力だけで引っ張り上げなければなりません。
身体障害があっても簡単に着用できるボトムスについて学生と議論をする中で、「スカートのように腰に巻き付けられたら、ストレスなく着用できるのでは」というアイデアが生まれました。そして、車いすの座席に広げて座るだけで着脱できるデザインが形になったのです。足に通すことも、腰を浮かして大変な思いをしながら引っ張り上げることも不要です。
一方で、「スカートは男性がはきづらいかもしれない」という指摘もありました。確かにそうかもしれませんが、私たちが目指しているのは、障害の有無や性別、年齢などを問わず、誰もが楽しめるデザインです。「スカート」というこれまでの概念ではなく、パンツ、スカートに続く第3の選択肢としてボトモールという概念を生み出せばいいと考えました。
――日常生活でスカートをはいているとのことですが、着用して、周りの目は気になりませんでしたか。
着用前は正直、とても気になりました。しかし、実際にはいてみると、単純にとてもおしゃれで感激したことを覚えています。加えてこれまではいていたパンツと比べて風通しが良く、着心地も快適で機能的にも優れていることに気付きました。
私はもともと、ファッションには全く興味がありませんでした。しかし、スカートをはいていると、街中や大学で「おしゃれですね」と見ず知らずの方から声を掛けられることがあります。そのおかげで、私自身もおしゃれをポジティブに受け入れられるようになりました。
大学では、教えたことのない学生から「ツイッターで見ました! 応援しています!」と声を掛けられることもあり、何か伝えられているのかなとうれしく思います。
――ファッションの分野から、特別支援教育や多様性について考えてみて、どんなことを感じましたか。
今の社会は、健常者と呼ばれるマジョリティーをメインにデザインされています。しかし、もしこの世界に車いすユーザーの方が多かったとしたら、どんな景色になっていたでしょうか。ファッションでは、パンツやスカートという概念がなかったかもしれませんし、ネックレスやイヤリングよりも足にアクセサリーを着けることの方が主流だったかもしれません。こうした「もしもの世界」の流行を形にしていったら、車いすユーザーだけに優しいものではなく、健常者も楽しめる新しい価値が生まれるのではないでしょうか。
世の中には「ユニバーサルデザイン」と言いつつ、全ての人にとってではなく、障害のある人だけに向けて作られているものが多いように思います。しかし、「私たち全員にとって輝くもの」と視点を変えてみると、これまでになかった斬新なアイデアが次々に生まれてくるのです。
ファッションだけでなく、特別支援教育や福祉などありとあらゆるシーンで、障害のある人をお客さま扱いせず、「自分も含めた全ての人が楽しむにはどうすればよいか」という視点を持たなければいけないと感じます。
――今後、多様性の価値観をアップデートする上で何が必要でしょうか。
現在の多様性は、「相手のために」という考え方で展開されてしまっています。「受け入れる」の発想だから、「どうして受け入れなければいけないのか」という対局の発想が生まれてしまいます。
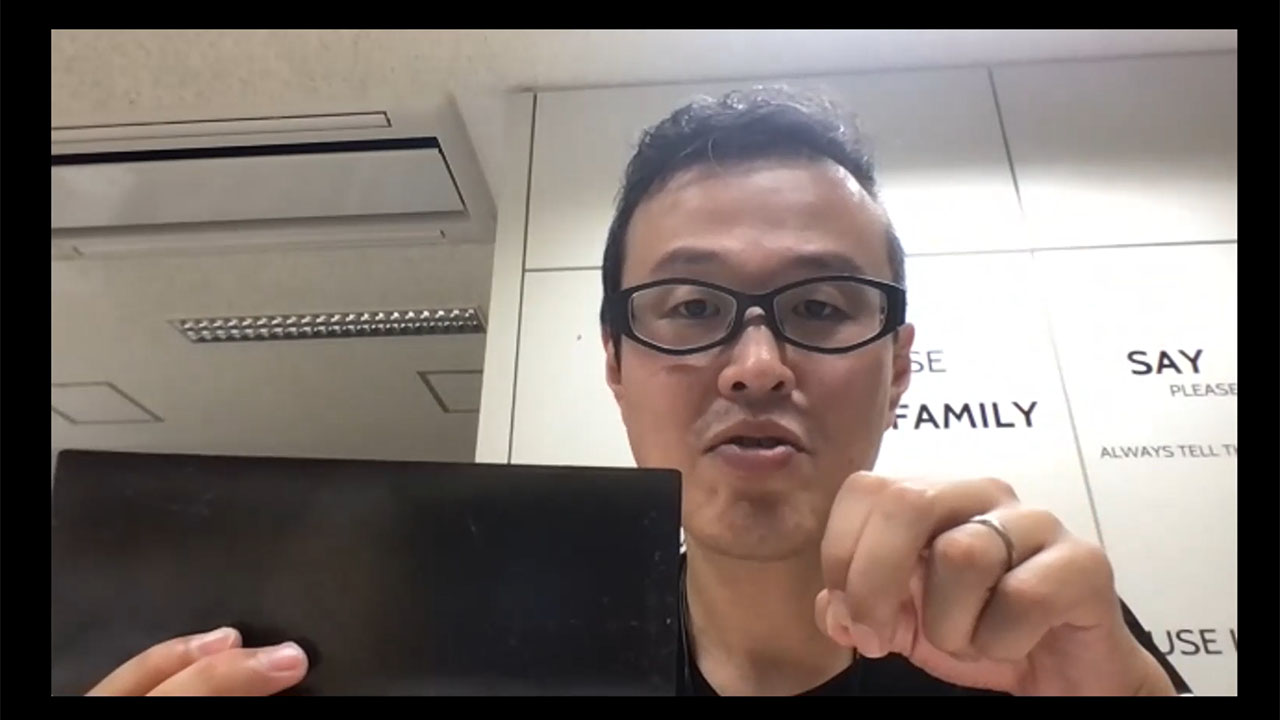
今後、障害者を受け入れる社会をつくったとしても、マジョリティーの側が「私たちが我慢しなければならない」と思い込んだままでは、何も解決しません。そんな状況を打破する上で、私たちが開発したボトモールの概念は一つのヒントになると思います。
障害のある方の立場に立ってデザインを開発するのだけれど、結果としてマジョリティーの側にも魅力が生まれる。今までバラバラにあったおのおのの多様な価値観をクロスさせて、新たな価値観を生み出すということです。それこそが多様性がアップデートした姿であり、これからの社会や教育に必要な観点ではないでしょうか。
――ファッション分野では、学生の皆さんや高校生とも一緒に活動されていると聞きました。
JPFAと兵庫教育大学小川研究室の共同プロジェクトとして「ミライの制服プロジェクト」を立ち上げ、誰もがストレスなく着られるおしゃれな制服を開発しています。プロジェクトには全国の高校生、大学生、大学院生約40人に参加してもらっています。
例えば、「感覚過敏だから刺激のない生地の服しか着られない」「手にまひがあるから、既存の制服では着脱しづらい」など、身体障害やジェンダーなどあらゆる理由で既存の制服を着ることが苦痛だったり、着られなかったりしている中高生が、全国にはたくさんいます。「私服でもいいのでは」という指摘もありますが、中高生に聞き取り調査をしてみると、制服に憧れがあり、「制服を着たい」と回答する生徒が予想外に多かったのです。この声を無視したくありませんでした。
現時点で、2種類の制服をリリースしています。どちらも障害の有無や性別に関係なく楽しめるデザインです。
機能的には、感覚過敏を考慮して、首回りを広く開けて肌に当たる部分を極力減らし、首元にはタグや縫い目を使用していません。加えて、着脱しやすいようにサイドにジッパーを取り入れました。また、こちらにもボトモールのデザインを採用しており、性別を問わず着用できます。座るとプリーツの紺色が現れ、常に座っている車いすユーザーにとってもスタイリッシュなデザインを実現しています。
われわれは、「選ばない」という選択肢を作りたいと考えています。例えば、男性の制服にスカートという選択肢があったとすれば「選ばない」ことを選択できます。しかし現状では選択肢がないので、「選べない」のです。新たな選択肢を生み出すことで、「選べない」を「選ばない」に変えたいと思っています。
――プロジェクトに関わる学生には、どんな変容がありましたか。
何より自分の頭で物事をしっかりと考える、思考が出来るようになりました。
教員にも言えることですが、学校現場では考える余裕や時間がどんどん失われて、大人も子どもも思考力が不足気味です。さらに言えば、思考するスキルを持てずに成長してしまっているようにさえ思えます。
そこで、私は学生に具体的なテーマを与えないようにしました。全て学生に任せたのです。最初は多くの学生が情報を探すスキルを持ち合わせていないので、何から始めれば良いのか分からずに困ります。そんな中でもあらゆる人の話を聞いて、さまざまな可能性や価値観から物事を捉え、主体的に方向性を定めていきます。このように,ものづくりは正解のない問いに挑む作業の連続です。そうした活動の中で思考力が鍛えられたのだと思います。
ただし思考力を鍛えるためには、どうしてもストレスを伴います。そのため、「ポジティブな環境」を準備することこそが重要であると考えています。ですから講義でもゼミでも、学生がポジティブになれる環境を何より大切にしています。
【プロフィール】
小川修史(おがわ・ひさし) 兵庫教育大学大学院学校教育研究科・准教授,博士(工学)、専門は教育工学と特別支援教育。2019年12月に(一社)日本障がい者ファッション協会(JPFA)副代表に就任、21年3月よりミライの制服プロジェクト・代表。現在に至る。