「さる先生」の異名を取り、ツイッター上で3万6000人ものフォロワーを持つ京都府八幡市立有都小学校の坂本良晶教諭。大手飲食チェーンの店長として全国1位の売上を記録した経験を基に、2019年に発刊した著書『さる先生の「全部やろうはバカやろう」』は、2万部を超えるベストセラーとなり注目を集めた。現在は、ICTを活用した授業・単元デザインにまい進する坂本教諭の授業を取材した後、ICTの活用と今後の展望について話を聞いた。(全3回)
7月4日の5時間目、坂本教諭が担任する4年1組では、テレビ会議システムを活用した交流授業が行われた。交流先は、オーストラリアとシンガポールにある日本人学校。教室前方の大型スクリーンに海外校の様子が映し出されると、子どもたちからは「映った!」「つながった!」と歓声が上がった。

交流授業のテーマは「世界子どもゴミフォーラム」。子どもたちが自分たちの住む街のごみ処理方法とその課題について、調べたことを発表するというものだ。坂本教諭のクラスの子どもたちは、iPadの「Key note」で作成したスライドを使いながら、流ちょうにプレゼンを進めていく。チャット欄には、海外校の子どもたちから「分かりやすい!」「4年生とは思えない!」などのコメントが続々と送られてくる。
3校それぞれの発表が終わり、交流授業は無事に終了。坂本教諭は3カ国の教室の子どもたちに向けて「今日学んだことはそれで終わりにせず、行動に移すことが大事だからね。一人一人、今日からどんなことに取り組むかを書いてみよう」と呼び掛けた。すると4年1組の子どもたちは端末内のアプリ「Padlet」を起動し、写真とテキストを組み合わせながらスライドを作り上げていった。タイピング入力も4年生とは思えないほど速い。
しばらくすると、子どもたちが次々と「先生、できたよ~」と坂本教諭の所にやって来て、うれしそうに端末の画面を見せた。ICTの活用が「当たり前」となっていることが、子どもたちの様子から伝わってきた。
――本日は、Zoomを使った交流授業を拝見させていただきました。今回の授業は、どんな経緯で行うことになったのでしょうか。
遠隔地との交流授業を最初に行ったのは、今から6年ほど前です。その時は沖縄県の石垣島の学校とつながって、自分たちが住む街をテーマに、子どもたちが調べたことを発表し合いました。当時はまだZoomがなく、端末の台数も限られていたので苦労しましたが、京都府独自のテレビ会議システムを使うなどして、何とか実施することができました。
子どもたちが自分たちの住む街について調べ発表する活動は、別に交流授業でなくても実施できます。でも、京都のことを京都に住む子に伝えたとしても、子どもたちのモチベーションは高まりません。今日のように、知らない国や地域の子ども同士で伝え合うからこそスペシャルな相手意識と目的意識が働き、子どもたちの学習意欲を引き出すことができると考えます。
――異なる国や地域の子どもとの交流は、多様性について知ることにもつながります。
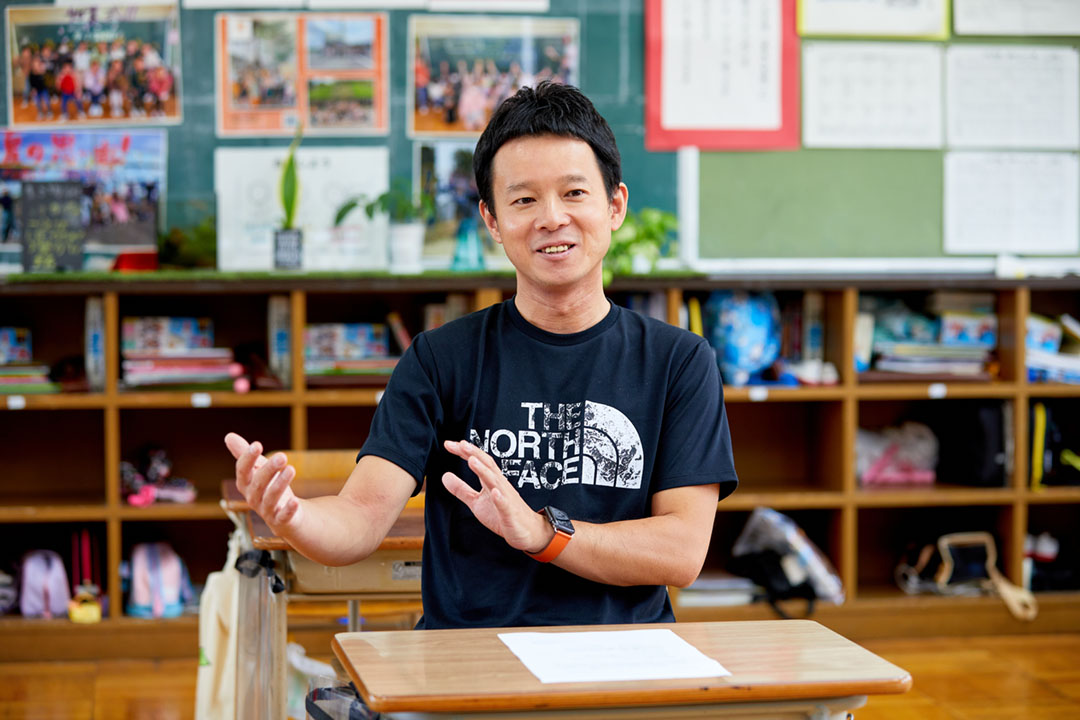
そうですね。今後は、今日のような授業を全国各地の学校とできたらいいなと考えています。例えば、本校の児童が地元の石清水八幡宮について調べ、札幌の児童が時計台について調べ、それぞれ発表し合う。そんな学習活動を全国に広げれば、子どもたちの学びはより実感の伴ったものになると思います。
一方で、こうした実践を広げるには、まずは教員同士が異なる国や地域の先生方とつながりを持たねばならず、そのためのネットワークづくりが必要です。そうした観点から私は昨年度、Teamsを使って全国で同じ学年を担任する先生方同士が情報交換をできる場をつくり、交流していました。
――全国の教員がつながれば、いろいろな知恵の共有もできそうですね。
全国各地の学校には、優れた授業実践がたくさんあります。でも、これらが共有されていないことから、至る所で「車輪の再発明」(すでに世の中に存在する技術や解決法を多大な労力をかけて一から発明すること)が行われています。これは働き方という点で大きなマイナスを生んでいます。
私自身、現在は「Canva」や「Kahoot!」などのアプリを使った授業も行っており、こうした実践を共有し合うことで、効果的な授業が手軽に再現できるようになったらいいなと考えました。そこでフェイスブックで遠隔地交流授業マッチングルームというコミュニティーを立ち上げました。ここで遠隔交流授業を実践したい指導者同士がつながったり、アイデアを交換し合ったりすることを目指しています。
――今日の授業では、子どもたちのタイピングの速さにも驚きました。
4月の時点ではタイピングが苦手な子どもがほとんどでした。でも、3カ月もあれば、あのくらいの速さで打てるようになるんです。個人的には、タイピングは2年生から始めるべきだと考えています。タイピングゲームを使って感覚的に学んでおけば、3年生で行うローマ字の学習もスムーズです。低学年でタイピングを習得できれば、早い段階から子どもたちのアウトプットの量を増やすこともできます。また、手で書くのが苦手な子に、異なるアウトプットの仕方を保障することにもつながります。
もちろん、手書きも大事なので、タイピングと並行する形でさせています。また、漢字が書けなくならないよう、「けテぶれ(計画・テスト・分析・練習)学習法」を取り入れるなどして、漢字学習にも力を入れています。
――日本の学校はコロナ禍で大きく変わりました。その間、どんなふうに過ごされていたのでしょうか。
2020年3月に全国一斉休校となった時、私は前任校にいました。そして、全国の他の学校と同様、やはりプリントを大量に印刷し、クラスの子どもたちに配って回りました。当時は1人1台端末もなかったですし、仕方がなかった面はありますが、個人的にはとても屈辱的で、敗北感を覚えました。
――1人1台端末が整備されたのは、その約1年後でした。
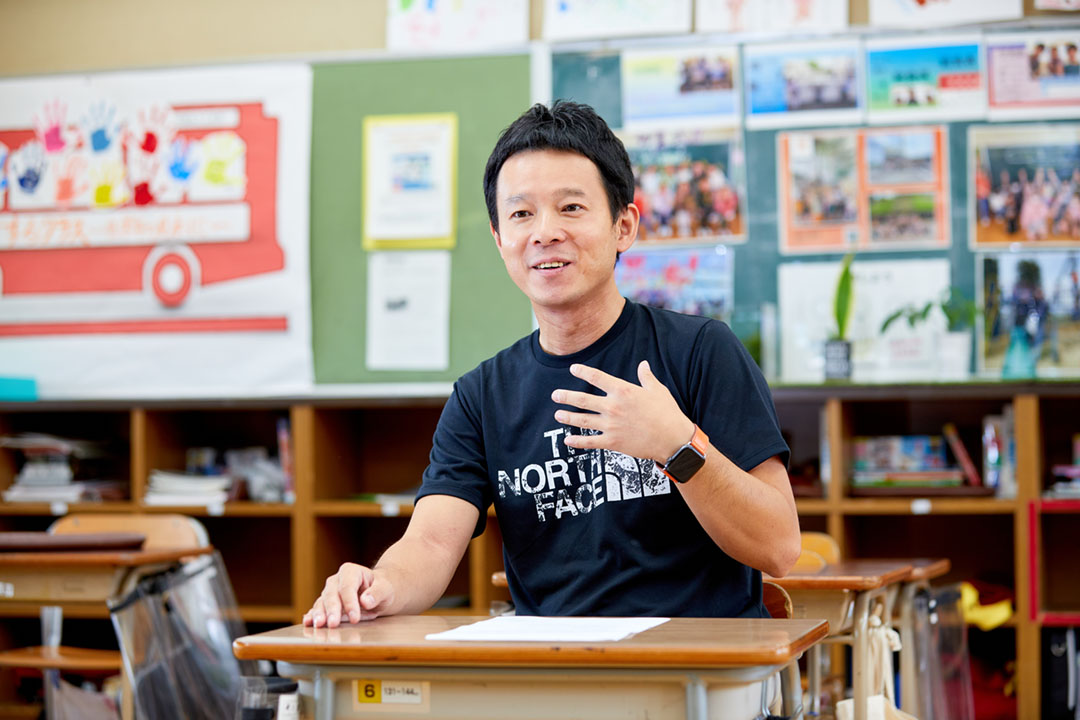
今思えば、コロナ禍はプラスに働いた部分も大いにあります。「GIGAスクール構想」の前倒しで1人1台端末が整備され、今年1~2月はオミクロン株の感染拡大を受けて多くの学校がハイブリッド授業を余儀なくされましたが、そこで自分自身のICTを活用する考え方や授業技術も磨かれたと今は感じています。
とはいえ、現状ではまだ学校間・教員間の格差があります。本校はICT活用の研究推進校のため、年1回は子どもたちが「Key note」などを使ってプレゼンをする機会がありますが、そうした機会がない学校では、端末を全く使わない状況も生まれかねません。だからこそ、全国の教員同士で、情報共有を図っていくことが大事だと考えています。
【プロフィール】
坂本良晶(さかもと・よしあき) 1983年生まれ。大学卒業後、大手飲食店チェーンに勤務し、兼任店長として全国1位の売上を記録。教員を目指し退職後、通信大学で教員免許を取得。翌年、教員採用試験に合格。2017年、子どもを伸ばしつつ、教員の働く時間を減らそうという「教育の生産性改革」に関する発信をツイッターで始める。『さる先生の「全部やろうはバカやろう」』(学陽書房)がベストセラーに。