PBL型の学習活動を通じて生徒たちの学力や非認知能力を高めるなど、全国的にも注目を集める大阪市立新巽中学校。2020年度からは教育活動にeスポーツを取り入れるなど、新たな試みもスタートさせている。「VUCAの時代」を生きる子どもたちに、どんな力を育もうとしているのか。教務主任・研究主任として同校をけん引してきた山本昌平教諭に、インタビューの最終回はeスポーツ導入の経緯やICT活用の意義などを聞いた。(全3回)
――教育活動にeスポーツを取り入れているとお聞きしました。詳しい経緯を教えてください。
コロナ禍になった2020年度、大阪市生野区が小中学生を対象にしたeスポーツ大会を開くことになりました。当時の山口照美区長が、自由に外出できない状況が続く中で、ゲームを通じた学びの可能性に着目されたのです。山口区長から直々に「教員からもゲームの教育的意義を語ってほしい」と打診され、大会の企画に参加することになりました。
私自身も、ゲームを通じて得られる学びは決して少なくないと考えています。例えば、大ヒットゲームの「あつまれどうぶつの森」では、株式投資や住宅ローン、利息などの仕組みを楽しみながら学ぶことができます。大会の共催者であるロート製薬の未来社会デザイン室室長・荒木健史さんとも意気投合し、子どもたちが多くの学びを得られる大会の在り方について話し合いを重ねました。
そうして20年10月に開催したのが「脱獄ごっこ×生野っこeスポーツチャレンジ!!」です。5人チームになって相手の陣地を崩していくシンプルなゲームですが、攻める人と守る人の役割分担が重要で、チームワークが求められます。大会当日は、区内外の小中学生が30~40人ほど参加し、大いに盛り上がりました。
――教育的意義も感じられたのでしょうか。

仲間と連携・協働しながら一つのミッションを遂行する経験を通じ、子どもたちは多くのことを学んだように思います。もちろん、こうした力は通常のスポーツでも育まれますが、eスポーツの場合は体格や体力、性別などに関係なく、皆が同じステージで対等に楽しむことができます。学校には体育祭で輝く子もいれば、文化祭で輝く子もいます。それと同様に、eスポーツ大会でこそ輝ける子もいるのです。
――区の大会に参加して、eスポーツの教育的意義を感じたことで、学校でも実施しようと考えられたのですね。反対はなかったのでしょうか。
「教育活動にゲーム」と聞いて、驚いた人もいたと思います。ゲームに限らず、教育活動におけるテクノロジーの活用については、使い過ぎや不適切使用を懸念して、使用に消極的な学校が少なくありません。
私自身は、テクノロジーを言葉と同列に捉えています。言葉も間違った使い方をすれば人を傷つけますが、私たちはそれ自体を奪ったりしません。より良い人生を送れるようにするために、言葉の正しい使い方を教えます。テクノロジーもそれと同じで、ゲーム依存の子が出たら、ゲームとの向き合い方をその子と一緒に考えればいいのです。
ゲームにはネガティブな印象がありますが、「物が悪い」という考え方はなくしていくべきです。また、「悪い」と思っていたものが「良い」に変わる、つまり常識や思い込みを書き換えられる経験をすれば、それは多様性を受け入れることにもつながります。教員にはそうしたことも伝えながら、理解を促しました。
――具体的に、eスポーツを用いてどのような学習活動をされたのでしょうか。

昨年2月に、2年生が中心となって「勝手に!eスポーツ大会」というイベントを開催しました。区の大会と同じ脱獄ゲームをして、その後には「ゲームは悪なのか」「ゲームは学びの道具になるのか」「人がワクワクドキドキする仕組みってどんなものなのか」をテーマに、実行委員の生徒たちがプレゼンテーションを行いました。
イベントは企画段階から生徒に委ねました。生徒たちは大会を運営することの大変さ、役割分担しながらプロジェクトを進めることの難しさを感じていたようです。この時のコアメンバーは翌年もeスポーツ大会の企画・運営を担いましたが、その成長には目を見張らされるものがありました。彼らは卒業後も生野区の「いくの多文化クロッシングフェス2022」の企画・運営に携わるなど、精力的に活動しています。
――eスポーツだからこそ、子どもたちは主体的に動けたのかもしれませんね。
今の子どもたちにとって、ゲームはごく身近で当たり前のコミュニケーションツールです。一方の大人は、ゲームにネガティブな印象を持っていて、「ゲームをする時間が長い子ほど学力が低い」といった悪い情報ばかりにとらわれ、教育的な意義に目を向けることができていません。もちろん「依存」してはいけませんが、「夢中」になるからこそ得られるものもあるのです。
――ゲームも含め、テクノロジーの教育への活用については、どう考えていますか。
子どもの中には、活字を読むのが苦手な子もいれば、話を聞くのが苦手な子もいます。そうした子どもに、異なるインプットの手段を保障する意味でも、ICTは有効です。ドリルアプリなどで学力の定着を図ることもできます。教員にとっては、採点業務や教材作成などが効率化されます。そう考えても、使わない手はありません。
――新巽中学校でのICTの活用状況はいかがでしょうか。
本校は特別支援学級も含め、全教室にホワイトボードと上方から照射するプロジェクターも配備されています。いつでもどこでもICTを使える環境が整えられているため、ベテラン、若手を問わずどの教員も積極的にICTを使っていて、例えば70歳の先生が「Good Note」というアプリを使ってオンライン授業をするなどしています。
――環境が整っていても、活用が進んでいない学校もあります。この点については、どう思われますか。
教育とは、なりたい自分やそのために付けさせたい力を明確にし、そこから逆算していく営みです。それはICTがあろうがなかろうが関係ありません。一方、新しいテクノロジーが生まれ続けることも変わらない事実です。だからこそ試行錯誤する時があったとしても、そうしたツールに温もりを込めながら、自分たちの目的を達成していくことが、私たち教育者の役割なのだと思います。
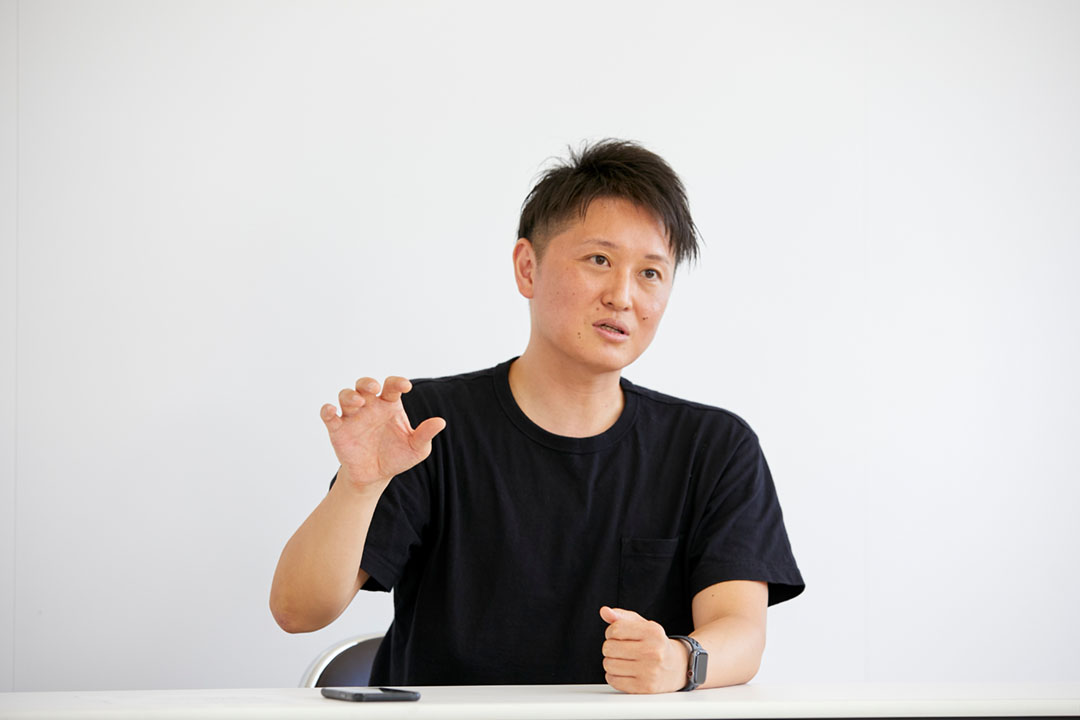
その意味でも、「子どもたちにどんな力を付けたいか」だけでなく、「どんな学校をつくりたいか」も明確にしていく必要があります。現状、学校教育目標が形骸化している学校も多く、それが共有されない限り、教員間の足並みもそろいません。
当事者意識を持って関わる仕組みを整えなければ人は動きませんし、環境だけを整えても人は動きません。価値観を共有する対話の時間も必要です。この2つの両輪がかみ合いつつあるのが今の本校であり、教育の在り方を考える上で一つの希望になってほしいという思いを持って、みんなで汗をかきながら進んでいます。生徒にとっても教師にとっても格差を生まない仕組みをつくり、問題解決を諦めない。全ての学校は変えられる力を持っていると私は信じています。
【プロフィール】
山本昌平(やまもと・しょうへい) 私立学校に常勤として2年勤務した後、大阪市立中学校で12年勤務。経歴の半分は、教務主任と研究主任を兼任。学校が今までの慣例や当たり前を繰り返すことに限界を感じて学校の仕組みから再編、企業と共に社会課題を解決するプロジェクトベースの学習環境にシフト。現在はロート製薬・区役所などと連携し、eスポーツ×教育の可能性をテーマに教育現場にゲームを導入。学校現場でeスポーツ大会を実施。Google認定トレーナー、GEG Ikunoリーダー、NHK for School「マスと!」制作委員。