現代アートを難しくしている要因の一つは、その作品の価値を「誰が」決めるのかという問題です。なぜこんな作品が評価されるのか全く理解できないと感じる体験は、現代アートの鑑賞においておそらく誰もが一度はしたことがあると思います。無数にある現代アートの作品の全てが、優れたコンセプトや強いインパクトを持ったものでもありません。そして、そうした条件が備わっている作品であっても、それが自分に響くかどうかはまた別の問題です。ある人に強く響いても他の人には全く価値が理解できない作品は、山のようにあるでしょう。だから全ての作品に共感する必要はないし、作品の価値を決めるのは作者ではなく、本来は鑑賞者に委ねられています。
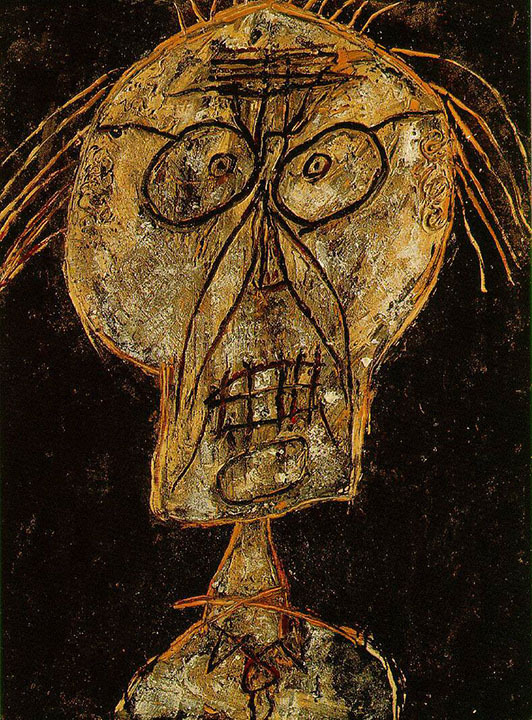
一方で、私たちは誰かが評価したものを受け入れてしまいがちです。有名な作家の作品やメディアに取り上げられた作品、受賞した作品、著名人や評論家が評価した作品、大勢の人が評価した作品、高い値段がついた作品などに価値を感じてしまいます。自分の頭と身体と心でその価値を確かめるのではなく、すでに与えられた情報によって価値が左右される場合も多いでしょう。正解のない現代アートにおいてそうした態度で鑑賞すると、作品の価値や真のメッセージが曇ってしまうことがあります。そこに価値を巡る落とし穴が潜んでいるのです。
もう一つ、作品の価値を巡る問題を難しくしているのは、それが「いつ」発表されたものなのかということです。もちろん、時代を問わずに力を持つ作品もありますが、それまでの常識的な見方に革命を起こすことを目指す現代アートの表現では、その時代においてこそ価値や意味があったという場合もあります。今では当たり前になっているような表現は、後の時代で見た時にその価値が分かりにくくなります。そういう作品は情報を補いながら鑑賞するほかないのですが、響き方やインパクトは発表当時とは異なるものになるため、価値が理解しにくくなるのは否めないでしょう。
現代アートが面白いのは傑作か駄作かを分ける基準が紙一重で、人によって感じる価値が全く異なるところにあります。機能や有用性など共通の基準に基づいて評価しがちな今の社会の中で、評価基準が一律ではなく、序列もつけがたく、人によって価値が異なるものと認められるのが、現代アートの特徴だとも言えます。
たった一人でも、その作品によって救いが得られたり、人生が変わってしまう可能性が担保されていたりするのが現代アートなのです。現代アートの世界こそ多様性が必要で、必ずしも大勢が評価するものだけに価値が認められるわけではないのです。自分だけが評価できる作品を見つけるレッスンをする上でも、現代アートは最適と言えます。