日本の学校の長所を挙げつつ、今後乗り越えるべき課題も指摘する西村カリンさん。フランスと日本の両方の社会を見てきたジャーナリストとして、2人の息子を育てる母親として、日本の学校教育をどのように見ているのか。インタビューの最終回では、教員不足やデジタル化など、最新の教育トピックについての問題意識を聞いた。(全3回)
――日本は今、教職の人気が下がり、教員不足が問題になっていますが、フランスでも同様のことが起きているそうですね。
その通りで、フランスも日本と同じような状況にあります。日本の場合は第一に、先生の負担が重過ぎます。加えて給料もあまり高くないし、実質的に残業代も出ません。本当にあり得ない話です。教職を魅力ある職業にしたいなら、ちゃんと残業代を出すべきです。加えて日本の教員にはストライキなどの権利もありません。この点は国連も問題だと指摘しています。
私の息子が通う学校の先生は、いつも笑顔で接してくれています。他の学校の先生もそうです。そのため、多くの保護者は「先生方は問題なく元気に働いている」と思っています。でも、実際にはそうではないかもしれませんし、私はいつも心配をしています。だから、先生との三者面談では、自分の子どものこと以上に先生のことが心配で、先生の話を聞きたいと思っています。
日本では、先生が自分のことを保護者に話す機会がありません。その結果、保護者は先生の状況をよく知らないまま、クレームを付けたりしています。フランスの先生は、保護者に向かっても堂々と意見を言いますし、デモもストライキもします。だから、先生が不満を抱えていることはみんな知っています。

――それでも、職業としての人気がないのですね。なぜなのでしょうか。
第一に給料が低いからです。加えて、保護者からクレームを言われたり、子どもから暴言を受けたりすることも少なくありません。そうした状況がある中で、なりたいと思う人が減っています。
――日本では今、不登校の子どもが増え続けています。この状況をどう見ていますか。
不登校の理由は人それぞれで、いろいろな事情があると思います。私は、学校の問題というより、家庭を含めた社会全体の問題ではないかと見ています。例えば、子どもの精神的な状況を理解して支援する専門家が足りません。
これは大人についても言えることで、うつ病への対応を投薬で解決しようとする傾向が強く、もっとカウンセリングなどで「話す」機会を設けるべきだと思います。子どもの場合、学校に合わないから不登校になるわけで、なぜ学校と合わないのか、専門家がしっかりと本人から聞き取って対応すべきです。専門的に状況を把握・分析して、家庭も含めて支援できる人をもっと増やす必要があります。
日本の病院での診察やカウンセリングは本当に短くて、3分程度で終わることもあります。フランスは雑談も含めて本当にいろいろな話をします。そうした中で、患者が突然「実は…」と本音を語り出すこともあります。日本の場合、本音を語れないまま、薬だけもらって帰るということも多い。きっと学校も同じような状況があるのではないでしょうか。

――日本でもスクールカウンセラーの配置は進んでいますが、週に数時間滞在するだけといった学校が大半です。
時間の長さが鍵だと思います。子どもたちの多くは、最初から本音を語ろうとはしません。だからこそ、長く滞在して、じっくりと話をする時間を確保することが大事だと思います。日本の場合、担任の先生がそうしたことまで対応していますが、カウンセリングには専門性も必要ですし、多忙な先生がその役目を担うには無理があります。
――日本の学校の先生は、多くの役割を担い過ぎているのかもしれませんね。
以前、うちの子が下校中に、不審者に声を掛けられたことがありました。大したことではないとは思ったのですが、一応、夫にその話をしたところ、夫が「念のために」ということで学校に報告を入れました。すると翌日、先生が警察と一緒にうちへ来たのです。私は「ああ、先生の仕事を増やしてしまった。申し訳ない…」と後悔しました。こうした話も含め、日本の先生は多くの役割を担い過ぎていると思います。
――著書の中で、フランスに比べて日本は、GDPに占める教育費の割合が低いと指摘していました。やはり、もっと専門家を入れるなどして、教育に予算を回すべきなのでしょうか。
確かに教育費の割合は低いですが、お金の使い方を間違っている側面もあると思います。例えばフランスの場合は、9月に新学期が始まるタイミングで、子ども1人当たり数百ユーロが国から家庭に支給されます。支給額は子どもの年齢とともに上がります。高校も大学も授業料は無料です。日本の場合、幼少期は手厚いのに、学年が上がるにつれて支給額が減っていきます。一方で、成長とともに保護者の負担は増えていく。こうした状況も改善していくべきだと思います。
――日本の学校でもいろいろな改革が進んでいて、一番大きいのは「GIGAスクール構想」で1人1台ずつデジタル端末が配備されたことです。このことをどう見ていますか。
うちの子も2人ともiPadを所持しています。メリットの一つは、オンラインで授業に参加できるようになったことです。少し熱があって、学校に行くのは控えるけれど比較的元気な場合、端末を使って授業に参加できます。うちの子も何度か、そうやって授業に参加しました。
下の子は1年生ですが、週に2~3回ほど端末を活用しているようです。何か調べ物をするときなど、必要なときだけ使うというスタイルで、良い使い方だなと思います。
――あまりに使い過ぎるのは問題だということでしょうか。
そうですね。全ての授業をデジタル化することには賛成できません。実際、そうした国があるのですが、うまくいかずに元に戻しました。やはり紙で読むのと端末で読むのとでは脳の使い方が違って、結果的に子どもの読む能力が顕著に低下したのです。デジタル端末で読む習慣がつくと、集中力を持続する能力が低下することも、最近の研究で明らかにされています。もちろん、デジタル端末を使うメリットもたくさんありますが、使い方や使う頻度には注意をする必要があります。
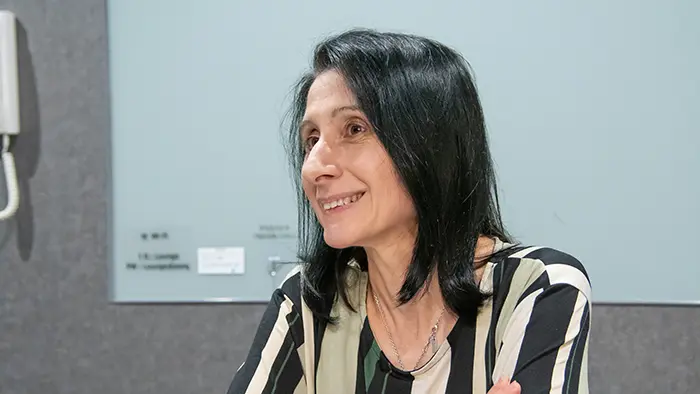
――日本の公立学校への提言はありますか。
先にも述べたように、やはり子どもを個人として認め、自らの意見を言える場をもっと設けるべきです。何事にも素直に従う労働者を育てるのではなく、自分の頭を使って考え、行動できる人間を育てていく必要があります。今、日本の学校では「多様性の尊重」が叫ばれていますが、実際には校則で厳しく縛るなど、多様性を認めていない学校も少なくありません。
日本の場合、校則だけでなく、大人社会の中にも意味不明なルールがたくさんあります。根拠の分からないルールに直面したとき、「以前からそうだから」で終わらせるのではなく、ルールの意味やロジックをしっかりと考え、必要に応じて見直していくことが大事です。学校でもそうしたことを子どもたちに経験させる必要があると思います。
【プロフィール】
西村カリン(にしむら・かりん) ラジオ・フランスおよび日刊リベラシオン紙の特派員。1970年生まれ。パリ第8大学を経てラジオ局やテレビ局にて勤務し、97年に来日。2000年からフリージャーナリストとして活動。04年より20年までAFP通信東京特派員。08年「Les Japonais 日本人」を出版。09年、同著書が渋沢・クローデル賞受賞。23年「Japon, la face cachée de la perfection(日本、完璧さの隠れた裏側)」、24年には初の小説「L'affaire Midori(みどり事件)」を出版。国家功労勲章シュヴァリエを受章。日本での著書に『フランス人ママ記者、東京で子育てする』『不便でも気にしないフランス人、便利なのに不安な日本人』(ともに大和書房)、『フランス語っぽい日々』(白水社)などがある。