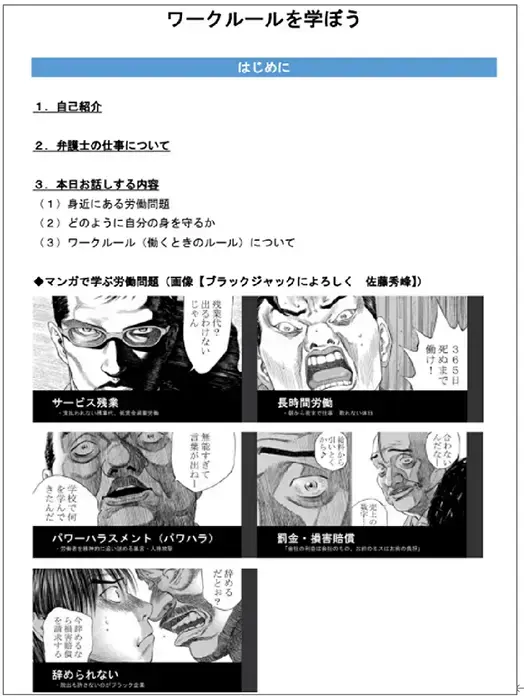ワークルール教育が生かされるのは、子どもたちが社会に出てからだけではない。ワークルール教育は、子どもたちの学校在学中から、すぐに役立つ教育なのだ。
現在、大学生はもちろん、多くの高校生もアルバイトをしており、「ブラックバイト」の被害に遭っている。「ブラックバイト」とは、奨学金問題に取り組む大内裕和教授が名付けた造語で、学生であることを尊重しないアルバイトのことを言う。親の貧困が進む中で仕送りも減少し、生活費を稼ぐために大学生が働く実態、非正規雇用の基幹化が進み、学生バイトが簡単に休める補助的業務ではなくなっていることなどを背景に、学業に支障が出ても休めず、退職したくても辞められないようなトラブルが典型だ。
全国大学生活協同組合連合会実施の調査(2025年2月公表)によれば、2024年度における自宅外の大学生への仕送りは平均月7万2350円にとどまり、月平均収入は13万2140円で、その28.4%はアルバイトによるものだ。多くの大学生にとって、アルバイトは遊ぶためではなく、生活上不可欠な収入源である。だからこそ、アルバイト先のトラブルを「嫌なら辞めればよい」と片付けられない。そもそも、トラブルの典型は退職妨害(辞めさせてもらえない、辞めるなら賠償金払えなどと脅される)であり、「嫌なら退職すればよい」ではアドバイスにならず、トラブルに向き合い解決することを迫られている。バイトという低い身分に加え、年齢・社会経験の乏しさから、ハラスメント被害に遭うことも多い。
就活の場面でも、求人情報の見方や労働条件に注目した企業調査の方法などのワークルール教育が生かされるが、きちんと教わった機会がある人は少数だろう。インターンシップ(教育実習もその一例)を経験する大学生も多いが、そこでのハラスメント被害も多く、卒業前の新人研修でブラック研修が行われるというトラブルもある。さらには「闇バイト」など犯罪行為に巻き込まれるケースにおいても、ワークルール教育には予防効果がある。
在学中からワークルール教育を生かす機会があるのは高校生も同じだ。株式会社マイナビの高校生対象の調査(25年)によると、アルバイトをしている高校生の割合は27.4%で、アルバイトをしている高校生のうち小遣いをもらっていない割合は54.9%に及ぶ。小遣いがもらえず、高校生活で必要な友達との交際費を捻出するためにアルバイトが不可欠な子どもも少なくない。
このように、ワークルール教育は、子どもたちの在学中から役立ち、即効性も期待できる。