「シティズンシップ教育」と聞くと、学校教育の中で「何を」「どのように」、そして「どの場面」で扱う教育なのか、と疑問に思う教員も多いのではないだろうか。まずは、学校の日常を思い起こしてみてほしい。
学級会でより良い学校生活に向けてルールを話し合うとき、総合学習で自分のまちを調べて、より良いまちづくりに向けた提案を考えるとき、英語の授業でノーベル平和賞を受賞したマララ・ユスフザイさんのスピーチを読み、世界がより良くなる活動について考えるとき――。こうした活動は全て、シティズンシップ教育に通じる活動と捉えることができるのではないか。つまり、シティズンシップ教育は全ての教員が教科や分掌を超えて関わる教育であって、決して一部の教員(特に社会科など)だけが推進する教育ではない、と捉えてはどうだろう。
そう考えてみると、学校の中にはこれまでも多様な形で、教科の枠を超えてシティズンシップ教育が行われてきたはずだ。
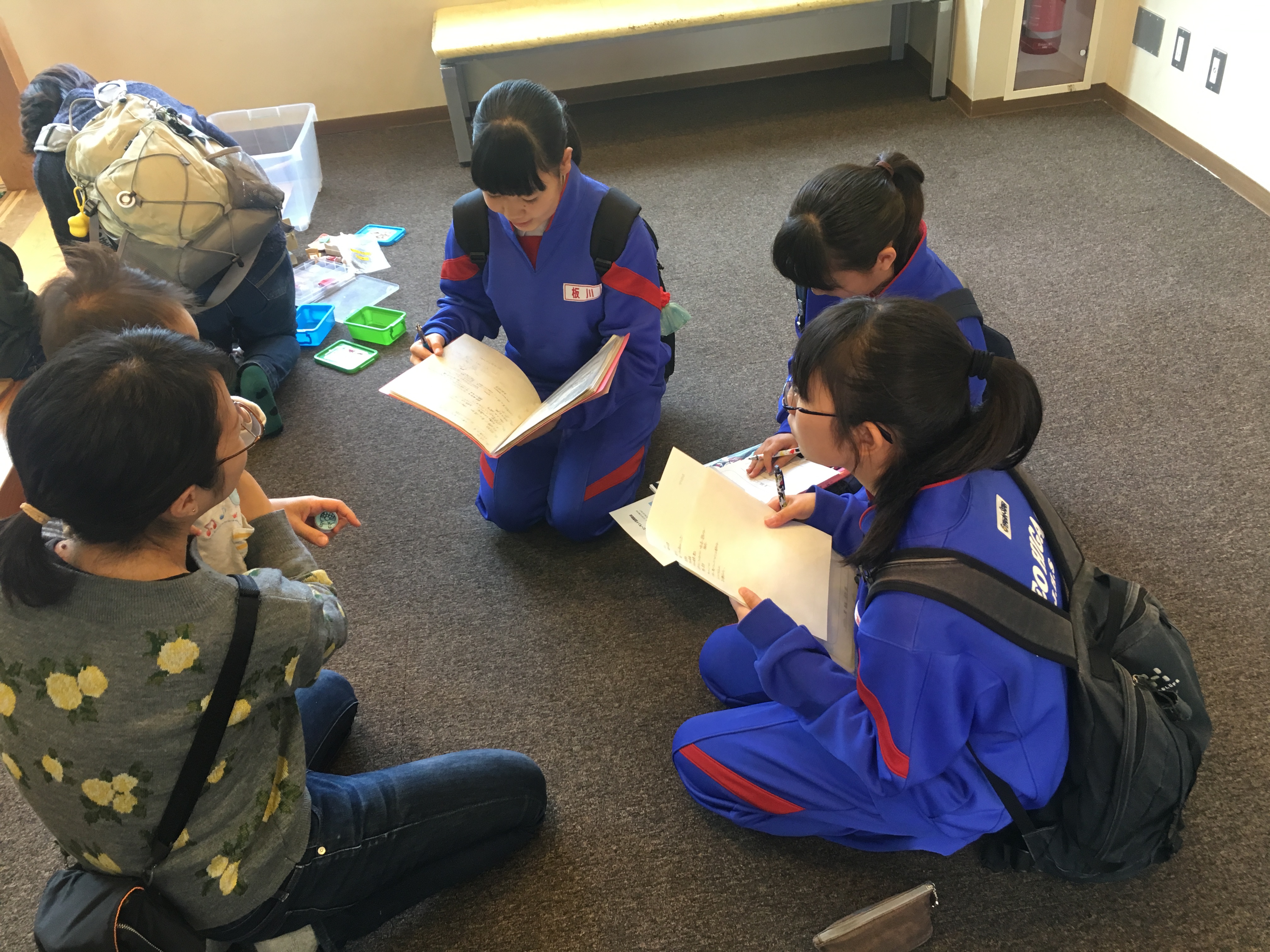
学校の中で繰り広げられてきたその教育は、どのような「シティズン」(市民)を育む実践であっただろうか。そしてそれらの学びは、これから児童生徒が生きていく「社会」とどのように関わってきたのだろうか。学校の中だけに「閉じた」学びではなく、今後は社会とつながり、社会に開かれた学びをつくることが求められている。そのためには、目指す社会像や生徒像を学校と社会が共有し、両者が協働した学びの創造が必要になるだろう。
私たち教員は、学校教育の場を通して社会と連携しながら、児童生徒を一人の「市民」として育む教育を推進していくことが求められている。
2017年に告示された中学校学習指導要領の前文には、「~多様な人々と協働しながら様々な社会的変化を乗り越え、豊かな人生を切り拓(ひら)き、持続可能な社会の創り手となることができるようにすることが求められる」と明記されている。教育を通して「持続可能な社会の創り手」としてのシティズンを、学校現場でどのように育むことができるのだろうか。
まずは私たち教員が、持続可能な社会の創り手の育成に向けて必要な学びとは何かを問い直す必要があるだろう。
そして、学校全体としてどのようなシティズンを育みたいのか、目指す児童生徒の姿について議論し、社会と共有することから始まるのではないか、と考えている。
松倉紗野香(まつくら・さやか) 埼玉県上尾市立大石中学校教諭(英語科)。認定NPO法人開発教育協会(DEAR)理事。専門は開発教育、国際理解教育など。中学校では総合的な学習の時間におけるグローバルシティズンシップ教育の実践を推進。各地で教員研修やワークショップの講師も務める。