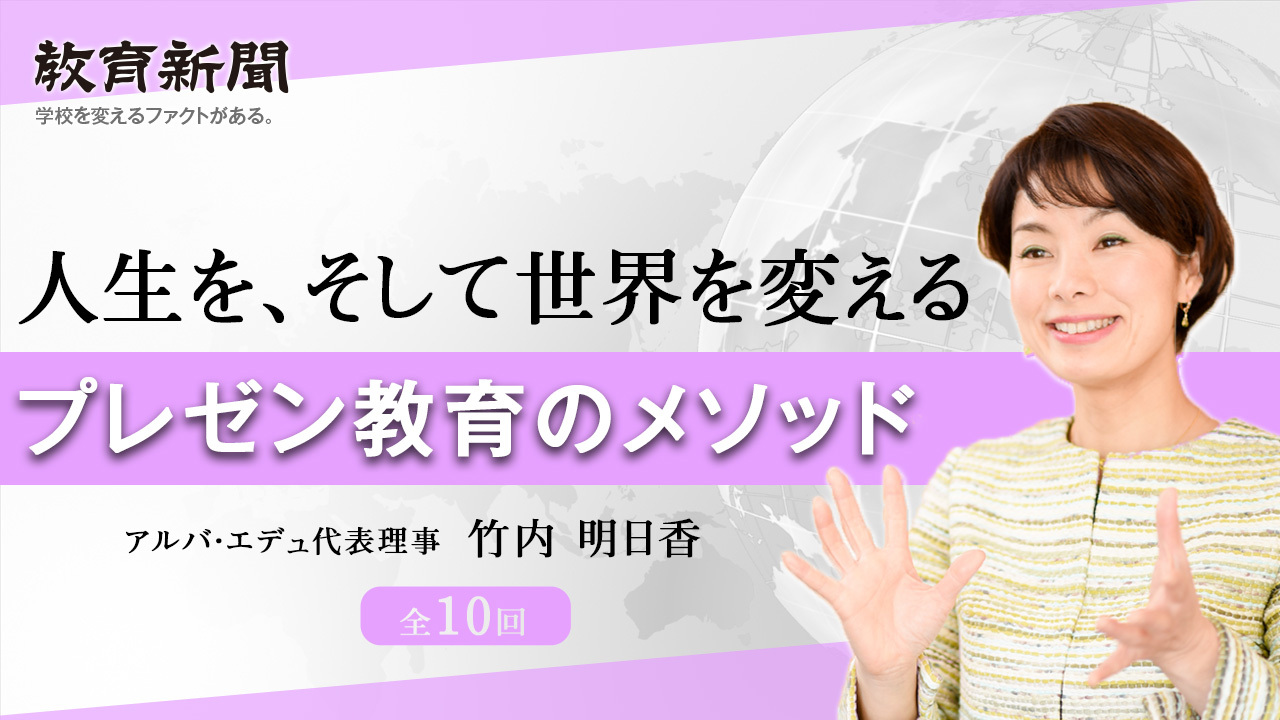
今回は、プレゼンで重視する3つの力の3番目の「見せる力」、プレゼンの最終工程に当たるビジュアル資料についてのお話です。自分の体以外のツールを使って、「イイタイコト」を人に伝える補強の部分です。「プレゼンで重要なのはスライドでは?」との思い込みからスライド作成に長い時間を費やすあまり、「考える力」「伝える力」がおろそかになるケースがあまりにも多いので、私はあえて3番目にしています。
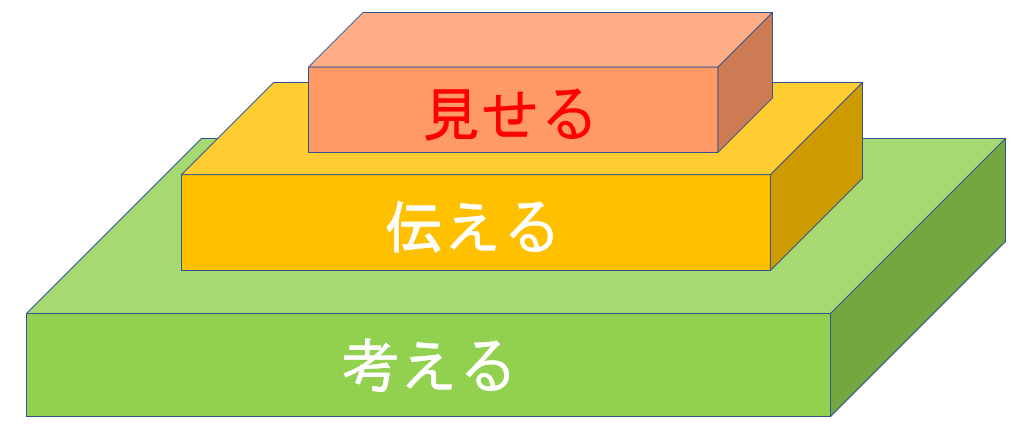
ビジネスの現場では日々当たり前に行われるプレゼンも、その内容はピンきりです。図と文章がレイアウトされた資料をそのまま転記しただけのスライドを投影し、用意した原稿を読み上げるような人もいます。そうしたプレゼンに触れるたびに、学校の授業でよく目にする「新聞づくりとその発表」との共通性を感じます。新聞づくりと表現力を高める学習は切り離した方が良いと私が強く思うゆえんです。
翻って「イイタイコト」を効果的に「見せる力」が宿ると、プレゼンにはオリジナリティーとともに絶大な力が生まれます。例えば、「地球を守ろう」というテーマのプレゼン。環境破壊の現状を示すものとして、何を見せると効果的でしょうか。年々上昇する気温のグラフ、溶けた氷の上でたじろぐシロクマの写真、プロデザイナーが創ったコーンの上で溶けつつある地球アイスの絵、色とフォントを工夫した「暑い」というだけの文字…。私はどれも正解だと思います。正解は一つではないのです。
そもそも新聞業界自らが電子媒体となって、写真や図、絵、時には動画も活用しながらニュースを伝えているこのご時勢、必要なのは情報をいかに短くキャッチーに見せるかの表現力です。YouTubeよりTikTok、FacebookよりTwitter、Instagramを好み、コンテンツを倍速で見る若者が増加する今日、「入り口」で聞き手に関心を持ってもらえること、その俎上(そじょう)に載せることも大事なのです。
長い文章を否定しているのではありません。新聞・雑誌のレイアウトを考える力も大切です。ただ、子どもたちがタブレット端末を手にし、調べた客観事実を「コピペ」する誘惑も大きくなる中で、従来のやり方から進化することも必要だと思います。
プレゼンは、自分の思いを情熱を持って伝える場であり、新しいアイデアを通じて相手の意識変容を促す場です。考えを深め、相手の印象に残る、魂の宿った表現の手法を磨くこと。これが、これからの時代を生きる子どもたちの人生の鍵を握ると言っても過言ではないと思います。