フィンランド語を学び始めて4カ月がたった頃、少しずつではあるがフィンランド語を用いてコミュニケーションをとれるようになってきた。そんなある日、同僚が私に話し掛けてきた。特別支援教育担当のレア‐マリア・シレン(Rea-Maria Siren)先生である。「ヒロキは、日本で理科の先生だったよね? この生物の教科書は私が作ったものなのだけど、よかったらプレゼントするね」と。
その教科書を見たときの第一印象は、書かれている文章がすっきりしている、ということと、私のフィンランド語のレベルでも分かりそうな内容で書かれているな、ということだった。
実はこの教科書は、生物と地理を専門とする3人の先生、それから一般のフィンランド語と合わせて、母語ではなく第二言語としてのフィンランド語を教える先生、さらには特別支援教育の先生の、計5人で構成されるチームによって作成された、特別な支援を要する生徒のための教科書だ。この教科書は全9冊にわたってシリーズ化されている。
ここで少しフィンランドの特別支援教育に触れておきたい。特別支援教育には、General Support(一般的な支援)、Intensified Support(より手厚い支援)、Special Support(特別な支援)という3段階の支援体制があり、子どもたちはそれぞれのニーズに合わせて、どの段階でもサポートを受けられる権利を持っている。
さらには、「支援を必要としない子どもはいない」という考えの下、全ての子どもたちが必要とする支援を受けながら学ぶことができるように、さまざまな工夫がなされている。
日本で「特別支援教育」と聞くと、障害の有無や発達障害がまず初めにイメージされるのではないか。フィンランドでは近年、移民の割合が増えていて、フィンランド語を母語としない生徒や、母語であってもフィンランド語の読み書きに困難を覚える生徒がいる。彼らもまた、特別な支援を要する生徒なのだ。
私が勤めているヘルシンキ国際高校(Helsingin kielilukio)にも、外国にルーツのある生徒がたくさん在籍している。入学後すぐに全新入生を対象に、フィンランド語についての読み、書き、聴き、読解の試験を行い、その結果に基づいて個別支援をどのように行っていくのかを、生徒のニーズと合わせながら決定している。
こういった背景がある中で、この教科書がいったいどのような役割を果たしているのか、そして教科書に込めた思いや意図を探るため、レア-マリア先生ほか4人の先生にインタビューしてみた。

◇◇◇
――新たな教科書を作ろうと思ったきっかけは。
私たちは、特別な支援を必要とする子どもたちや、第二言語としてフィンランド語を学ぶ移民の子どもたちには、簡単な言葉で書かれた独自の教科書が必要であると考えました。今までは高校生を対象とした特別支援教育でも活用できるような、中学生レベルの内容の生物の教科書がありませんでした。そこで、フィンランド国家教育庁からの依頼もあり、私たちで新しい教科書を作ることにしました。
――この教科書の特徴を教えてください。
この教科書シリーズの目的は、カリキュラムの核となる内容を、分かりやすいイラスト、簡単な表現、大きめのフォントサイズで示すとともに、さまざまなレベルの生徒に適した課題を捉え、見つけ出すことです。
その良い例が、テキストの間に挿入された「読解チェック問題」です。その目的は、探究を通して生物学的思考を刺激することです。この教科書のイラストと研究活動は、生徒が自分自身で実験し、自然界の現象を調べることを促すよう、工夫しています。本シリーズの内容は削減されたわけではなく、教科の本質を見失うことなく、簡素化しています。また、一般教育のカリキュラムに沿った内容なので、一般的な生物の授業にも適しています。
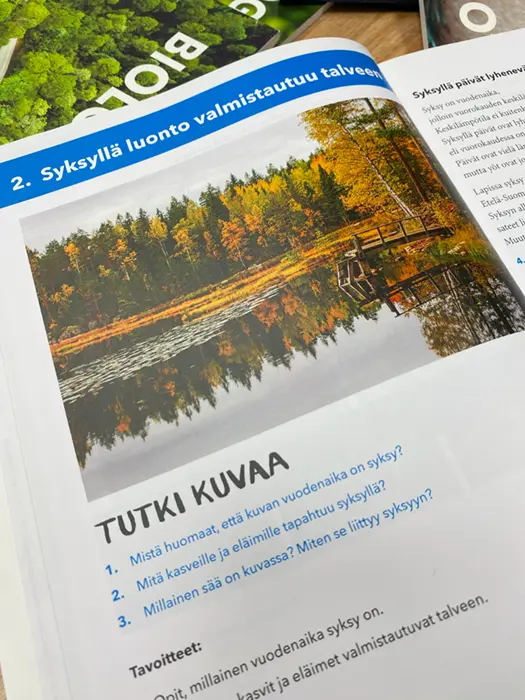
――従来の教科書では、フィンランド語を母語としない生徒たちにとって、どのような困難がありましたか。
従来の教科書には非常に多くの概念が記載されているにもかかわらず、あまりにも簡潔に説明されています。さらには文章量が多く、本質が見失われているケースがたくさん見られました。画像が多用され、さまざまな種類の文章が重なっているため、何が本質なのか把握しづらく、ページを見ていても落ち着かないのです。
――教科書の作成にさまざまな専門家の先生が関わっていますね。それぞれの役割は。
私たちはさまざまな立場の専門家からなる、ユニークなチームです。執筆にあたっては、まず生物教員が基本的な文章を書き、特別支援教育教員とフィンランド語教員が、特別な支援を要する生徒の理解に合うように、文章を編集しました。その後、生物教員が、記載内容が正しいかどうかをチェックしました。絵や課題のデザインはみんなで一緒に考えて、進めました。
この本は、休日や勤務時間外に執筆されたものです。それぞれの専門分野でのスキルが、最終的にはプロフェッショナルとして結果に反映されたように感じます。最後に、文章は簡単な言葉で表されているかを、言語の専門家にチェックしてもらっています。
――実際にこの教科書を使用した事例や生徒の反応、成果などを教えてください。
本書の「リーディング復習問題」は、特に高い評価を得ています。レイアウトやイラストの分かりやすさ、さまざまなレベルの課題、イラストが文章を理解する上での助けになっている点なども評価されています。本シリーズは必要なものであり、多くの教師のニーズに応えています。
フィンランドでは、特別支援の教員は教科教育の資格を持っていませんが、全ての教科を生徒に教えています。私たちの教師用の教材は、生物教員でなくても簡単に使えるように工夫されています。例えばイラストには、授業でディスカッションするための質問が添えられていますし、練習問題や絵の問題には全て、解答例が用意されています。
一方、本シリーズがいくつかのパートに分かれていることで混乱する教員や、テストに向けた指導が難しく、手間が掛かると感じる教員もいるようです。
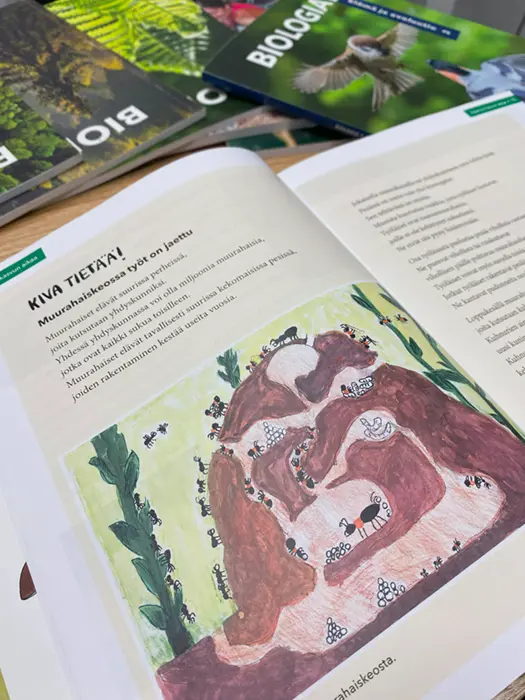
――今、フィンランドの教育について感じられていることや、日本の先生へのメッセージを。
生徒の読解力、語彙(ごい)力、集中力の低下を懸念しています。生徒のやる気、思考力、日常生活管理能力も、ここ数年で著しく低下しています。教育課程は生徒の自主性を重視していますが、生徒の能力は設定された目標と一致していません。
さらにはデジタル化の急速な進展と学校業務への統合は、多くの教師にとって課題となっています。一部の学校では、教員が自分の時間を使って、必要なデジタルトレーニングを自ら習得しなければなりませんでした。
将来的には、これらの問題にもっと注意を払うべきです。学級規模を大きくし過ぎないことや、教員の人数を増やすべきです。また、生徒の認知レベルに基づいたカリキュラムを作ることも重要です。
そして、今以上に教員の協調性を高め、授業の計画立案の時間を増やすべきです。行政の社会福祉事業、家庭、学校など、さまざまな立場の責任を明確にし、教員の職務内容を限定すべきだと考えています。
◇◇◇

日本のように、教科書会社によって作成された教科書を採択して現場で使うのも、もちろん素晴らしいことではあるが、「特別な支援を要する高校生に対する教科書がない」「現状の教科書では難しい」という現場発信の困り感から、この制作プロジェクトがスタートしている点が魅力的だ。誰が使うのか、誰のために作るのかが明確になっている点に、この教科書の価値がある。
さらに、現役教員が自分の専門性を生かしながら、協力して作成していくことで、専門性の掛け算が生まれている。紛れもなく彼らのチームはプロフェッショナルの融合であることは間違いない。
最後はフィンランド教育のリアルを話してくれた。これらの内容は、近年フィンランドにおいてよく取り上げられているトピックで、日本の課題とも近い。世界には、今よりも明るい未来に向けて、試行錯誤しながらもチャレンジしている同志がいるという事実を、忘れずにいたい。
【プロフィール】
徳留宏紀(とくどめ・ひろき) Nordic Educations代表、教育コンサルタント。フィンランド・ヘルシンキ在住。ヘルシンキ国際高校勤務。元公立中学校教諭。学力向上コーディネーターとして、教科学習を通じて非認知能力・認知能力の向上を実現。また現在は岡山大学大学院にて非認知能力の研究に従事。「教員の心理的安全性を高める組織マネジメント」で、2019年度日教弘大阪支部最優秀賞受賞。幼稚園から大学までの教育現場、保護者、企業を対象に、非認知能力に関する講演会も行っている。