大手飲食店時代のノウハウを生かしつつ、「教育の生産性改革」を進めてきた京都府八幡市立有都小学校の坂本良晶教諭。学校の働き方改革に新風を吹かす一方、日々の授業においては「信じて任せる」指導を通じ、子どもの主体性を伸ばすことを意識してきた。実際に日々どのような授業が行われているのか、プロジェクト型で進める音楽科の授業を取材し、その狙いなどを聞いた。(全3回)
7月4日の6時間目、4年1組の子どもたちは音楽科の授業で、とあるミッションに取り組んでいた。その名も「鈴木先生プロジェクト」。1年生の時の担任で、現在は他校にいる鈴木先生に、自分たちの成長した姿を動画に撮って送るというものだ。
授業は、リーダー役の3人の児童がリードする形で進む。動画に収めるのは『子どもの世界』とスピッツの『空も飛べるはず』の2曲の斉唱。まずは坂本教諭のギター演奏に乗って、練習を重ねる。『子どもの世界』は、歌の他に数人がリコーダーの演奏も担う。

入念に練習を重ねた後、いよいよ動画撮影の本番。「鈴木先生、僕たち私たちの成長した姿を見てください」とリーダー役の児童が言い、合図とともに坂本教諭がギターを奏でる。2曲の収録が無事に終了…と思いきや、児童の一人が「リコーダーを間違ったから、もう一回やりたい!」と言いだし、再収録がスタート。2回目はうまく行き、無事に「鈴木先生プロジェクト」は完了した。
45分の授業は基本的に子ども主導で進められ、坂本教諭は時折指示を出す程度だった。それでも授業は順調に進み、子どもたちは楽しそうに活動していた。「鈴木先生に見てもらうのが楽しみ」という子どもたちの感想からも、一人一人が高いモチベーションで斉唱や演奏に取り組んでいたことが分かる。
――先ほどの授業といい、5時間目の交流授業といい、自身が説明する場面は限られ、活動を子どもたちに委ねていたのが印象的でした。
そうですね。もちろん、一斉講義形式で子どもたちに知識を付けたり、思考・表現の仕方を教えたりはしますが、アウトプットの時間は子どもたちに委ねるようにしています。こうした授業の進め方には子どもたちも慣れているので、アドバイスすることはあっても、「こうしなさい」と指示を出すことは減りました。
――その狙いは、どこにあるのでしょうか。
やはり子どもの主体性を伸ばすことです。学校には、やればやるほど子どもの主体性を奪う「マイナス仕事」が少なくありません。例えば、集会の発表などで、見栄えを気にしてセリフを全て教師が用意し、子どもたちに読ませるようなことがあります。こうした活動は、手段の目的化に陥っていて、子どもの主体性を殺してしまいます。
――主体的に活動するからこそ、学びが楽しくなるのでしょうね。
今日の2つの授業をご覧いただいて分かったと思いますが、子どもたちは本当に楽しそうに学んでいます。だから、クラスには登校を渋る子もいません。やはり大きいのは、1人1台端末が入って、ICT化が進んだことです。これにより、授業も学級経営も大きく変わりました。私の教室ではiPadが、子どもたちが「面白い」「楽しい」という瞬間をつくってくれるツールになっています。
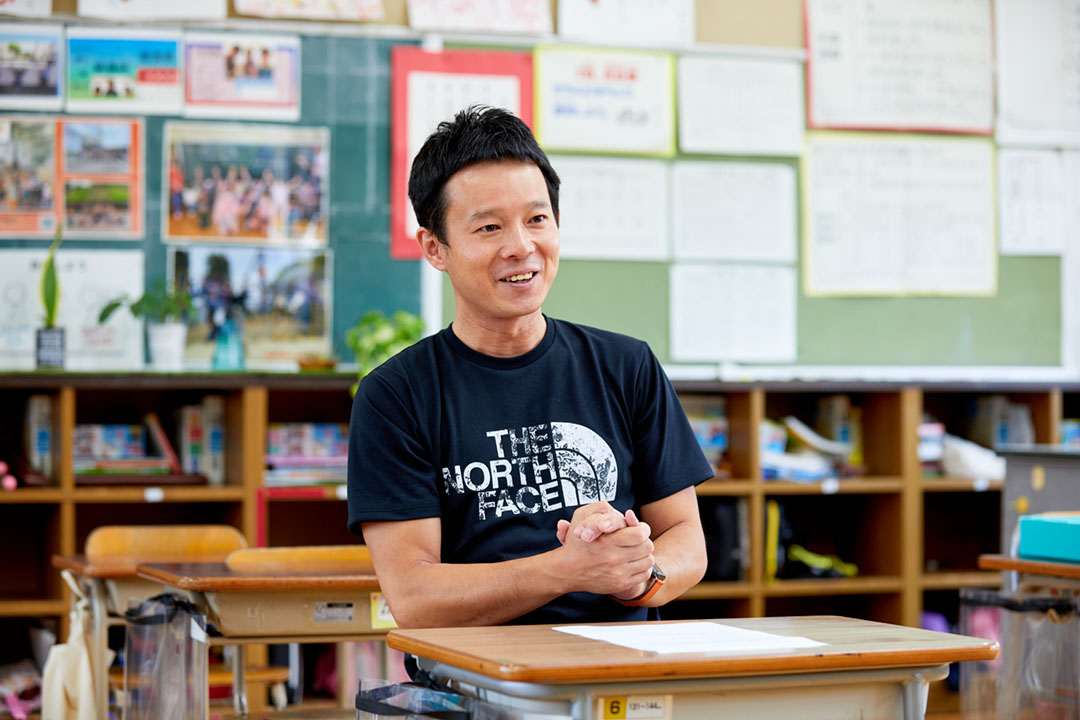
一方で、日本の学校のICT化は、世界から見て「3周遅れ」と言われています。だから、私自身が日々の実践を発信し、横に広げていきたいと考えています。一方で、多くの自治体や学校が厳しい規制を敷き過ぎて、現場が使いづらくなっているような状況もあります。私の場合は、何とかその規制をかいくぐりながらやっていますが、使いづらくて嫌になってしまう人も多いのではないでしょうか。
明治維新で武士がちょんまげを落とし、刀を捨てた時と同じような状況が、今の学校にはあります。刀では絶対に黒船には勝てません。多くの武士が侍としてのプライドを持ちつつ、近代社会に適応していったように、今の先生方も教師としての誇りを持ちつつ、指導の在り方や方法をアップデートしていく必要があります。開国派と攘夷派のように争っているような場合ではありません。
――ICTの他に、日本の学校教育の課題をどのように捉えておられますか。
日本でも新学習指導要領に基づき、資質・能力ベースの授業改善が叫ばれていますが、世界的な潮流から見れば、まだ乖離(かいり)があります。コンピテンシーベースと言いつつ、コンテンツの量は増えていますし、ペーパーテストの中身は変わっていません。
多くの教員はペーパーテストに合わせて授業を組み立てていくので、これが変わらないと授業は変わりません。そうした状況がある中で、私自身はいかにペーパーテストに引っ張られないようにするかを意識しながら、授業づくりをしています。大切なのは、21世紀型スキルを伸ばすような授業デザインをすることであり、すなわちそれは「面白い」授業、「楽しい」授業をやっていくことだと思います。
――2019年に出された著書『さる先生の「全部やろうはバカやろう」』は、大きな反響を呼びました。
そうですね。ありがたいことに、教育系の書籍としては異例のベストセラーとなりました。でも、最初に書籍化の打診をいただいた時は、「そんな本が売れるのか」と心配でした。それ以前の教育系の書籍にはないタイプの本でしたからね。でも、発売されるとあっという間に増刷、増刷となって、「ああ、自分がやってきたことは間違いじゃなかったんだ」と胸をなで下ろしました。
――書籍が売れたことで、何か変化はありましたか。
ちょっとした有名人になったことで、苦労したこともありました。「本を出している割に、全然できないじゃないか」みたいに取られたこともあります。実際、本を出した翌年に自分の力不足でほとんど通用せずに苦しんだこともあります。そうした経験を通じ、効率化のマインドセットは維持しつつも、現実を見ながら泥臭くやることの大切さも痛感しました。
――最後に、今後の目標を教えてください。

私自身がICTを活用することで「楽しい」「面白い」授業を創造すること、そしてそうした授業を横に広げていくことが今後の目標です。そのために現在も、ツイッターやインスタグラム、note、Voicyなどを使って草の根的な活動を展開しています。
また、実践内容を本にまとめて、『全部やろうはバカやろう』のGIGA版を出版予定で、現在執筆中です。そうやってICTを使った実践にチャレンジする先生を増やしていけたらいいですね。とにかく、世界から「3周遅れ」と言われる状況を何とかしていきたいと思います。
【プロフィール】
坂本良晶(さかもと・よしあき) 1983年生まれ。大学卒業後、大手飲食店チェーンに勤務し、兼任店長として全国1位の売上を記録。教員を目指し退職後、通信大学で教員免許を取得。翌年、教員採用試験に合格。2017年、子どもを伸ばしつつ、教員の働く時間を減らそうという「教育の生産性改革」に関する発信をツイッターで始める。『さる先生の「全部やろうはバカやろう」』(学陽書房)がベストセラーに。