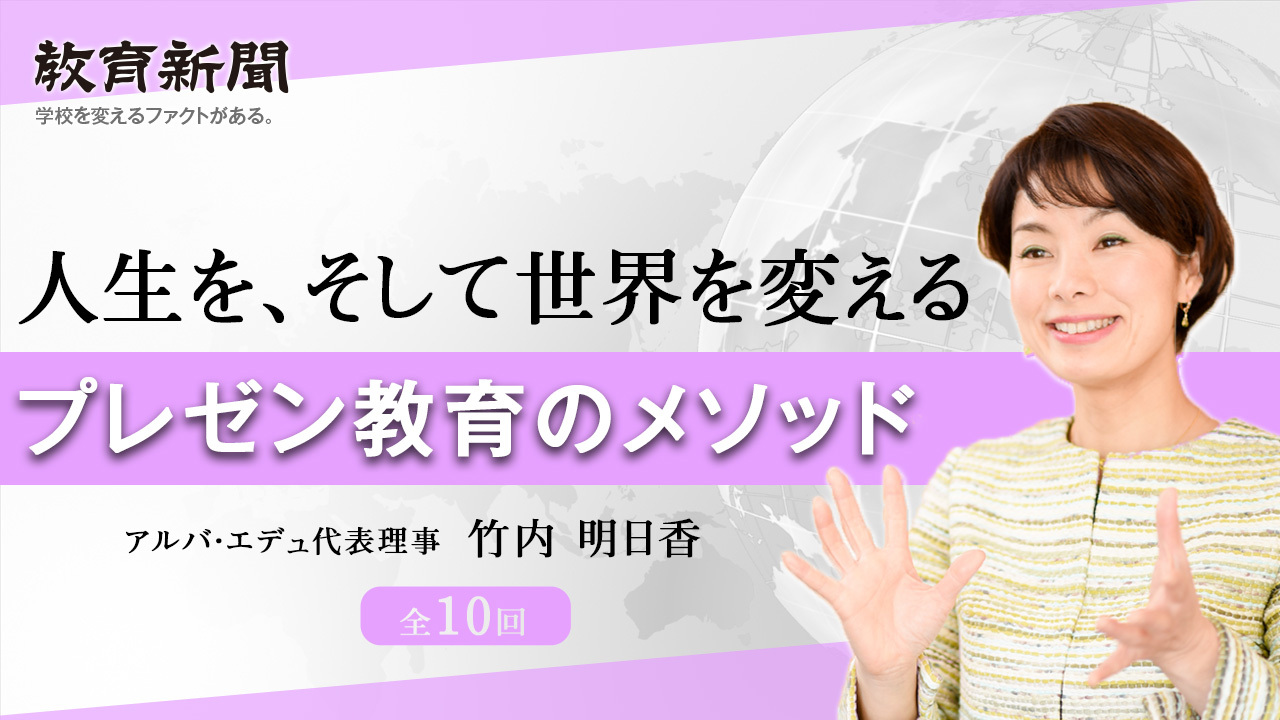
「プレゼン教育は、一見エリート教育かと思ったけれど、実際は低位の子たちが輝くプログラムなんですね」
私たちのプログラムを導入してくださっている東京都江戸川区の校長先生のこのお言葉が、今でも心に響いています。「学力」という物差しでは輝く場が少ない子どもたちも、プレゼンには主体的に取り組め、思いが伝われば大きな拍手を浴びることができる。プレゼン教育は一斉指導とは一線を画すもので、個別最適な学びを得られるプログラムだ。そう話された校長先生と近しいお言葉を、実は文科省の方からも頂戴したことがあります。「アルバ・エデュのプログラムは個別最適化のど真ん中ですね」と。
自分を主語に、興味のあることや好きなことを探究し、問いを立てて考えを深める。そして、正解のない「イイタイコト」が聞き手の心に伝わると、拍手喝采を浴びる。こうしたプレゼン教育において、例えば子ども同士がチームになって一つのプレゼンを創り上げたり、発表後にポジティブなフィードバックをかけ合ったりすると、協働的な学びへと発展します。特に学年が上がり、SNSグループごとに人間関係が閉じていくような年代では、クラスメートの多様な考えを知る良い機会となり、思わぬ副産物も生まれます。ある中学校のクラスで、中心的存在の子が過去にいじめを受けていたことを告白するプレゼンがあり、教室内からはすすり泣きも聞こえました。後日、先生からクラスでつらい思いを抱えていた別の子とその発表者が授業後に深く話すようになるなど、クラスの一体感が増したと伺いました。
かつてウォルト・ディズニー氏は、勉強についていけず学校を中退し、仕事先を何度も解雇されながら、大好きなネズミの絵を描き続けました。そして、202回も銀行に足を運んでディズニーランドの夢についてのプレゼンを繰り返しました。数字に強い兄がいたことも、夢の成就を近づけました。情熱を解放し、話すチャンスを得た人に、自分の苦手を補う協働者が加わることで、夢はより一層実現に近づくのです。
世の中を変えているのは、社会の課題、不満や不安を解決に導くユニークなアイデアを通じて賛同者・共感者を集め、行動に移している人たちの愚直な営みです。効率的に解を導き出すことだけに躍起になるのではなく、心理的安全性のあるクラスの中で「話す力」から多様性を引き出し、相互に認め合っていく。そうしたクラスこそ、世の中を変える人材を多く輩出するように思います。