災害支援の現場では、コーディネーション(調整)が重要です。さまざまな団体や個人が、「何か役に立ちたい」という志を持って被災地に駆け付けてくれても、それらを整理する団体や人が必要となります。そうでないと、支援が特定の地域に集中してしまい、被災家庭や子どもたちに支援が均等に行きわたらないという問題も起こります。
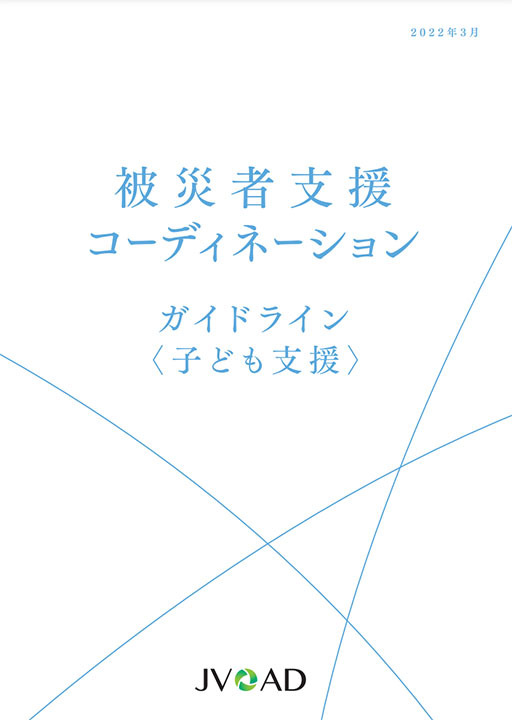
また、さまざまな支援団体が教育委員会や学校に押し掛けて子どもたちの情報を得ようとするため、行政や先生方に迷惑を掛けることにもなります。だからこそ情報を整理し、支援に漏れやむらが生じないように調整をするコーディネーターの役割が必要になるのです。
世界の災害支援の現場では、国連などによる「クラスターアプローチ」と呼ばれる制度があります。教育、栄養、水衛生、保護などの分野(クラスター)ごとに調整団体がおり、政府や自治体の担当局にも出席してもらう形で定例会議が行われています。子ども支援分野では、UNICEF(国連児童基金)やセーブ・ザ・チルドレンなどの団体が調整役になることが多いです。

日本でもJVOAD(特定非営利活動法人全国災害ボランティア支援団体ネットワーク:Japan Voluntary Organizations Active in Disaster)が、2022年3月に「被災者支援コーディネーションガイドライン」を作成しました。子ども支援の分野でもCFS協議会(災害時の子どもの居場所協議会)などが協力し、「被災者支援コーディネーションガイドライン<子ども支援>」が作成されています。このガイドラインには、7つの子ども支援分野ごとに支援の内容、目指すべき理想の状況、行政と民間による支援、支援の不足や偏りにつながる要因、そして参考となる事例が明記されています。7つの支援分野には、①居場所支援(遊び・学習等)②子ども関連施設への支援③災害時のストレスとメンタルヘルスケア④物資支援⑤経済支援⑥子どもの権利保護に関する啓発や権利擁護など⑦復興計画づくり(子どもにやさしい防災計画)――が含まれます。
今後、これらのコーディネーションガイドラインは、各都道府県や市区町村などにおいて、それぞれの地域の実情に合わせて使われることが想定されています。災害時や災害後の子ども支援において、関係機関同士の連携や調整不足により子どもたちがさらされるリスクへの対応が十分に行われず、支援を必要としている子どもや家族に必要な支援が届かない状況が起きないようにするためのものです。今後も、次の災害がいつどこで起きるか分かりません。子どもたちへの支援が円滑に調整されることで、発災直後から子どもたちを取り巻く状況が速やかに把握され、子どもたちの安心・安全な生活が確保されるための支援が適切に実施されることを願います。
(おわり)