今回は、精神疾患教育の授業で求められる工夫と配慮を紹介したい。いずれも、精神疾患の特徴に基づくものである。
まず、知識を網羅することよりも、実際を知ることを優先したい。いろいろな病気の症状や治療を知ろうとすると、知識の羅列となって実感が湧きにくい。精神疾患を持つ方の生の語りを聞くことができると、具体的なイメージが持てるようになる。授業に当事者を招くことは難しいかもしれないが、動画教材を用いて実際を知る工夫がある。スポーツ選手や芸能人の中には精神疾患をカミングアウトしている方も増えているので、そうした動画は偏見をなくすことにもつながる。
次に、生徒自身、生徒の兄弟姉妹や両親、友達が精神疾患を持っている場合があることを念頭に置いておきたい。別世界のこと、遠い将来に罹患(りかん)するかもしれない病気ではなく、今現在の自分や身の回りのことかもしれない。授業の中での話し方や説明において、そうしたことへの配慮をお願いしたい。
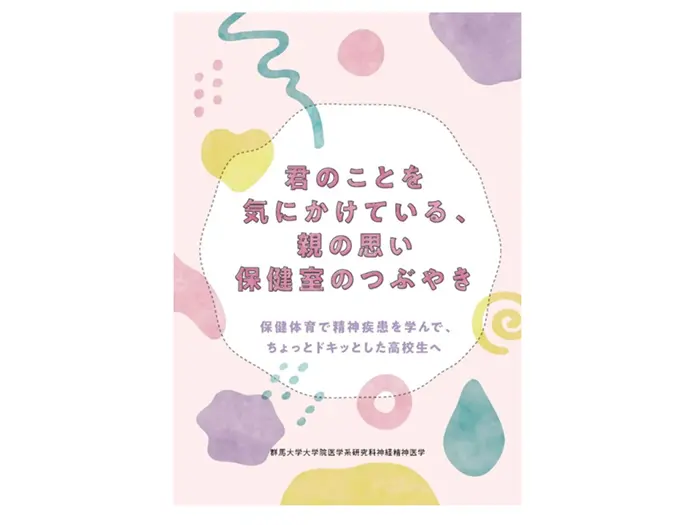
医療の基本を定める医療法で、精神疾患はがん・脳卒中・急性心筋梗塞・糖尿病と並ぶ「五大疾病」の一つとされているので、「5つの国民病の一つ」という言い方が受け入れやすい。それでも傷つく生徒がいるかもしれないと考え、群馬大学精神科では冊子「君のことを気にかけている、親の思い保健室のつぶやき-保健体育で精神疾患を学んで、ちょっとドキッとした高校生へ」を作成した。ホームページからPDFファイルをダウンロードできるので利用してほしい。
さらに、「予防」の考え方にも配慮をお願いしたい。どんな病気でも、健康増進に励んで予防できることが理想だが、努めたからといって100%予防できるわけではない。予防を強調すると、病気を持つ人を「努力不足の自己責任」と責めるニュアンスになりやすい。予防の話とセットで「精神疾患になっても大丈夫」というメッセージを届けたい。
認知症について、「予防と備え」という考え方が広がってきている。そこでの「備え」は、本人や家族としての準備だけでなく、社会の仕組みとしての取り組みでもある。「精神疾患になっても大丈夫な学校と社会をつくる」という考え方を広げたい。
最後に、「精神疾患の原因」について、正しい理解をお願いしたい。「環境か遺伝か」という質問に、私は「高血圧や糖尿病と似ている」と答えている。高血圧になりやすい体質を持ち合わせていても、塩分を制限したり運動に励んで血圧を時々チェックしたりすることで、高血圧を予防したり軽くしたりすることができる。同じように精神疾患についても、ストレスへの敏感さがあっても、役立つ対処法を見つけたり自分のメンタルヘルスを時々振り返ったりすることで、精神疾患に備えることができる。