「病気未満」のメンタルヘルスは生徒にとって身近なものなので、精神疾患より関心が持ちやすい。学習指導要領の範囲を少し超えるが、精神疾患と関連して教えることができると、生徒のメンタルヘルス向上が期待できる。
リストカットをはじめとする自傷は、保健室でしばしば出合うだろう。第3回で述べたストレスへの「行動の反応」である。痛みを感じ、出血を目にすることで、心の苦しさを一時的にまひさせる。ストレスのつらさをやり過ごすための、やむにやまれぬ自己対処である。
生徒自身はそう内省できないことが多いので、まずストレス対処の一般論として理解してもらう。その上で、生徒にどんなストレスがあり、どんなつらさを感じているかを、一緒に探していく。理解してくれるかもしれない大人を身近に感じられると、自傷に頼らないストレス対処法を模索できるようになる。そうやって解決できることを生徒自身が実感することが、落ち着きを取り戻すもとになる。
不登校は、どの学校にもあるだろう。いじめもなく、生徒自身にも理由が分からないときほど、メンタルヘルスが影響している。背景の一つは、対人関係の苦手さである。おとなしいタイプと、考えがはっきりして周りと折り合えないタイプがある。もう一つは、自分自身と将来への不安である。勉強や部活動が思うようにできないと、意欲が湧かず、自分に自信をなくし、将来を不安に感じる。不登校で経験が不足すると、苦手意識や不安がますます増して、悪循環を招く。教科の学習とともに学校で学んでいる、対人関係と自己内省についてのつまずきである。
そうした不登校の心理を理解してもらうために、当事者の声を紹介している本がある。岩波ジュニア新書『居場所がほしい-不登校だったボクの今』は、自身の経験をもとに不登校支援に携わっている著者の話なので、不登校の生徒にも受け入れやすい。自分と同じ経験を語る先輩の声を聴くことで、対人関係に少し希望を持て、見通しが見えてくると不安が減る。そうなることができれば、不登校にどう向き合えばよいかを考えるゆとりができる。
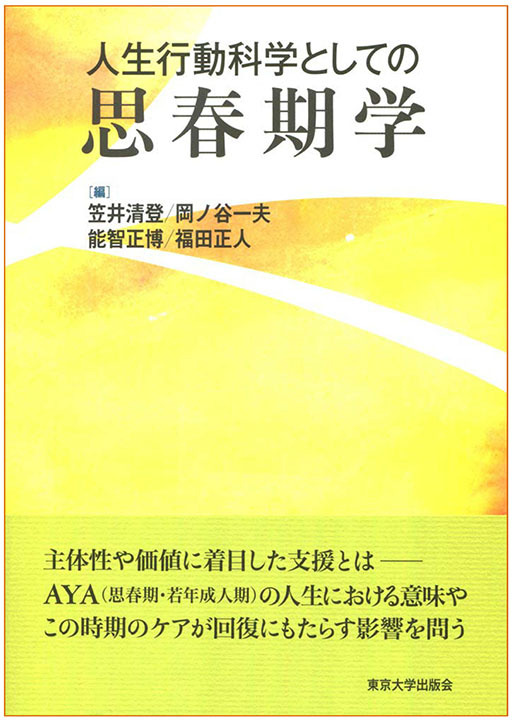
発達障害について、教師向けの講習は数多いが、当事者の生徒やその同級生が知る機会はどのくらいあるだろうか。医学部の1年生に、発達障害は「強い個性」であり「自覚して使いこなせれば『長所』、気付かずに振り回されれば『生きづらさ』」と講義をすると、初めて知ったという感想が多い。振り回されれば、自傷や不登校の背景となることもある。なお、高校生に向けた本として、ちくまプリマー新書『ぼくらの中の発達障害』がある。
思春期の心についての解明は、最近になってようやく進んできた。その成果をまとめた書籍に『人生行動科学としての思春期学』がある。