高校保健体育科での精神疾患教育は、約40年ぶりの再開である。1965年ごろまでの教科書には、精神疾患について「廃人同様になる、優生手術の対象」という今からは想像もできない差別的な記載があったため、70年代後半から消えた経緯があった。今回の再開は、精神疾患についての医学医療の進歩とともに、人々の理解と社会の仕組みが進んだことの表れである。WHO(世界保健機関)が2013年に「メンタルヘルスなしに健康なし」としたように、今ではこころの健康の重要性は当然のことと受け止められている。
精神疾患やメンタルヘルスは誰にとっても重要なテーマであり、とりわけ若い世代にとっては健康問題のトップに位置付けられるもので、これからの長い人生がどう充実するかの鍵となる。さらには、自殺という形で命にも関わる。精神疾患教育が目指すメンタルヘルス・リテラシーは、精神疾患について知識があり、理解ができていることだけではない。精神的な不調に気付くことができ、援助を求めることができ、周囲を助けることができる、そうした行動を身に付け実践できることである。
しかし、メンタルヘルス・リテラシーは個人としての取り組みに基づく自己責任ではなく、社会としての取り組みでもある。ストレスの多い世界で、互いに心を支え合う地域社会、心の危機に支援がすぐ届く仕組み、心を病んでも安心して暮らせる社会、そうした「こころの健康社会」の構築が目標である。自動車が故障したとき、どこに居てもJAF(日本自動車連盟)が30分ぐらいで来てくれるが、死にたいと思った人のもとに、専門職が支援に駆け付ける仕組みはない。国の基幹としての自動車産業だけでなく、人々の生活の基盤である「こころの健康」を大切にする社会が、「未来の当たり前」となることを期待したい。
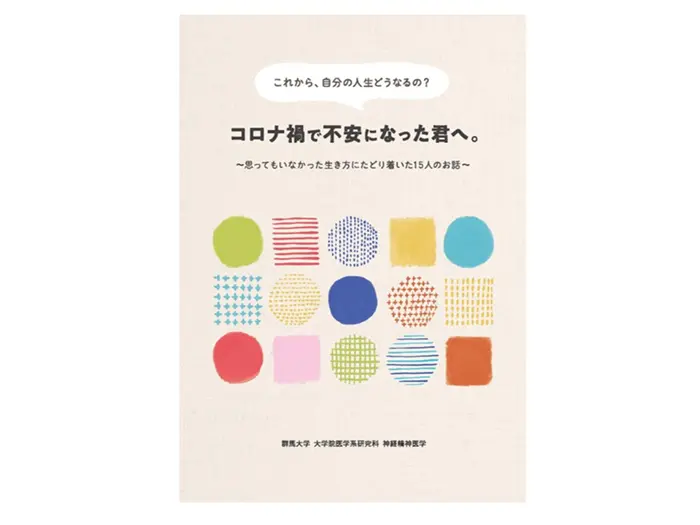
そこまで大掛かりでなくても、自分ができる社会としての取り組みを、少しずつ進めていきたい。筆者は大学入学直後の1年生に、「大学生に読んでほしい本」を勧めている。例えば、岩波ジュニア新書『〈できること〉の見つけ方-全盲女子大生が手に入れた大切なもの』は、視力障害に伴う精神的な困難に挑戦した画期的な生き方を紹介している。『「働く幸せ」の道-知的障がい者に導かれて』は、日本で一番大切にしたいとされた会社の経営者が幸せについて語ったものである。『あふれでたのはやさしさだった-奈良少年刑務所 絵本と詩の教室』は、重大犯罪を犯した少年が持つ純粋な心を教えてくれる。また、筆者自らもささやかな取り組みとして、若者に向けた冊子「これから、自分の人生どうなるの? コロナ禍で不安になった君へ。」を作成し、群馬大学精神科のホームページで公開している。
今後、高校保健体育科での精神疾患教育が、「こころの健康社会」の礎となることを願っている。
(おわり)