
約3000着のこども服の譲渡会や母親らとの交流を通じて、環境問題や子育て支援など社会が抱える課題について学生たちが考える取り組みが9月4日、東京都文京区の東洋学園大学で開かれた。

中学生の8割、小学生・高校生の9割が平日に適正な睡眠時間を確保できていない――。そうした実態が9月3日、寝具メーカー大手・西川が公表した「nishikawa 睡眠白書 2025」で明らかになった。

夏休みの課題を大きく分けると2種類になる。1つは各種コンクールに出品するために作成した、ポスターや工作、自由研究などの作品だ。もう1つは、「夏休みのドリル」や漢字練習・計算練習など、1学期の学習内容の復習である。
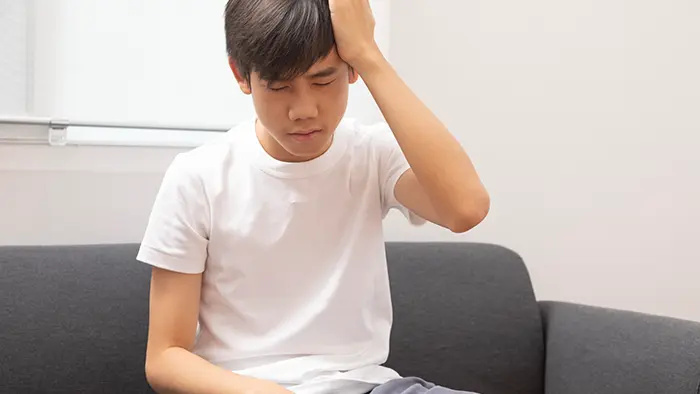
頭痛や腹痛など、月に1回以上経験する身体症状が多い子どもほど、抑うつ症状を併発するリスクが高まることが9月2日、全国の10~15歳の子どもを対象に行った国立成育医療研究センターの大規模調査で明らかとなった。

その出張授業、新しい教育ニーズに対応している?――。企業が学校などに行う出張授業をアップデートしようと、(一社)「プロフェッショナルをすべての学校に」は9月1日、東京都新宿区の早稲田大学で企業関係者約100人が参加するシンポジウムを開いた。

中学校で教員による生徒の盗撮が起きたことを受けて、愛知県みよし市は9月3日、全ての市立小中学校の校内に防犯カメラを設置すると発表した。今年度補正予算案に必要経費を盛り込んだ。

過度に大人の指示を待つ子が生まれてしまう要因は、それまでの大人の関わり方が大きく影響しています。特に、周囲と同じ行動を取ることが暗に推奨されてきた学級文化が根付いていると、指示を受けて動くことが当たり前になってしまいます。

江戸時代の教育学者、細井平洲の言葉に「人の子を教育するは菊好きの菊を作る様にはすまじく、百姓の菜大根を作る様にすべきこと」というものがある。菊好きは、理想的な好みの形を目指して育てる。百姓は形や大きさにかかわらず「おいしくなあれ」と育てる。最近は、自身が「菊好き」なのでは、と悩む先生たちによく出会う。菊好きから百姓への転換の難しさも、非常に多く見聞きする。

前回、「心理的事実」と「客観的事実」を明確に区別した上で、「心理的事実」については積極的に謝罪し、「客観的事実」については慎重に扱うことの重要性を伝えた。今回はそのスキルを読者の皆さんに授けることを目指して、具体的な事例を挙げながら解説していく。

近年、通信制高校の存在感が急速に高まっています。文部科学省の「学校基本調査」によると、2024年度の通信制課程在籍者は約29万人で、高校生全体の約10.7人に1人が通信制を選択しています。