「先生の話を聞いて、諦めずにやってみようと思いました。」
ある日、いつものように教室で語りを終えた後、ある子どもが笑顔でそう言いに来てくれました。私の言葉が、迷いの中にいたその子の背中をそっと押せた瞬間でした。教師の語りには、こうした「子どもの心を動かす力」があります。
私自身、語りの力を信じて、これまで多くの語り本を世に送り出してきました。本に掲載されている語り(とっておきの話)は、私が今まで担任してきた学級の子どもたちに語ってきたものです。
今、私たち教師の語りが必要とされる理由とは何でしょうか。VUCA時代に自分の人生の答えを探る今の子どもたちは、日々あふれる情報に囲まれています。SNSや動画を通じて、瞬時に答えを得られる時代です。しかし、すぐに見つかる答えばかりが、子どもの心を動かすわけではありません。信頼している担任の先生の言葉に耳を傾け、自分で気付き、考え、行動する。その過程が、子どもの心を大きく動かしていくのです。
教師の語りは、単なる情報伝達ではありません。子どもの心に問いを投げ掛けることで、ねらいの根底にある道徳的価値をより身近に感じられる効果があります。また、一方的な押し付けではなく、教師と子どもで双方向性のある語り合いを意識することで、思考を一層深めたり、考えを整理したりすることもできます。失敗したとき、友達とけんかをしたとき、うまくいかない日が続いたとき…。そんな日々の中で、教師の語りは「この言葉を信じて、諦めずにやってみよう」と思えるきっかけとなります。
また、語りは子どもたちと教師の信頼関係を築きます。「何を語るかの前に、誰が語るか」とよく言われますが、私はどちらも大切だと思います。なぜなら、「何を語るか」の積み重ねが「誰が語るか」になるからです。子どもたちからすれば、いつも心を動かす話をしてくれる先生の話をもっと聴きたいと思うことでしょう。
「何を語るか」の積み重ねを意味のあるものにするためには、教師が自身の教育観と向き合い続けなければいけません。今、この学級で何を大切にしたいのか。迷いながらも、目の前の子どもたちと語り合い続け、教師としての自分自身の答えを見つけていくのです。
つまり、語りをしているその間だけが「何を語るか」を生み出しているわけではないのです。
あなたに問います。「語る前に絶対に外せない教師のマインドセット」とは?
次回、またお会いしましょう。
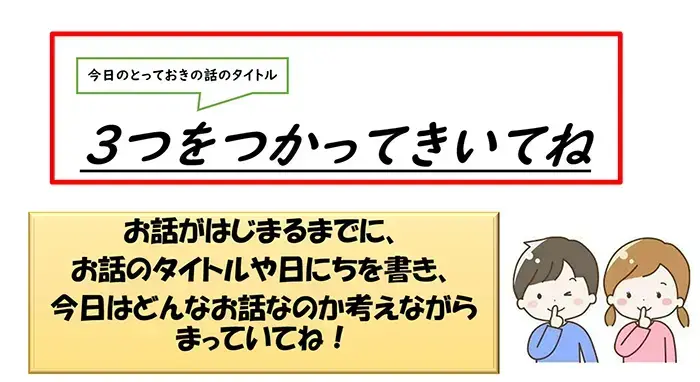
【プロフィール】
小木曽弘尚(おぎそ・ひろなお) 愛知県公立小学校教諭。「教師の語り」を中心テーマに実践と研究を積み重ねてきた。教育サークル「Totteoki」代表。LINEオープンチャット「ZTK全国とっておきの話クリエイター協会」「STO初任者をとっておきの話で応援する会」運営。著書に『こどもの心に響く とっておきの話100』(東洋館出版社)、『高学年担任の子どもの心をつかむ とっておきの語り』(学陽書房)、『くろぺん先生とっておきの局面語り 叱るよりここ一番で効くお話』(明治図書出版)など。編著・共著・雑誌寄稿も多数。