子ども・若者政策としての「居場所」の重要性が再評価され、全国各地でさまざまな居場所づくりが始まっている。しかし、学校もまた子どもにとって身近で大切な居場所の一つであるという視点は見落とされがちだ。そうした中、高校での居場所カフェなど、学校の中に居場所をつくる取り組みが広がっている。学校の中に居場所をつくることや、地域の団体とつながることで、どのようなメリットがあるのか。居場所づくりでエアポケットになりがちな中学校での取り組みを取材した。
以前はコンピューター教室だったという部屋に20人ほどの生徒が集まり、少しにぎやかな雰囲気でそれぞれの学習に取り組んでいた。東京都足立区立花保中学校では、毎週水曜日の放課後にASK(After School Katariba)という居場所が開かれている。登録すれば花保中の生徒は誰でも利用できる。最初の30分は目標を設定して各自で勉強を進めるが、その後は隣にある「リビングルーム(ochanoma)」でくつろぎながら、遊んだり、話したりする生徒が多い。
「過ごし方は、ルールを含めて子どもたち自身が話し合って決めている。夏休みなどにこの場所を使って開くイベントも、子どもたちの声を聞いて企画している」
そう話すのは、足立区内で学習支援をしている認定NPO法人カタリバの中井征弥さんだ。普段のASKでの学習支援や見守りは、カタリバのスタッフが行っているが、イベントでは地域の支援団体と連携し、さまざまな大人と生徒が一緒に食事をつくったり、スイカ割りなどの催しをしたりして一緒に楽しむそうだ。
1年生の頃からほぼ毎週ASKに来ているという3年生の男子生徒は「宿題や問題集に取り組んではいるけれど、どちらかというと遊びに来ている感覚だ。ここに来れば先輩・後輩の上下関係もなく、多くの人とフレンドリーに話すことができる」と顔をほころばせる。
花保中の泉明美主任教諭は「同じ部活動や同じ小学校の出身など、中学生にはさまざまな人間関係があるが、普段の学校生活の中では、違うクラスや学年に行く機会は限られている。ここには1年生から3年生までが一緒に集まって勉強して、文字通りお茶の間のようにひと息つける場所だ。カタリバのスタッフの方や地域の方もいて、親や教員の縦の関係、友人との横の関係とも違う斜めの関係がある」と話す。クラスや学校になじめていない生徒でも、ここならば話ができる、という場合もあるそうだ。
ASKが始まったのは2021年。その翌年には、使われていなかった隣接する準備室を改装して居場所化するリビングルームプロジェクトが動き出した。何もない状態からどんな部屋にしようかと話し合った当時の生徒はすでに卒業し、壁にはASKをよく利用していた卒業生の手形が飾られている。居場所のルールや家具の配置はその年の生徒たちによって常に変わっているものの、誰が来てもよく、思い思いに過ごせる場所という点は変わらずに受け継がれているようだ。
学校の中にありながら、普段の学校生活とは異なる時間を過ごせる居場所。それは、卒業した後も学校や地域とのつながりを感じられるもやい綱のような存在でもある。
生徒は教室に入ってくると、ホワイトボードに「今日のイラストテーマ」として提示された「シマウマ」の絵を描いて、おのおのが好きな席に座っていく。
横浜市立寛政中学校では月に2回、月曜日の放課後に視聴覚室で「学びの居場所~アナザープレイス~」が開設されている。寛政中の生徒なら誰でも気軽に来ることができ、30分ほど学習に取り組んだ後は、参加者やスタッフとちょっとしたゲームをしたり、さいころを振って出たテーマについて話す「さいころトーク」をしたりする。
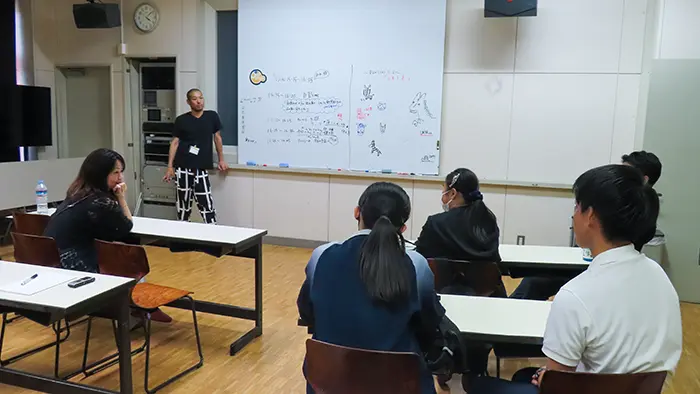
運営しているのは、寛政中のある鶴見区を中心に、精神疾患を抱える親とその子どもの支援をしているOmoshiroだ。スタッフの青木大三さんは「私たちとしては、その場にいる人が自分の気持ちを大事にしながら、安心してコミュニケーションを取ることができる場所にしたいと思っている。自分の思いはこうしたら伝わるかもしれない、ということを知ってもらえたらと考えている。昨年からスタートして、さまざまな仕掛けを大人たちも楽しみながら試行錯誤してやってきた。中学生が意外と自分のことを話す『さいころトーク』を求めているという気付きもあった」と振り返る。
この日も学習がひと段落すると、「落ち込むときって、どんなとき?」というお題で、スタッフの木内寛長さんによる「お悩み相談」のコーナーが始まった。生徒もスタッフも、そして様子を見に来ていた教員も、話の輪に自然と加わる。
教員やスタッフが最近落ち込んだことについて愚痴をこぼすように言うと、生徒がアドバイスすることもある。逆に「どうやってストレスを解消しているの?」と木内さんが聞くと、生徒が少し悩みながら、何気なくいつもやっていることを思い出し、少しずつつぶやいていく。普段は教員と生徒、大人と子どもという関係だが、ここではそれぞれ一人の人としてお互いに自己開示をしているように感じられた。
久しぶりに来たという中学2年生の女子生徒は「ここに来ると人と話せて、楽になれる」と打ち明ける。
「中学生は自我の確立に向けたスタートラインに立っている段階だ。学校や家庭とは異なる環境で、教師でも保護者でもない第三者的な大人の価値観に触れながら、やりたいことを整理していくことが大事だ。中学生が、自分はどうやって歩いていこうかと、0.5歩でも1歩でも踏み出すきっかけをつくりたい」と木内さん。
寛政中でこのアナザープレイスの立ち上げの中心メンバーとなった近藤嵩純教諭は「子どもが子どもらしくいられる機会がなかなかないまま中学生になった生徒が多く、大人から自分の存在を純粋に受け入れてもらえた経験が少ないと感じていた。部活動も希望制になる中で放課後に居場所をつくっていく必要がある。将来的には、地域の中に子どもたちが自由に過ごせる場所ができるのが理想だ」と話す。
地域にある居場所が学校との連携を働き掛ける動きも出ている。全国こども食堂支援センター・むすびえは昨年度から「こども食堂・学校架け橋プロジェクト」をスタートさせ、子ども食堂を運営している団体などに委託して、学校と連携した取り組みを模索し始めている。
プロジェクトの委託を受けた団体の一つ、ふうどばんく東北AGAINでは、これまでも高校で出張授業を行ったり、地域の高校生がボランティアとして活動に参加したりしてきた実績がある。今年度からは拠点を構える宮城県富谷市で、学びの多様化学校との連携を開始した。ふうどばんく東北AGAINのスタッフが学びの多様化学校である富谷市立富谷中学校西成田教室に出向き、生徒向けに料理教室を開くことになったのだ。

ふうどばんく東北AGAIN副代表理事の髙橋尚子さんは「普段、フードバンクなどで食糧支援をしている家庭の中には、子どもの不登校で悩んでいる保護者もいたので、不登校経験のある子どもが通っている学びの多様化学校とつながり、どんな支援ができるのかをもっと知りたいと思った。生徒も教師や保護者以外の大人と関わる機会になるので、学校としても前向きだったのはありがたかった」と話す。6月に開かれた1回目の料理教室では、切ると断面に模様や絵が表れる「飾り巻き寿司」に挑戦。生徒は準備から片付けまで積極的に参加し、教員からも好評だったという。
しかし、学校の中で地域の団体が独自の活動をしていくには、さまざまなハードルがある。特に食品を扱う活動の場合、施設の利用や衛生管理の観点から難色を示されることが多い。
「企画の最初の段階が一番大変で、お互いの考えていることややりたいことが分かれば、学校ともっと一緒にできることがある。そのためには、普段から学校とつながりをつくって、私たちの活動を知ってもらうことも必要だ」と髙橋さん。学校の施設を使って居場所をつくることができれば、地域住民や子どもが集まりやすいなどのメリットがあると強調する。
【キーワード】
居場所 子どもが心身の両面で安心、安全に過ごせ、社会的なつながりを実感できる場を地域の中につくっていくことが求められている。2023年12月には、こども・若者の視点に立った居場所づくりを全国で推進していく政策上の根拠となる「こどもの居場所づくりに関する指針」が閣議決定された。