
昨年12月に行われた中教審への諮問を受けて、教育課程企画特別部会で次期学習指導要領の骨格を検討する濃密な議論が繰り広げられている。新年度が始まり、次の学習指導要領も視野に入れた新しいチャレンジが学校現場で展開されることが期待される。そこで、文部科学省が先日公表した「諮問のポイント」をテキストに、特別部会でのこれまでの議論を振り返ってみたい。
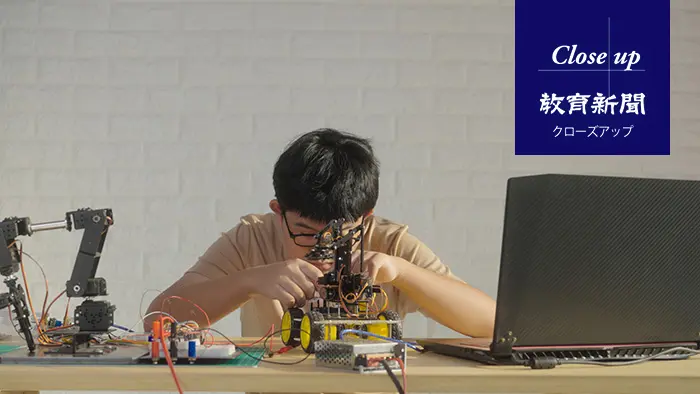
情報活用能力の充実に向けて、文部科学省は次期学習指導要領で中学校の技術・家庭科を分離し、「新・技術分野(仮称)」で、生成AIをはじめとする情報活用能力の育成に力を入れていく方針を打ち出した。これに先駆けて、初等中等教育における技術教育の学術研究を行う日本産業技術教育学会は、昨年5月に技術・家庭科の技術分野を「テクノロジー科」に再編することを提言している。

次期学習指導要領における探究的な学びと情報活用能力の関係について、文部科学省は5月22日、小学校の総合的な学習の時間(総合)に「情報の領域」を付加する方針を打ち出した。同日に開かれた中教審教育課程企画特別部会第8回会合で提案された。中学校では技術・家庭科を分離して、技術分野での情報技術の学習を他の領域との関連も持たせながら充実することも明記された。「学習の基盤となる資質・能力」についても言語能力と情報活用能力に整理する方向性を示した。
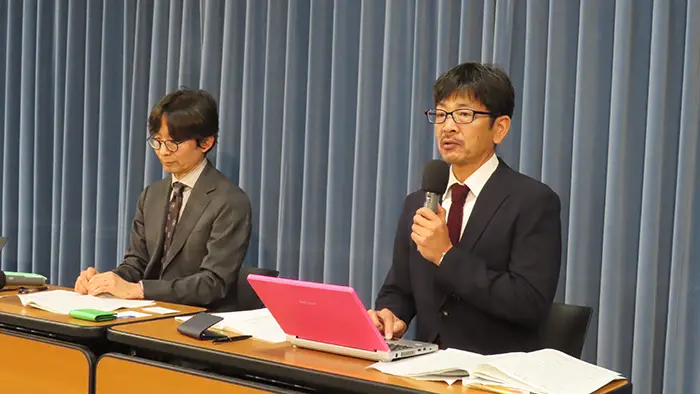
次期学習指導要領を巡り、東京学芸大学の大森直樹教授や学校の教員で構成する「標準時数と教育課程研究会」は5月14日、文部科学省で記者会見を開き、年間の標準授業時数を小学校で875時間、中学校で945時間とする提言を発表した。次期学習指導要領に向けた検討を行っている中教審教育課程企画特別部会では、文科省が「裁量的な時間」の導入などによって学校ごとに柔軟な教育課程編成を可能とすることを提案しているが、総授業時数は変わらないのでカリキュラム・オーバーロードの解消にはつながらないと批判している。

次期学習指導要領の基本方針を検討している中教審の教育課程企画特別部会は5月12日、第7回会合を開き、小学校から高校段階までの情報活用能力の育成について協議した。日本では情報教育の系統的な指導が行われていないなどの課題を踏まえ、文部科学省は小学校で一定の時間を確保することや、情報技術の進展の速さに対応するため、学習指導要領解説の一部改訂を適宜行っていくことなどを論点として提示。中学校では「技術・家庭科」が教員免許や担当教員が別であるにもかかわらず、成績評価では一つの教科として扱われることを課題に挙げた。この「技術・家庭科」の問題について、この日の会合で発表を行った堀田龍也主査代理は、別教科として位置付けることが適切だと提案した。

中教審の教育課程企画特別部会で、次期学習指導要領の方向性が検討されている。昨年12月の文科相からの諮問を受け、今年1月30日に初会合を開催。現在、4月25日の第6回まで会合を重ねている。ここまでの流れを図解で振り返り、キャッチアップしていこう。

次期学習指導要領の方向性を検討している中教審の教育課程企画特別部会は4月25日、第6回会合を開き、学習指導要領の構造化に向けて、「学びに向かう力、人間性等」と各教科の「見方・考え方」について議論した。

昨年12月に行われた中教審への諮問を受けて、教育課程企画特別部会で次期学習指導要領の骨格を検討する濃密な議論が繰り広げられている。新年度が始まり、次の学習指導要領も視野に入れた新しいチャレンジが学校現場で展開されることが期待される。そこで、文部科学省が先日公表した「諮問のポイント」をテキストに、特別部会でのこれまでの議論を振り返ってみたい。

次期学習指導要領の方向性を議論している中教審の教育課程企画特別部会は3月28日、第4回会合を開き、論点の一つである柔軟な教育課程編成を促進するため、学校ごとに授業時数の中に「裁量的な時間(仮称)」を設けられるようにするイメージを文部科学省が提案した。「裁量的な時間」では、児童生徒の実態に応じた学習支援などに使うことを想定しているほか、授業改善に向けた教員研修や学校の研究活動などに充てられるようにすることも検討する。

学習指導要領の改訂に向けて、学校の課題解決に取り組むSchool Voice Projectは3月14日、学校の教員に行った現行学習指導要領の内容に関するアンケートの結果を公表した。小学校では国語や外国語などで内容量が多いという声が多数寄せられ、自由記述では「総合的な学習の時間」に関する意見が目立った。

学年ごとに各教科などの授業時数の総枠として示されている標準授業時数。川崎市教育委員会は2月10日、7つの市立中学校の3年生で年間総授業時数が標準授業時数に足りないことが分かり、追加の授業を実施するなどの対策を行うと発表した。一方で、文部科学省は2月28日、標準授業時数を大幅に上回っている教育課程を編成している学校の割合を見ると、都道府県や政令市で大きな差があるとして、学校の指導体制に見合った不断の見直しを求める通知を出した。次期学習指導要領の議論でも、標準授業時数はポイントになる。そこで、標準授業時数の考え方を一度整理しておきたい。
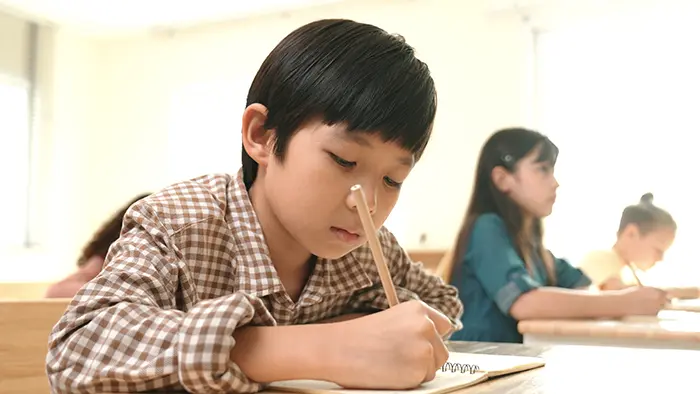
次期学習指導要領の骨格を話し合っている中教審の特別部会は2月17日、第2回会合を開き、新学習指導要領の構造化をテーマに議論した。個別の知識や技能を関連付け、各教科の主要概念の深い理解との関係を「タテ」に、各教科で育まれる資質・能力のうち、「知識及び技能」と「思考力、判断力、表現力等」の相互関係を「ヨコ」に整理したイメージが示された。

13回にわたり、現行学習指導要領について考えてきた。まだいくつか話すべきことはあるが、すでに次期学習指導要領の検討が始まっている。まずは中教審への諮問文を見ていきながら、残りの話題についてはその中で触れていきたい。今回の諮問理由はかなり長く、詳細な記述となっている。主な審議事項に入る前に、「顕在化している課題」として挙げられた3点を読み解いてみよう。

学習指導要領の改訂に向けて、中教審初等中等教育分科会教育課程部会は1月29日、第132回会合を開き、昨年末に中教審に諮問された「初等中等教育における教育課程の基準等の在り方について」などに関する意見交換を行った。諮問事項の基本的な方向性を議論する「教育課程企画特別部会」を設置することも決めた。

次の学習指導要領に向けて、昨年12月、中教審に「初等中等教育における教育課程の基準等の在り方について」が諮問された。今後、中教審で学習指導要領の改訂作業が始まるが、その前にまず、諮問がどんな審議を求めているのかを押さえておきたい。そこで、文部科学省初等中等教育局教育課程課教育課程企画室の栗山和大室長に、諮問のポイントを聞いた。栗山室長は学習指導要領の改訂のプロセスを通して「学校現場や教育委員会とコミュニケーションしながらつくっていきたい」と話す。

阿部俊子文科相は1月14日の閣議後会見で、学習指導要領の次期改訂に向けて中教審に諮問したことに関連して、「さまざまな課題に取り組む上で教師の努力と熱意に過度な依存はできず、教育課程の実施に伴う負担の指摘にも真摯(しんし)に向き合うことが必要と考えている」と述べ、分かりやすく使いやすい学習指導要領の在り方などを論点に、中教審に検討を求めたいとの考えを示した。

現行の学習指導要領で示されているように、これからの社会を生き抜く子どもたちに必要な力を育成するため、学校は学び方を変えていかなくてはならない。しかし、学習指導要領をどう扱い、どう教育課程を編成していけばよいのか、その具体的な方法が分からずに困っている教員や学校は多いのではないだろうか。横浜創英中学・高校の本間朋弘校長は、現行の学習指導要領について「新しい学びを実現していくために、極めて弾力的かつ柔軟に運用できる基準が示されている。上手にさばけば、公立・私立問わず、より特色のある教育課程を編成できる」と強調する。同高校で2025年度からスタートする新しい教育課程をどのように編成していったのか、その具体的な手順とともに、次期学習指導要領改訂に向けた思いも取材した。

「授業時数や単位数を各校の校長に権限委譲し、引き算していかない限り、個別最適な学びや探究的な学習は実現できない」――。そう訴えるのは、文部科学省の学校DX戦略アドバイザーとして全国19自治体に生成AI研修などの支援を行っている、スクールエージェント代表取締役の田中善将氏だ。個別最適な学びや探究的な学習を広げる上で、生成AIの活用以前に重要なことは、「学校教育のスリム化」だとして、次期学習指導要領に向けた議論の中心に据えるべきだと主張する。
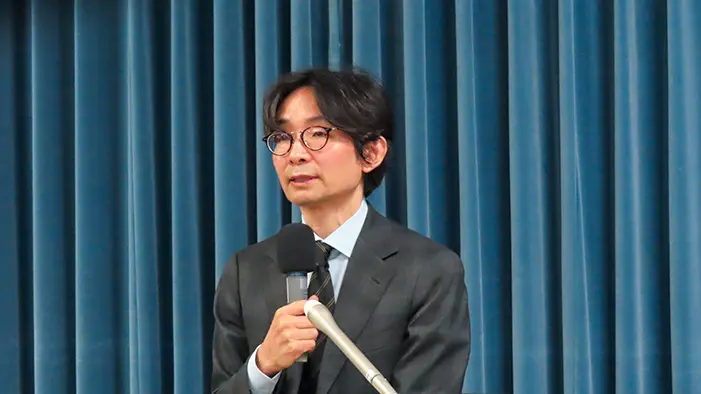
1989年に告示された学習指導要領以降の4期の学習指導要領を経験した中学校の教員は、前回や現行の学習指導要領下の標準授業時数を、子どもの生活に合っていないと捉える傾向にあることが11月21日、東京学芸大学の大森直樹教授の調査で明らかとなった。調査では、1日の授業時数の増加が、不登校生徒や病休の教職員の増加に関係しているかも尋ねており、関係していると考えている教員が多いことも分かった。大森教授は次の学習指導要領では標準授業時数や学習内容を削減し、週に6時間授業を2日だけにすることや、授業時間を現行の50分から45分に短縮することを提案している。
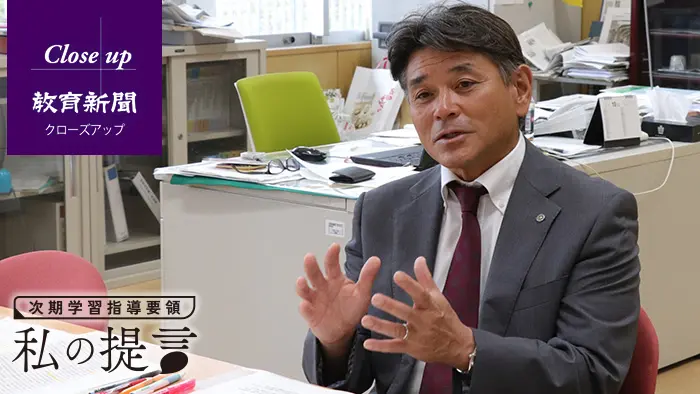
変わる授業の在り方、学校における働き方改革など、さまざまな課題に直面する中学校現場の視点で学習指導要領の改訂に向けた議論を注視する全日本中学校長会の青海正会長は、生徒の主体性を尊重する授業改善では「高校入試の在り方も議論すべき」と提言し、授業時間短縮などについても実情に合わせて学校が柔軟に対応できる方向での実現を期待する。また、青海会長は、スポーツ庁と文化庁が設けた有識者会議「地域スポーツ・文化芸術創造と部活動改革に関する実行会議」(部活動改革実行会議)の委員でもあり、「地域移行」から「地域展開」への改称案も上がる部活動改革については「中学校に期待される役割は大きく、簡単には切り離せない。学校によっていろいろな進め方があってよい」との見解を示している。

現行の学習指導要領では、小学3、4年生に「外国語活動」が前倒しされ、5、6年生では「外国語」が教科化されたほか、中学校と高校でも英語の学習内容が大幅に改訂された。「次期学習指導要領 私の提言」第6回は、2009年告示の高校学習指導要領(外国語)の作成協力者を務め、中学校・高校の検定教科書の執筆にも関わっている神奈川大学の久保野雅史教授に、現行の学習指導要領の課題と、今後の進むべき道について聞いた。久保野教授は現行の学習指導要領により、中学校で習う英語が極端に難化し、学力が二極化するなど、学校での英語教育は破綻の危機に瀕していると警告。文部科学省に対して今回の改訂の結果をきちんと検証し、次期学習指導要領に生かすべきだと訴える。
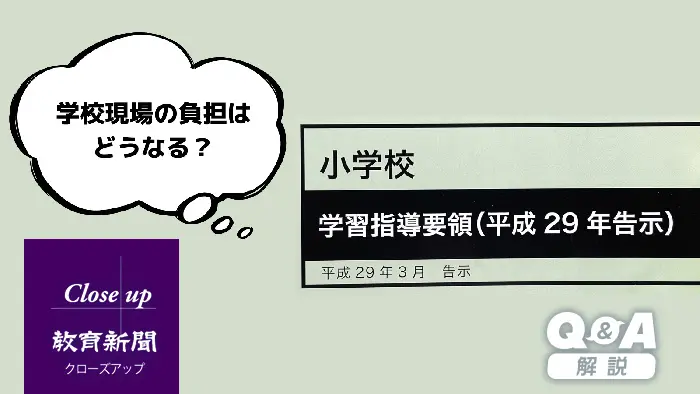
10年ぶりとなる学習指導要領の改訂作業を控え、学校現場にとって気になるのは、教育課程の新しい内容とともに、その実施に伴う負担に対する懸念だろう。改訂作業は中教審に対する文科相の諮問でスタートするが、それに先立つ文部科学省の有識者検討会では、学校現場の負担に向き合いながら、教育課程の見直しを進めていくという方向性が見えてきており、これまでの学習指導要領の改訂作業にはなかった新しい展開が動き始めている。その一例として有識者検討会の論点整理では、総授業時数について現在以上に増やさないように求めた。とはいえ、教師の「ワーク・オーバーロード」と教育課程の内容を巡る「カリキュラム・オーバーロード」は区別して考えるべきだといった考え方も示されており、教育課程の見直しと学校現場の負担を巡る議論は、改訂作業の中でどこまで実質的な内容になるのか、予断できない状況だ。これまでの議論と今後の方向性について、Q&A形式で考えてみたい。

教育課程を考える上で、目標や内容などと並んで欠かせないのが評価だ。現行の学習指導要領では、資質・能力の3つの柱に結び付く形で「知識・技能」「思考・判断・表現」「主体的に学習に取り組む態度」の3観点に整理され、高校でも観点別評価が導入されるなどしたが、教育評価が専門の西岡加名恵京都大学教授は、各教科は「知識・技能」および、「思考・判断・表現」と「主体的に学習に取り組む態度」の観点を統合した2観点に整理し、「主体的に学習に取り組む態度」は主に総合的な学習(探究)の時間(総合)や特別活動などで評価すべきだと提案する。「次期学習指導要領 私の提言」第3回では、西岡教授に評価の課題を聞いた。

学校の働き方改革の議論で、現行の学習指導要領の影響として指摘されているのが、学習内容が飽和して学校現場を疲弊させるカリキュラム・オーバーロードの問題だ。大森直樹東京学芸大学教授は、現役の小学校教員に行った調査などから、現行の学習指導要領が最も子どもの負担が大きく、不合理なものになってしまっていると指摘。平日は5時間とするなど、標準授業時数や学習内容を減らすことを提案する。

日本の教育課程の基準である学習指導要領の改訂に向けた議論が、間もなく本格化する。文部科学省の「今後の教育課程、学習指導及び学習評価等の在り方に関する有識者検討会」は9月17日に、論点整理案について大筋で合意。今後、取りまとめられた論点整理を基礎的資料として参考にしつつ、中教審での審議がスタートすることになる。それを前に、現行の学習指導要領の課題や改訂に向けたポイントを「次期学習指導要領 私の提言」として有識者にインタビューしていく。

今後の部活動の地域移行に向けて、室伏広治スポーツ庁長官は9月18日に開かれた記者会見で、「子供たちがスポーツ・文化芸術活動に継続的に親しめる環境づくり」が重要だと改めて強調した。現在、ワーキンググループでの検討が進んでいる「地域スポーツ・文化芸術創造と部活動改革に関する実行会議」で、論点の一つに次期学習指導要領における部活動の位置付けが挙がっていることについて、室伏長官は「子供たちがスポーツ・文化芸術活動に継続的に親しめる環境づくり」を軸に、学習指導要領にどう位置付けられれば、それが一番達成できるかという視点で考えるべきだとし、実行会議での議論に期待を寄せた。
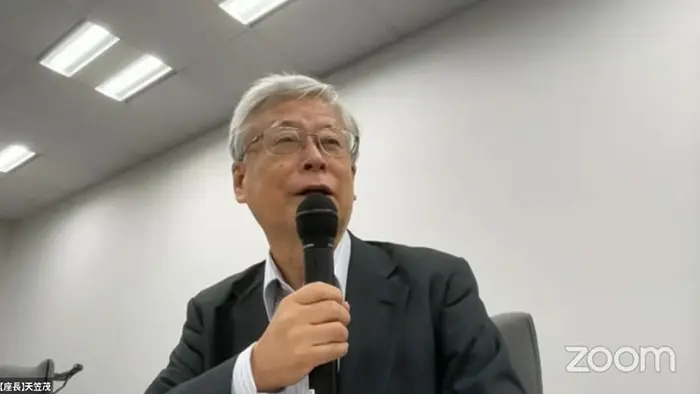
文部科学省の「今後の教育課程、学習指導及び学習評価等の在り方に関する有識者検討会」は9月17日、第15回会合を開き、これまでの議論を踏まえ、学習指導要領の改訂にあたって検討すべき課題をまとめた論点整理案について、大筋で合意した。論点整理案では、資質・能力を重視した現行学習指導要領の方向性を評価しつつ、教育課程の実施に向けた学校現場の負担感が大きいことを指摘。負担が生じる原因に向き合い、教育課程と教育環境整備が全体的に機能するようにすべきだとした上で、「総授業時数については、現在以上に増やすことがないよう検討すべき」と踏み込んだ。
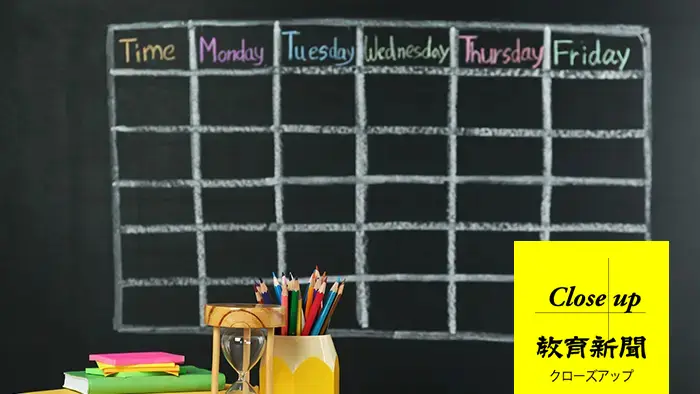
9月17日に示された文部科学省の「今後の教育課程、学習指導及び学習評価等の在り方に関する有識者検討会」の論点整理(案)では、次期学習指導要領を見据えた重要なポイントが提示されている。昨年12月以降、15回にわたる会議を踏まえて取りまとめられた論点整理は今後、学習指導要領の改訂をはじめとする教育課程の改善の検討の基礎的な資料として活用されることが期待される。論点整理案の構成を基に、その内容を詳しくみていく。
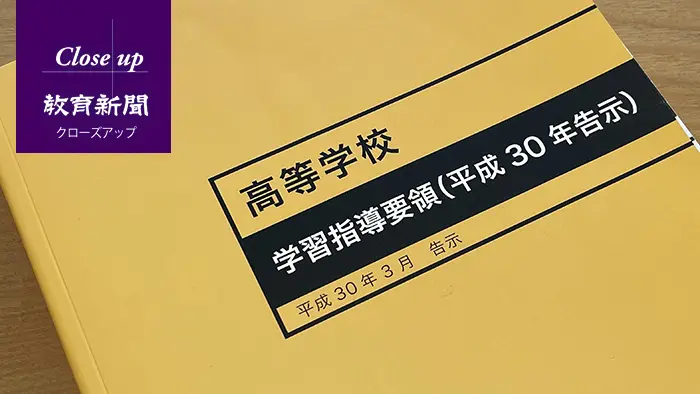
10年に1度の学習指導要領の改訂作業に先立ち、元文科副大臣の鈴木寛・東京大学教授・慶應義塾大学特任教授は教育新聞社の取材に応じ、「高校は義務教育ではないのだから、一律の学習指導要領はもう必要ない」と指摘し、独自の改革案を説明した。それによると、高校の学習指導要領は最低基準を示すために大綱化し、法的拘束力を外す。その上で、いくつかの大学が高校関係者とも協働して各教科・科目の指導指針案を提供し、そこから各高校は自校の生徒に合った指導指針案を選んで組み合わせ、教育課程を編成する。さらに英国の高校卒業資格と大学入学資格である国際資格「A-Level」を参考にしながら、高校生は学びたい教科・科目を自分で3から4以上選び、主体的に学びを深めていくことでウェルビーイングを実現する、という道筋を描いた。さらに、その実現に向け、文科相の諮問で、中教審にドラスティックな改革案の提示を求めることが「非常に重要だ」と強調した。聞き取った内容を寄稿形式でまとめた。