10月、11月、12月生まれの子供はメンタルヘルスの問題を抱える割合が高い―― という、ノルウェーの大規模データから導いた分析結果が最近、公表された。データを見る限り、季節要因ではなく、学校や教育システムに関連すると研究者は見ている。
ノルウェー科学技術大学(NTNU)のクリスティーネ・ストランド・バッハマン氏らは、1991年から2012年に生まれた4歳から17歳の子供たちの医療情報を分析した。ノルウェー人100万人以上のデータからは、10月から12月に生まれた子供たちは他の時期に生まれた子供より、精神疾患と診断される割合が高かった。言葉や学習、運動といった分野の発達の遅れに関しても同様の傾向が見られた。特に女子は不安やうつ病、適応障害などの感情障害と診断される割合が高い傾向があった。
この「生まれ月の逆風効果」は日本を含む世界中で研究が進んでいるが、ノルウェーの研究者は「季節要因」の影響ではないと見ている。生まれた月によって子育ての仕方に違いがあるとか、よりよい子育て環境を用意できる親が年初を狙って出産するといったことは考えられない。それよりも、学校や教育システムと関連していると見ている。
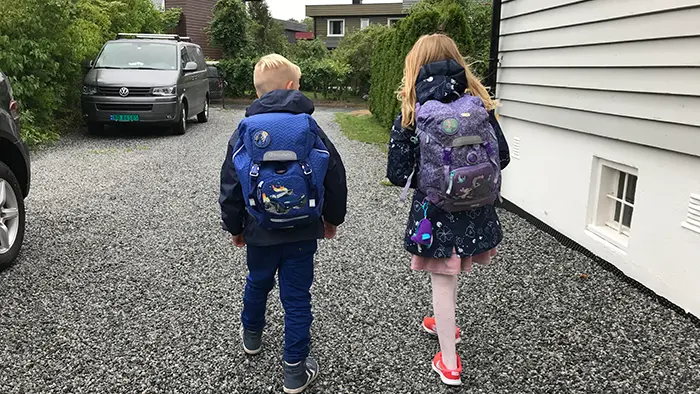
ノルウェーの基礎学校(日本の小中学校に相当)は8月から新年度が始まるが、その年に6歳になる子供たちが入学する。つまり、1月から12月に生まれた子供たちが集められて学年が編成されるのだ。そのため、12月末に生まれた子は、クラスで最も幼い子になる。日本の「早生まれ」の子たちと似たような立場だ。
2022年に同じ研究グループが公表した分析では、11月と12月に生まれた子は1月と2月に生まれた子に比べて、ADHDと診断されて治療薬が処方される割合が80%も多かった。
この「最年少」の子たちは、他の子たちに比べて発達が未熟なことが多く、多動性や衝動性があり、集中力に問題があることが多い。これはADHDの症状と重なるために、診断される割合が高いのだろう。子供の発達には個人差があるが、学年の区切りで判断することで、「最年少」の子たちの幼さが特に目立ってしまい、過剰に投薬されている可能性も示唆される。
クラスで「最年少」ということは、学習や運動、あるいは社会的な場面で、同年代の子供に比べて劣っていると感じる場面が多いことを意味する。そのネガティブな経験が、さまざまな形で蓄積されているのではないか、とストランド・バッハマン氏は言う。
妊娠37週未満の早産で生まれた子供も、ADHDと診断される割合が高い。正期産児として生まれた子供は年齢とともに投薬量が減少するのに対して、早産児として生まれた子供は投薬期間がより長くなる傾向がある。とすると、12月に妊娠37週未満で生まれた女の子は、そのこと自体は病気ではないにもかかわらず、潜在的には三重の負荷がかかっていることになる。同学年の子供といっても、発達の段階はさまざまだ。
これに対して、ストランド・バッハマン氏は入学時期の柔軟化が解決策になると主張する。発達がゆっくりな子は、6歳ではなく、もう1年遅らせて入学すればいい、というのだ。
実際、入学時期が柔軟なデンマークでは、10月から12月に生まれた子供の約40%が入学を翌年度に遅らせている。デンマークでは、「最年少」の子たちのADHD治療率は他の子たちと同程度にとどまっている。
※比較教育研究会は世界各地の教育現場をフィールドにする教育学者のグループです。地域研究に根差した日本の比較教育学の強みを生かして、現地の教育実践や人々の暮らしを多角的に見つめています。本連載は林寛平(信州大学)、佐藤仁(福岡大学)、荻巣崇世(東京大学)、黒川智恵美(上智大学)、能丸恵理子(ライター)が担当しています。