給特法改正の制度設計に取り組んでいる中教審「質の高い教師の確保」特別部会の議論では、公立学校教員の時間外勤務に手当を支給する考え方について否定的な見解が相次ぎ、給特法の枠組みを維持した上で教職調整額を増額する方向がほぼ固まったように見える。この問題を巡っては、教員の長時間勤務が解消されない状況を背景に、給特法を廃止して時間外勤務手当を支給すべきだとする意見も根強い。教育新聞の読者投票 Edubateでも意見は分かれており、「時間外手当を支給し教職調整額廃止」が「時間外手当はなく教職調整額を10%以上増額」をやや上回っている。中教審は、なぜ教員への時間外勤務手当の支給に否定的なのか。今後のスケジュールとともに、Q&A形式で解説する。
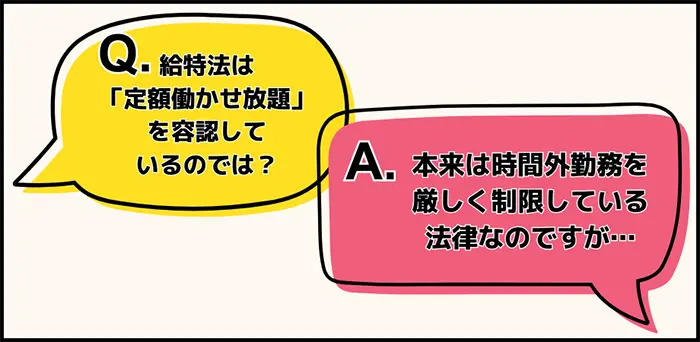
--労働基準法では、法定労働時間(1日8時間、1週40時間まで)を超える労働は時間外労働とされ、割増賃金の対象になると定められています。それなのに、公立学校教員の時間外勤務に時間外勤務手当が支給されないのは、なぜでしょうか。
1972年に施行された給特法によって、例外的なルールが定められているためです。給特法は正式には「公立の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置法」という長い名前の法律です。給料月額の4%に相当する額を教職調整額として上乗せ支給する代わりに、時間外勤務手当と休日勤務手当を支給しないことを定めています。
--時間外勤務手当を支給しない給特法の枠組みは、教員に対して「定額働かせ放題」を容認しているとの批判を受けています。
給特法は本来、教員の時間外勤務を厳しく制限している法律です。その上で、例外的に時間外勤務を認める業務として、政令でいわゆる「超勤4項目」を限定しています。4項目の内容は①校外実習その他生徒の実習②修学旅行その他学校の行事③職員会議④非常災害の場合、児童または生徒の指導に関し緊急の措置を必要とする場合、その他やむを得ない場合に必要な業務--となっています。
同時に給特法では、教員の健康と福祉の確保が掲げられています。2019年の法改正では超勤4項目以外の業務も含めて教員の勤務時間全体を在校等時間として時間管理を行う枠組みを作り、時間外在校等時間に「1カ月45時間以内」「1年間360時間以内」という上限を定めました。この内容は「公立学校の教師の勤務時間の上限に関する指針」として20年に告示されています。こうした仕組みを考えると、給特法は本来、「働かせ放題」の仕組みではないはずです。
ただ、22年度の教員勤務実態調査の結果によると、公立学校教員の1日当たりの在校等時間は小学校教諭10時間45分、中学校教諭11時間1分で、19年度調査の結果に比べて30分程度しか減っていませんでした。文部科学省では、上限指針を超える長時間勤務を行っている教員の割合は小学校で64.5%、中学校で77.0%に上っているとみています。つまり、告示されて3年がたっても、公立学校教員の3分の2が上限指針を守れないまま長時間勤務を続けているのが学校現場の実態です。
参考記事:若手教員支援、授業持ちコマ数の削減が必要 勤務実態調査確定値
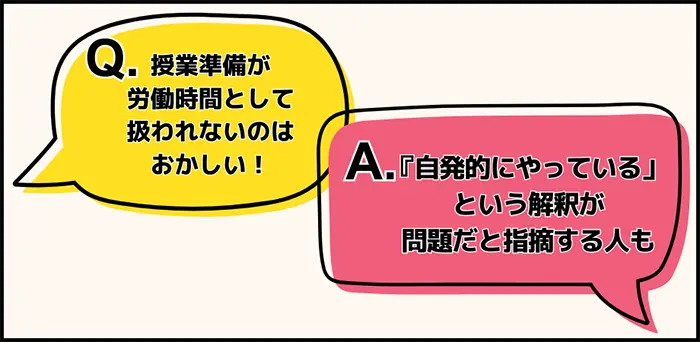
--教員の時間外勤務はなかなか減らないのに、時間外勤務手当が支給されない状態が続いているのは、おかしくないですか。それに私立学校や国立大学附属学校の教員には、同じ教員なのに時間外勤務手当が出ていると聞きます。
国立大学附属学校の教員は、以前は給特法の対象でしたが、04年の国立大学の法人化で対象から外れています。労働基準法は第36条で時間外勤務と休日勤務の取り扱いについて労使間協議で取り決めることを定めていて、私立学校や国立大学附属学校の教員は、この労働基準法の適用対象です。
しかし、公立学校教員は給特法によって労働基準法の適用対象から除外されています。このため、公立学校教員の時間外在校等時間のうち、超勤4項目に含まれない部分は「教員の自発的行為」とされ、労働基準法上の労働時間として扱われてきませんでした。例えば、授業準備や保護者対応、部活動顧問などで時間外勤務を行った場合は、「教員の自発的行為」と見なされ、時間外手当の支給対象になりません。この給特法の枠組みにおける時間外勤務の解釈は、超勤手当の支払いを求めて訴訟を起こした教員側が敗訴する理由にもなってきました。
--授業準備や保護者対応、部活動顧問などのために、夜まで学校に残って働いている教員も珍しくありません。それが労働時間として扱われないなんて、これもおかしいと思います。
そこを給特法問題の本質とみる専門家もいます。大阪大の高橋哲准教授(教育法学)は教育新聞のインタビューで、「問題は、超勤4項目以外で残業をせざるを得ない教員たちの現状をどう捉えるかです。こうした残業について、労働法の一般的な学説は、労働時間と解釈して残業代の支給対象になると考えています。これに対し、文科省や教育委員会は『自発的にやっているので労働時間ではない』と主張しています。つまり、教員に残業代が支給されない根本原因は給特法ではなく、文科省などの恣意(しい)的な法解釈にあるというのが私の考えです」と答えています。給特法が「働かせ放題」を容認しているかのように誤解されるのは、文科省の恣意的解釈に根本的な問題があるという指摘です。
参考記事:【給特法考㊥】「文科省の恣意的解釈こそ問題」 阪大・高橋准教授
また、中教審特別部会の4月4日の会合で、妹尾昌俊委員(ライフ&ワーク代表理事)は給特法の枠組みを維持して時間外勤務手当を支払わない状態を続けた場合について、「問題の一つは、時間外勤務の多くが教員の自主的・自発的な行為とされ、労働基準法上の労働に当たらないということだ。これを解決できない」「例えば、土曜日や日曜日の部活動指導について、手当や旅費として公費が出ているにもかかわらず、時間外勤務命令を出したものではないという位置付けで、労働基準法上の労働ではないという、非常にちぐはぐな法制度になっている。本当にこれでいいのか、しっかり考えないといけないはずだ」と述べました。給特法維持の流れができつつある中教審特別部会の委員の一人として、問題点を厳しく指摘した発言でした。
参考記事:教員の時間外勤務手当、否定的な意見相次ぐ 中教審特別部会
教員の時間外勤務を減らすために、給特法の廃止を求める有識者の見解も紹介します。別の中教審特別部会の委員も務めた立教大学の中原淳教授(人材開発・組織開発)は教育新聞の取材に対し、「長時間労働是正の研究に取り組んできて感じるのは、『就業時間はここまで、これより先はお金(残業代)がかかる』というキャップ(上限)がなければ、絶対に成功しないということだ。今の時間外勤務の上限指針(月45時間、年360時間)だけでは難しい」「民間企業なら、残業代を支払わなければ労働基準監督署から是正勧告を受ける。そのようなサンクション(制裁)が掛かる仕組みが、長時間労働是正の大きなストッパーになっている。しかし学校にはそれがなく、実質、労働時間管理を行っている人がいない」と説明し、給特法については「廃止した方が良い」と答えています。
公立学校教員にも労働基準法を適用し、時間外労働を減らすためのインセンティブを確保すべきだ、というのが給特法の廃止を求める人たちの基本的な主張になっています。
参考記事:【勤務実態調査】個々の学校ができることには限界 中原教授
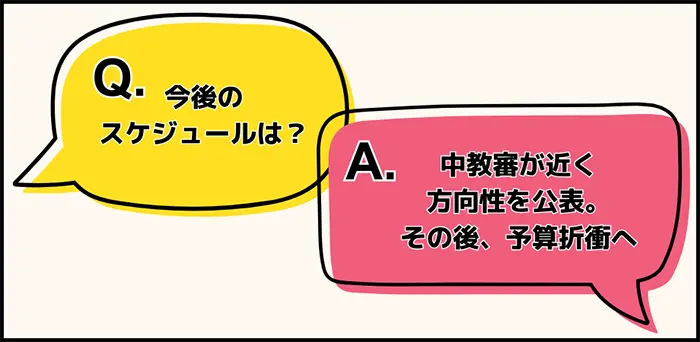
--これほどいろいろな問題が指摘されているのに、中教審特別部会の議論では、給特法の枠組みを維持したまま、教職調整額を増額し、時間外勤務手当の支給はしないという方向性が固まってきているように見えます。なぜなのでしょうか。
先ほどもお伝えしたように、給特法は本来、教員の時間外勤務を厳しく制限している法律なのですが、同時に教員を優遇している仕組みでもあります。時間外勤務をやってもやらなくても、給料月額の4%分が教職調整額として支給されるからです。
給特法が施行された当時は教員に優れた人材を確保する政策が次々と打ち出され、公立学校教員の給与を優遇する人材確保法や義務教育等教員特別手当なども創設されました。文科省によると、1980年時点で教員の給与水準は一般公務員よりも7.42%高かったそうです。こうした教員への優遇策は一般公務員の処遇改善や行財政改革によって徐々になくなり、現在、教員に対する優遇措置は0.35%で、一般公務員とほとんど変わらない給与水準になっています。
これに対して2020年代に入り、教員の長時間勤務が社会的にも注目され、新年度に学級担任が足りないなど子供たちへの影響も懸念される中で、将来の学校現場に優れた人材を確保するために教員の待遇改善を求める動きが再び広がってきました。
自民党の「令和の教育人材確保に関する特命委員会」は23年5月、教員の時間外勤務について「将来的には月20時間程度を目指す」とともに、教職調整額を現行の4%から「少なくとも10%以上に増額」する政策提言をまとめました。これを受ける形で、政府は23年6月、「経済財政運営と改革の基本方針2023」(骨太の方針)で、24年度から3年間を「集中改革期間」と位置付け、給特法について「24年度中の改正案の国会提出を検討する」ことを閣議決定しています。
参考記事:学校のマンパワー拡充「義務教育のコストが変わる」 萩生田氏
国内政策や国際協調の合意形成には、時代の動きを捉える「モメンタム」(勢い、弾みなどの意味)が必要だと、よく言われます。その意味で、いま、財源確保を含め、教員の処遇を改善する何十年に一度という局面がきていると思います。
今後少子化が進み、必要な教員数が減っていくことを考えると、教員の処遇改善に向けて、このチャンスを逃すわけにはいかないという思いが関係者にはとても強いと、取材していて感じます。文科省の矢野和彦・初等中等教育局長は、24年2月14日の中教審特別部会のあいさつで、「ある意味『関ヶ原』。17年以来の働き方改革の議論を進めてきた中での集大成」と気持ちを込めました。同日の特別部会では、給特法に批判的な立場をとっている労働界代表の金子晃浩連合副会長も教職調整額の引き上げに対して明確に反対することはなく、教職調整額の想定を超えた時間外勤務に対して時間外手当の支給を求めています。労働組合として、取れるものは取ろうという考え方にみえます。
このほかにも、給特法の枠組みを変更して教員の時間外勤務に手当を支給する考え方に反対する理由として、4月4日の中教審特別部会では、委員から「教員一人一人の時間外勤務が必要かどうか、管理職が毎日毎日、個別具体に見極めることは事実上難しい」「教員の高度専門職としての自律性を損なう」といった指摘が出ました。いろいろな意見がありますが、議論の背景には、教員の処遇を改善するチャンスを逃してはいけない、という共通認識があるとみていいでしょう。
こうした状況を背景に中教審特別部会は近く、教職調整額を増額する方向性を明確に示すとみられます。そうなると、時間外勤務手当の支給はしないという、給特法の枠組みを基本的に維持することになると思います。
参考記事:給特法「現行の枠組み維持した上で改善」が大勢 中教審特別部会
--なるほど。今後はどのようなスケジュールで政策作りが進むのですか。
教員の給与は当初予算案に盛り込まれるので、給与の見直しを定める法改正は予算関連法案として扱われます。給特法について政府は「24年度中の改正案の国会提出」を掲げていますので、25年度予算編成のスケジュールに合わせて検討が進むことになります。
政府のスケジュールとしては、6月ごろに閣議決定される新たな「経済財政運営と改革の基本方針」(骨太の方針)で大まかな姿を示し、8月末までに文科省が概算要求として政策の具体像をまとめます。ただ、概算要求には具体的な金額を示さないまま予算折衝の過程で政策内容を詰めていく「事項要求」というやり方もあります。この概算要求では、公立学校教員の級別職務に主任教諭を新設するなど、教員制度改革の全体像をみながら具体像を詰めることになり、予算獲得に向けて文科省の手腕の見せどころと言えます。いずれにせよ、12月下旬の政府予算案で具体像が固まり、予算関連法となる給特法の改正案は25年3月末までに国会提出されることになります。
このスケジュールから逆算すると、制度設計を担う中教審は近く、給特法を含めた教員の処遇改善について、方向性をまとめることになります。それから自民党など政権与党での議論が行われ、骨太の方針に反映されるという政策決定プロセスです。自民党は国会で多数派を握る政権与党であり、政権与党の同意がなければ、政府は政策遂行に必要な予算や関連法案を国会で成立させることができません。中教審がまとめた方向性を受けて、文科省は、政策を実現するために政権与党との擦り合わせを進めることになります。
参考記事:給特法の改正論議、とうとう決着へ 教育専門メディアが解説
--教員の処遇改善には期待したいですが、気になるのは教員の長時間勤務の解消はどうなるのかということです。公立学校教員の3分の2が上限指針を超える長時間勤務を続けている現状はどう考えてもおかしいと思います。
昨年6月、政府が骨太の方針に24年度から3年間を「集中改革期間」と位置付けることを盛り込んだ際、当時の永岡桂子文科相に閣議後会見で集中改革期間のゴールをどこに設定するのか見解をただしたことがあります。永岡前文科相は「上限指針の実効性向上に向けた枠組みの構築が重要」と答えました。
つまり、24年度予算に盛り込まれている小学校高学年教科担任制の強化や教員業務支援員の配置拡大、25年度予算案に盛り込もうとしている教員の処遇改善とそれに伴う給特法の改正など一連の政策の目的は、教員の長時間勤務を解消し、時間外在校等時間を月45時間、年360時間以内とする上限指針を全国各地の学校現場で実現していくことにあると、文科省は設定しているわけです。これはもっと注目されていいことだと思います。
参考記事: 教員の集中改革期間、時間外勤務上限指針の実現目指す 文科相
給特法の廃止を求めて有志の会を立ち上げ、署名活動などを続けてきた公立高校教員、西村祐二氏は「大切なことは、教員の長時間勤務をなくすことだ。給料を上げてくれと言っているわけではない」と繰り返し訴えています。教員の長時間勤務を解消することが一連の議論の最も重要なゴールだと認識していることは、文科省で政策作りにあたっている人たちにも、給特法の廃止と時間外勤務手当の支給を求める人たちにも、大きな違いがないように取材していて感じます。
そうなると、重たい事実となるのは、22年度の教員勤務実態調査で、公立学校教員の1日当たりの在校等時間は19年度調査の結果に比べて、30分程度しか減っていなかったという結果です。
--上限指針が告示されて3年がたっても、公立学校教員の3分の2が上限指針を守れないまま長時間勤務を続けているということですよね。これまでと同じ取り組みで、本当に上限指針を実現できるのか、という疑問が湧きます。
文科省と中教審はいろいろな取り組みをしてきています。中教審は23年8月、標準授業時数を大きく上回る1086時間以上の教育課程を見なすことなどを求めた緊急提言をまとめています。強調されているのは▽国、都道府県、市町村、各学校などが自分事としてその権限と責任に基づき自主的に取り組む▽保護者や地域住民、企業など社会全体が一丸となって課題に対応する--の2点が極めて重要だということです。
参考記事:標準授業時数上回る教育課程「年度途中に見直しも」 中教審緊急提言
文科省では学校の働き方改革について詳細な事例集をまとめています。全国の学校現場から好事例を集めているほか、チェックシートを通じて校内の業務改善や保護者との連絡手段のデジタル化などを進める働き方改革のノウハウを確認することができます。
一方、専門家からはこれまでの取り組みの延長では、教員の時間外在校等時間を大幅に減らすことはできないという指摘も出ています。上限指針を設定した19年の中教審答申をまとめた特別部会で部会長を務めた小川正人東京大学名誉教授は「従来のアプローチと違う、より効果的なアプローチ、手法で取り組まないと時間外在校等時間を大幅に減らせない」として、教員の在校等時間を強制的に減らす法的な枠組みの導入が必要だと説明しています。具体的には、健康確保のための振替休暇を措置することや、勤務間インターバルを学校に定着させることを提案しています。
参考記事:【給特法考㊦】「強制的な削減ルールが必要」 東京大・小川名誉教授
仮に給特法の枠組みを維持して時間外勤務手当を支給しないという選択をする場合であっても、教員の長時間勤務が解消されなければ、将来の優れた教員人材を確保することは難しくなります。政府・文科省にとっては、政策目的を達成できないということです。26年度までの3年間の集中改革期間を通して、全国各地の学校現場で上限指針を実現できる環境を本当に作ることができるのか。そこに本質的な課題があると思います。