教員の長時間労働や人材不足を解消するために、業務効率化や時短の取り組みなど、教員の働き方改革が強く叫ばれている。この記事では、教員の働き方の課題に加えて、具体的な対策や成功事例を紹介する。働き方改革推進のカギとなるデジタル活用についても解説する。

働き方改革とは、多様な働き方が選択できる社会を目指す取り組みを指す。働き方改革関連法の施行で、民間企業では残業の上限規制や在宅勤務など柔軟で多様な働き方が進んだ。働き方改革は全ての労働者が対象であり、その中には小学校や中学校の教員も含まれる。
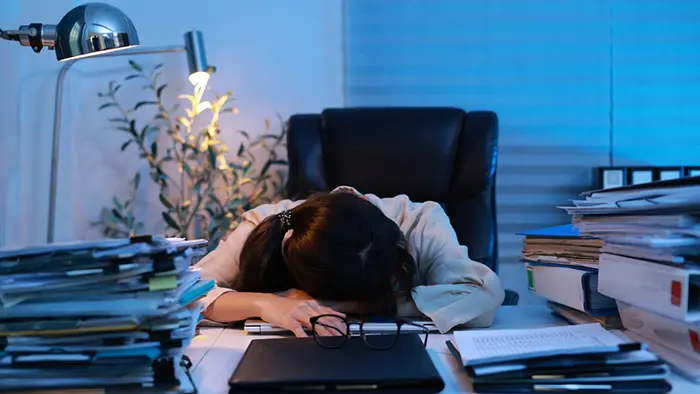
長時間労働の現状だけでなく、採用倍率の低下や特別支援学級の増加、産休・育休取得者の増加などによる「教員不足」「なり手不足」も深刻さを増し、教員の働き方改革は差し迫った教育課題となっている。
文部科学省が2023年4月に発表した22年度の教員勤務実態調査の内容によると、教諭の1日あたりの平均勤務時間は小学校で10時間45分、中学校で11時間01分だった。16年の前回調査と比べて、小学校で30分、中学校で31分減少していたものの、週60時間以上働く教員の割合は、小学校で14.2%、中学校が36.6%だった。
この間、文部科学省は働き方改革を推進する総合策「公立学校の教師の勤務時間の上限に関するガイドライン」(19年1月)を策定し、時間外勤務は1カ月45時間以内、1年間で360時間以内の目安を示した。だが、22年度調査では、通常期には小学校で65%、中学校で77%の教員が上限指針を超える時間外勤務の実態が明らかになった。なぜ長時間労働は解消しないのか。
文部科学省 教員勤務実態調査(令和4年度)の集計(確定値)について
08年に改訂された学習指導要領で、授業時数が約30年ぶりに増加し「脱ゆとり」に転じた。その次の17年の改訂では、新しい時代に求められる資質・能力を育成するため、理数教育や道徳教育、体験教育の充実、小学校での外国語教育の導入と教科化など、新たな内容が盛り込まれた。高校では国語や英語、数学などの科目が再編されるなど、学習内容が量的にも質的にも大きく変化した。このため教員は授業準備や成績処理、さらには学年・学級経営に割く時間も増えることになった。一方で、02年度に導入された完全学校週5日制は見直しが行われなかったため、平日の授業時数は増え、結果として1日あたりの授業時間が増えることになった。これが教員の長時間労働の構造的な要因の1つと言える。
〇関連記事
【勤務実態調査】通常期の指針超え 小学校65%、中学校77%
「ゆとり教育」は余裕を生んだのか データから見える意外な実態
もう一つは部活動の指導にある。平日の放課後だけでなく、練習や大会の引率などで土日の出勤も珍しくない。20年度より部活動改革が始まったが、文部科学省の教員勤務実態調査(22年度)によれば、中学校の教員が土日の部活動に関わる時間は1時間29分だった。前回調査の2時間10分からは40分減少したものの、大きな削減には至っていない。働き方改革の必要性は分かっていても「生徒に勝利の喜びを経験させたい」といった使命感や、部活動を通じて生徒と関わるのが楽しいという意識、生徒や保護者の期待に応えなければという義務感から教員が出勤することも少なくない。
〇関連記事
教員の年齢構成のアンバランスさも働き方改革を困難にしている。団塊世代の教員が大量退職し、現在、教員の「若返り」が進んでいる。22年度の学校教員統計調査によると、30歳未満の教員の比率が上昇し、50歳以上の比率は低下した。若手教員のうちは、担任業務や教科の授業準備に膨大な時間がかかる。また、学校外での初任者研修を受ける際には授業を代わってもらう教員が必要になるのに加え、他の教員が初任者ら若手の育成に当たる必要もあり、中堅やベテラン層の教員の業務負担が増している。だが、中堅やベテランも急増した若手教員の育成に十分手をかけられないのが現状だ。若手教員の中には仕事になじめず、心身の不調を来し、休職や退職せざるを得ないケースが指摘されている。
〇関連記事
教員不足は小中高とも年度後半に深刻化 妹尾氏や末冨教授らが公表
【産休・育休と教員不足(上)】 取得する教員の「後ろめたさ」

さらに深刻なのは全国的な教員不足の問題だ。特別支援学級の増加や、産休・育休取得者の増加などが要因とされるが、長時間労働による教職の魅力低下が影響していると見る向きもある。教職を志す人を増やすためにも働き方改革は急務だ。
文部科学省の調査によると、公立学校全体の採用試験倍率は3.4倍(22年度実施試験)と過去最低を記録。最も高かった1999年度実施試験の13.3倍と比較して大幅に下落している。特に小学校では、22年度実施試験で倍率が1倍台となった自治体も多く、実質的に定員割れとなっているところもある。
文部科学省 令和5年度(令和4年度実施)公立学校教員採用選考試験の実施状況について
また、志願者の減少で、採用されなかった志願者を充当することが多かった常勤講師(臨時的任用教員や産休・育休代替教員)の不足も起きている。4月に教員数が足りず、一部の授業ができないなどの事態が毎年度各地で頻発している。
教員の採用倍率が低下すれば、必要な人材を確保することが難しくなり、結果として児童生徒への支援の質の低下と教員の負担増を招く。将来の教員のなり手を確保するためにも働き方改革は急務だ。
〇関連記事

教員の働き方改革を成功させるには、19年の中教審答申を踏まえ「できることは直ちに実行する」ことがポイントだ。以下、中教審の特別部会が23年8月に取りまとめた緊急提言に基づいて解説する。
中教審 教師を取り巻く環境整備について緊急的に取り組むべき施策(提言)
働き方改革以前、ほとんどの教育現場では、教員の出勤・退勤時間を把握せずにいた。タイムカードやICカードの打刻によって出退勤記録を残し正確な労働時間を把握することは働き方改革の基本となる。学校閉庁日の設定や、留守番電話の導入、メールによる連絡対応の整備なども有効だ。子どもたちのために「納得するまで働く」というこれまでの意識を変え、定時退勤を習慣化すれば、メリハリのある働き方改革につながる。
〇関連記事
学校では、行事が増えたり、新たな問題に対処するために教員の業務が増やされたりしても、他の業務の見直しが図られることは少なく「教員の仕事が増えることはあっても減ることはない」という状態が長年続いてきた。
文部科学省は19年の中教審答申に基づき、教員の働き化改革のために削減可能な業務を「基本的には学校以外が担うべき業務」「学校の業務だが、必ずしも教師が担う必要のない業務」「教師の業務だが、負担軽減が可能な業務」(学校・教師が担う業務に係る3分類)の例を示している。
教員の働き方改革を進めるには、登下校時の見守りなど「本来は学校以外が担うべき業務」を地域やサポートスタッフなどに振り分け、教員の業務を削減していくことが重要になる。また、プールの維持管理のような業務は、可能な範囲で外部委託するなどして自治体レベルで業務量の削減に努める必要がある。
教員の働き方改革のために、授業時数や学校行事のあり方の見直しも進めたい。年間授業時数が1086単位時間以上と、標準の授業時数を大幅に上回っている学校は、指導体制に見合った計画へと見直し、学校行事についても精選・重点化し、準備を簡素化・省力化することが求められる。
〇関連記事
中教審の答申では、部活動は「必ずしも教師が担う必要のない業務」に分類され、働き方改革で見直すべきだとされる。特に休日の部活動は地域移行が段階的に進んでいる。地域資源を活用するなど、教員が土日に参加しなくても運営可能な体制を構築することが必要となる。
〇関連記事

教員の働き方改革を進めるには、デジタル化による教育の効率化や業務負担の軽減が不可欠だ。以下、デジタルツールの活用について解説する。
「ICT」とは「Information and Communication Technology(情報通信技術)」の略称であり、「ICT教育」とは情報通信技術を活用した教育のことを指す。20年度末から児童生徒への1人1台の端末と、大容量・高速のネットワークを一体的に整備する「GIGAスクール構想」が実現したことにより、ICT環境は全国的に整いつつある。今後は働き方改革のためにも、端末やクラウドを活用した教材プリントや宿題などの配布、課題提出、成果物の蓄積などが望まれる。教員の板書の準備や実際に板書している時間、資料を用意する時間の削減には電子黒板の導入も有効だ。
〇関連記事
「デジタルで教育の質向上を」自民、学校DX推進で文科相に提言
授業以外のさまざまな校務をデジタル化することも、業務の効率化に貢献するため、教員の働き方改革につながる。学校には健康観察の集計や、特別教室や体育館の使用状況、時間割と週案の管理、行事予定管理、起案書の作成と決裁などの重要な事務作業が山積している。既存のグループウエアを活用したり、校務支援ソフトなどを導入してデジタル化を進めたりすれば、ペーパーレス化が進むだけでなく、担当教員を探しに校内を駆け回らなくても、オンライン上のチャットツールで連絡が済み、時間の節約になる。
〇関連記事

以下、教員の働き方改革に成功した2校の具体例を紹介する。
名古屋市立東築地小学校では、「業務改善」と「意識改革」の2つのアプローチで働き方改革を進めた。具体策としては、朝の打ち合わせの簡略化、会議のやり方の変更、行事の見直し、18時以降の留守番電話の導入などの取り組みを実施。その結果、2学期には残業時間が月80時間以上の教職員がゼロという快挙を達成した。
〇関連記事
【職員室革命(1)】マインドセット①働き方のルールを意識する
国立大学の附属学校では、教員が平日の夜や土日に研究活動に取り組んでいることが少なくない。また、伝統的に実施されている独自行事とその準備にも多くの時間とエネルギーがかけられ、教員が厳しい労働環境に置かれているケースがある。
そうした中、大分大学教育学部附属小学校では働き方改革のため、独自研究を基にした公開研究会の廃止、提案のワンペーパー化、学校の経営方針を基にした業務のスクラップなどの取り組みを実施し、18時45分完全退勤を実現させた。
〇関連記事

海外の学校は、日本に比べて業務の分業化が図られている点が特徴だ。教員は長期休暇が取れて、個人の勉強時間も確保できる。働き方改革を進める際、海外の具体例が参考になるところもあるだろう。
イギリスや韓国では、日本のように教員が担うべきかが曖昧(あいまい)な部分の業務を削減した。フィンランドでは、教員は授業のあるコア時間のみ学校にいるだけでよく、勤務時間の大部分を教科の指導に当てられる環境が整えられている。
〇関連記事

学校の働き方改革が本格化して5年。しかし、教員の過重労働は依然として解消されていない。放置すれば、病休者や退職者の増加、教員志望者の減少が進み、公立学校が正常に運営できなくなる恐れがある。教員の長時間勤務を是正する働き方改革は、質の高い教育を確保する上でも避けて通れない。国・自治体・学校の各レベルで推進し、学校の労働環境を改善する働き方改革が求められている。