
名古屋駅から在来線を乗り継いで約30分。知多半島の付け根に位置する愛知県東浦町に、半世紀近く前から「個別最適な学びと協働的な学び」に取り組んでいる公立小学校がある。東浦町立緒川小学校は1978年、オープン・スペースを備えた校舎に全面改築されるとともに、「個性化教育」への大改革にかじを切った。それ以降、独自のカリキュラムと、徹底して子どもの目線に立つ教育観が脈々と受け継がれてきた。2021年の中教審答申が「個別最適な学びと協働的な学びの一体的充実」を提言したことを受け、現在、緒川小の教育に改めて注目が集まっている(全2回の前編)。

不登校児童生徒が増加し続ける中、各自治体では教室に入りづらい子どもたちを受け入れる校内のサポートルームなどの開設が進められている。埼玉県戸田市でも2022年度から市内の小学校3校をモデル校として「戸田型校内サポートルーム・ぱれっとルーム」をスタートさせ、現在では市内全小学校に広がっている。モデル校の1校が、市立美女木小学校だ。「ぱれっとルーム」の開設から2年、子どもたちにとって安心・安全な場を守りながらも、一人一人の次のステップも見据えてチームで動く、同校の試行錯誤を取材した。
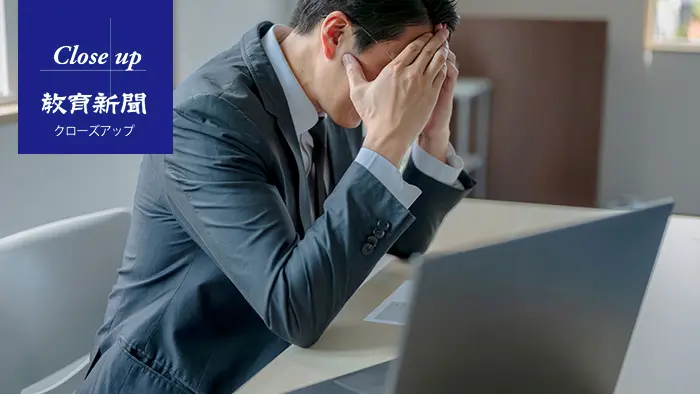
教員の確保が難しい現状に頭を抱えているのは、現場の教員だけでなく、教育委員会も同じだ。丁寧な指導を通じて学力を引き上げたり、特別な支援が必要な児童生徒へのケアを充実させたりするため、予算が許すならば、教員を増やしたいと考える教委は少なくない。だが、こうした議論を進めるには、配置する人材を確保できることが前提となる。今回は、深刻な教員不足によって、教育条件を改善するどころか維持することも難しくなり、追い詰められつつある教育行政の姿をレポートする。

下校時刻を40分早める――。長野県の松本市立波田小学校が「働き方改革」の一環として実施し、成果を上げた取り組みの一つだ。教員1人当たり週に3時間以上のゆとりを生み出した同校の改革は、話し合いを始めてわずか3カ月でスタートしたという。改革を推進してきた三輪千子校長に、これまでの経緯を聞いた。

教師の処遇改善策などを盛り込んだ中教審「質の高い教師の確保特別部会」の審議まとめ案。審議まとめ案が示された特別部会の開催直前に記者会見し、教職調整額の引き上げについて「手段と目的が整合的ではない」と批判した立教大学の中原淳教授と、特別部会の臨時委員として、審議まとめ案に対しても検討すべき論点を意見書として出している(一社)ライフ&ワークの妹尾昌俊代表理事がオンラインで対談した。第1回では教職調整額の引き上げをはじめとする、大きな予算増を伴う改革の目的と手段の整合性を検証する。

教員政策の方向性を描いた中教審の審議まとめ素案について、2019年に働き方改革答申をまとめた小川正人東京大学名誉教授は「学校内外の分業を徹底するのか、それとも教員に教科指導と生活指導を含めた『多能工』的な役割を求め続けるのか、中途半端ではないか」と指摘した。その上で、学級担任手当の新設など「対応策のベクトルが混乱し、不十分さが見える」と問題提起した。
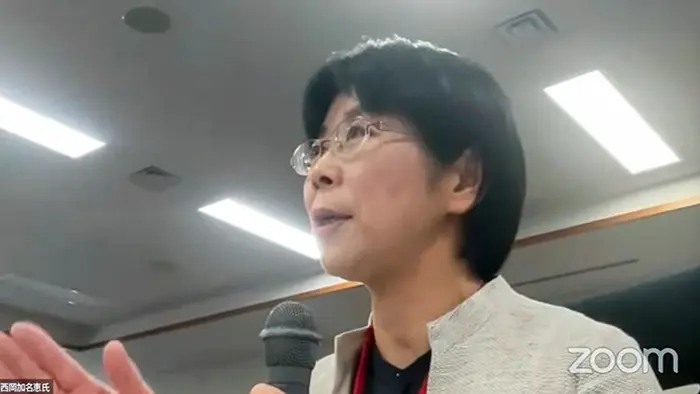
次期学習指導要領を見据えた教育課程や指導、評価などの在り方を議論している文部科学省の有識者検討会は4月26日、第11回会合を開き、招かれた教育方法学(カリキュラム論、教育評価論)が専門の京都大学大学院教育学研究科の西岡加名恵教授が、「学習評価の在り方からカリキュラム改善を考える」というテーマで発表を行った。西岡教授は現行学習指導要領における評価の3観点のうち、「主体的に学習に取り組む態度」の成績付けは、「思考・判断・表現」に統合すべきだと提案した。

教員は朝早くに学校に行き、夜遅くまで学校にいる。特に4月の仕事量は多い。教員にも家族と過ごしたり、世の中を知ったりする時間が必要だ。より良い授業や学級経営を目指すなら、職員室で考えているだけでは限界がある。そのため仕事量の見直しと合わせて、自由度の高い働き方を実現したい。「授業時間が終わったら、先生たちは学校にいない」を、日本社会の当たり前にできないか。

給特法改正の制度設計に取り組んでいる中教審特別部会の議論では、公立学校教員の時間外勤務に手当を支給する考え方について否定的な見解が相次ぎ、給特法の枠組みを維持した上で教職調整額を増額する方向がほぼ固まったように見える。中教審は、なぜ教員への時間外勤務手当の支給に否定的なのか。今後のスケジュールとともに、Q&A形式で解説する。

文部科学省が2022年に出した特別支援教育を巡る通知を巡り、大阪弁護士会が3月、「子どもたちがインクルーシブ教育を受ける権利を侵害している」として、内容の一部を撤回するよう勧告した。通知は特別支援学級に在籍する児童生徒が通常学級で受ける授業数に制約を設ける内容となっており、障害者権利条約が定めるインクルーシブ教育の理念に反すると判断したという。これに対し、文科省側は「(通知は)インクルーシブ教育を目指したものだ」と真っ向から反論し、撤回には応じない考えを示している。論争の背景を取材した。

神奈川県鎌倉市立七里ガ浜小学校で先月、市立の小中学校の教職員約50人を対象に生成AIについての研修会が行われた。教員たちが実際に生成AIを使い、学びの場に生成AIをどのように活用するのか議論が行われた。

東京都教育委員会は今年度、不登校の生徒に対し、教室とは違う別室で学びを続けられる仕組み作りを、都立高校17校で始めた。その中の1校、都立荻窪高校では、昨年6月からこうした校内別室指導の取り組みを推進。安心できる雰囲気の中、生徒が徐々に学びへの意欲を取り戻すなどの成果が見られる一方で、不登校生徒に関わる教員や支援員の間で、共通理解を図ることの難しさも分かってきたという。

学校現場での生成AIの活用はまだ始まったばかりだ。文部科学省の「生成AIパイロット校」として、全教員が授業や校務で活用を進めた千葉県船橋市立飯山満中学校では、さまざまな成果や課題が見えてきている。また、同校はこれまで授業改善を前提として、ICTの活用を進めてきた。教師が一方的に教える一斉授業からの脱却で見えてきた「新しい学びの姿」はどんなものなのか━━。

発達障害のある子ども、不登校傾向の子ども、家庭環境に困難を抱える子ども、外国にルーツのある子ども――。多様な子どもたちへの対応は、学校現場の大きな課題になっている。こうした子どもたちへの支援に取り組んできた東京都足立区の学校現場では、学校教育のユニバーサルデザイン(UD)の実践が浸透しつつある。

埼玉県の蕨市立北小学校は、校内研究の在り方を抜本的に改革。教員が主体的に取り組みたいテーマを募ってグループ研究を進める一方、研究発表会に向けて授業や指導案を作り込むのはやめ、普段通りの授業で研究の成果を見せること、参観者と教員、児童との対話を増やすことを意識。教員が主体的に学びを深める「幸せな校内研究」の実現を目指した。

東京都目黒区では、区立小学校22校のうち17校で「40分授業午前5時間制」を導入し、学校裁量の時間を増やしている。同区立宮前小学校(渡部浩文校長、児童306人)では、授業時間の短縮で生み出した時間で、子どもたちから出た疑問を深く追究する独自の探究学習「たんQ」を始めた。どのような教育活動が実現できるようになったのか、同校を取材した。
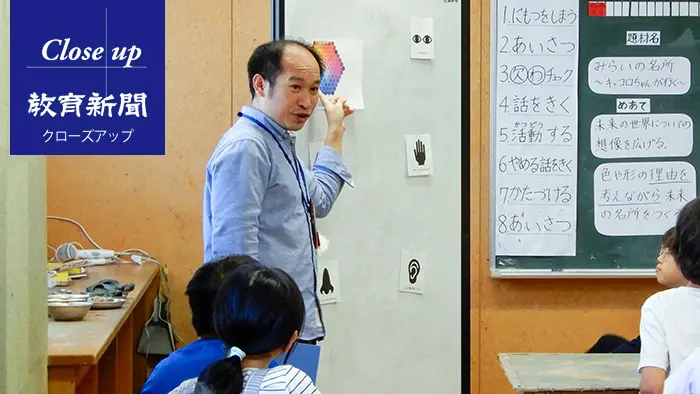
現行の学習指導要領において、学びの核として位置付けられている「総合的な学習の時間」。しかし負担や課題を感じている教員も多い。そうした中、学年の通期の学習における概念を核に、総合的な学習の時間のカリキュラムづくりに取り組んでいるのが、東京都三鷹市立第三小学校の山下徹主任教諭だ。4年生が昨年10月から取り組む「未来の暮らしを考える」プロジェクトを追った。

「40分授業午前5時間制」は教員の働き方をどう変えているのか━━。東京都目黒区では、区立小学校22校のうち17校で授業時数の特例として1コマを40分とする「40分授業午前5時間制」を導入している。授業時間を短縮することで生み出した時間の活用は各校で異なるが、同区立中根小学校ではその多くを「教員の放課後時間のゆとり」に活用することで、働き方改革を進めている。

待ったなしの状況となっている学校の「働き方改革」。だが、長年続いてきた職場習慣を変えることに抵抗感を示す教員もおり、スムーズに進まない学校や地域もあるとされる。そうした中で注目を集めているのが、データと対話に基づいて課題の改善を図る「サーベイフィードバック」という手法だ。文部科学省が2022年度から取り組んでいる校長研修のモデル事業にも採用された。

大分県立芸術文化短期大学で非常勤講師を務める望月陽一郎氏は、独自調査から「まだ授業で活用する段階にないと考える教員が多い」と指摘。北海道東川町でICT教育推進アドバイザーを務める同町立東川小の石本周司教諭は「子供たちの方がどんどん先に行く現象が起きている」と語る。学校が活用に踏み切れない背景に関する分析や、制限のある中で活用する現場教員の実践を取材した。

最近「次の学習指導要領はどうなりますかねえ」といった質問を受けることが多いが、今の段階では、どうにも答えようがない。そんな先のことより、現行学習指導要領の着実な実施に全力を上げるのが賢明であろう。むしろ気になるのは、現行学習指導要領について、すっかり分かった気になってはいないかである。まずは現行の学習指導要領のどこが画期的だったのか、特徴を整理したい。

非正規教員の中には、学校で「先生」として働きながら、毎年教員採用試験を受け続けている人もいる。「なかなか合格できないのは、その人の資質に何か原因があるのではないか」と思うかもしれないが、それならばどうして、その人は正規教員とほとんど変わらない業務を担っているのだろうか。非正規教員の視点から日本の教員採用が抱えている葛藤を考察する。

来年度から東京都渋谷区の全区立小中学校で、月曜日から金曜日まで午後の授業を探究学習の「シブヤ未来科」に充てることが、12月27日までに教育新聞の取材で分かった。文部科学省の「授業時数特例校制度」を活用し、総合的な学習の時間を年間70時間から約150時間に拡充する計画だ。教育課程をこれほど大胆に探究学習にシフトさせるのは全国でも初の取り組みとみられる。

中教審は12月13日、初等中等教育分科会教育課程部会を開き、OECD(経済協力開発機構)が2022年に実施した生徒の国際学習到達度調査(PISA)の結果を踏まえた今後の学習指導要領の在り方などを議論した。「数学的リテラシー」「読解力」「科学的リテラシー」の全3分野で日本のスコアが上昇したことを歓迎する一方、背景には教員の献身的な努力があるとして、現場の負担に配慮するよう求める声が相次いだ。

川崎市立川崎小学校では、2代の校長が12年間かけ、子ども主体の授業の実現に向けた校内研究を重ねてきた。鍵は「全員参加・全員理解」の授業と「子どもたちが安心して過ごせる学級経営」。結果として、外国につながる子どもに不登校児童は現在なく、教師と保護者の良好な関係という好循環も生み出している。ごく一般的な公立小学校が粘り強く続ける取り組みを取材した。

中部地方初となる公立の「学びの多様化学校(いわゆる不登校特例校)」として、2021年4月に開校した岐阜市立草潤中学校。登校しても家庭にいても学べる、担任は生徒が選ぶ、校則や制服などの決まり事はないなど、不登校を経験した生徒のありのままを受け入れる「学校らしくない学校」として、開校当初から注目を集めてきた。生徒たちはこの3年、どのように過ごしてきたのか━━。草潤中の今を取材した。

深刻な教員不足の要因の一つとして挙げられる「産休・育休」の増加。前編では、産休・育休の当事者である教員の苦悩を紹介した。一方、欠員が生じることになる学校現場は、代替教員の確保や柔軟な引き継ぎに悩んでいる。文科省は今年度から、代替教員を年度当初に前倒し配置できるよう加配の運用を見直しており、さらに踏み込んだ支援策をとる自治体も出ている。

名古屋駅から在来線を乗り継いで約30分。知多半島の付け根に位置する愛知県東浦町に、半世紀近く前から「個別最適な学びと協働的な学び」に取り組んでいる公立小学校がある。東浦町立緒川小学校は1978年、オープン・スペースを備えた校舎に全面改築されるとともに、「個性化教育」への大改革にかじを切った。それ以降、独自のカリキュラムと、徹底して子どもの目線に立つ教育観が脈々と受け継がれてきた。2021年の中教審答申が「個別最適な学びと協働的な学びの一体的充実」を提言したことを受け、現在、緒川小の教育に改めて注目が集まっている(全2回の前編)。

自立と共同を重視し、異年齢の子どもが一緒に学ぶクラス編成をするといった特徴で知られる「イエナプラン」に基づく学校が、日本でも増えつつある。その中の一つ、長野県佐久穂町にある茂来学園大日向中学校(長沼豊校長、生徒21人)は、日本で初めてイエナプランを実践する中学校として、昨年4月に誕生した。