

小学6年生と中学3年生を対象とした「全国学力・学習状況調査」(全国学力テスト)が4月18日、全国の小中学校で実施された。2007年度にスタートした全国学力テストは「自治体間の競争をあおっている」との批判を受けながらも、東日本大震災が起きた11年度、コロナ禍に見舞われた20年度を除いて毎年行われてきた。この全国学力テストと共振するように、21世紀になって拡大したのが、都道府県や政令市などの地方自治体が独自で実施する学力調査だ。その20年史を振り返ると、「ゆとり教育」への批判や全国学力テストの成績向上に対するプレッシャー、教員の「働き方改革」の必要性といった学校を取り巻く環境の変化の中で、揺れ続けてきた実態が浮かび上がってくる。
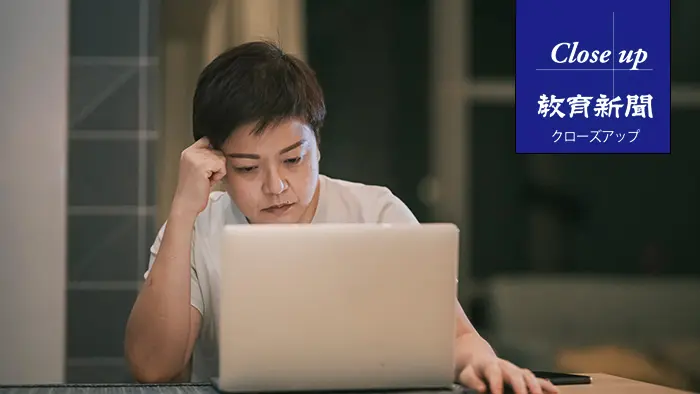
教員の「働き方改革」や待遇改善について審議している中教審の特別部会は、公立学校の教員の勤務時間外の貢献も含めた対価として支給している「教職調整額」の水準について、月額給与の4%から同10%以上に引き上げることを盛り込んだ審議まとめの素案を示した。労働時間に応じた残業代を支給せず、定額の教職調整額を支払う同法の仕組みを巡っては、教員の長時間労働の要因になっているとの指摘がある。このため、法律自体の廃止を求める声もあったものの、維持される公算が大きくなったと言える。給特法体制の下で教員の長時間労働を是正していくには、どうすればいいのだろうか。今回はある自治体で起きたケースに基づき、「給特法を使う」という視点で考えた。

教員の「働き方改革」や待遇改善を巡り、中教審の特別部会は、給特法に基づいて公立学校の教員に支給している「教職調整額」について、月給の4%としている現行水準を改め、10%以上に引き上げるよう求める方向で調整に入った。関係者への取材で判明した。給特法は、教職調整額を支給する代わりに時間外勤務手当・休日勤務手当(残業代)を支払わないと規定している。現場教員の間には、同法を廃止して労働時間に応じた残業代を支払う仕組みに変えるべきとの意見も根強いが、「教員の職務の範囲を切り分けることは困難」などとして見送る方向だ。文部科学省はこうした方針について、4月19日に開催される中教審の特別部会で示す審議まとめ案に盛り込む。

投資や資産形成などについて学ぶ「金融経済教育」の学校現場への普及に取り組んでいる「金融経済教育を推進する研究会」は4月4日、こうした教育を一層拡充するよう求める要望書を文部科学省に提出したと発表した。現行の学習指導要領では資産形成に関する学習内容が増えたものの、同研究会が実施した調査の結果、教員の知識や指導体制、生徒の理解などの面で課題が見られたと指摘。次期学習指導要領では、投資の意義や役割に関する学習を一層充実させるとともに、担当教員を養成する段階で経済学の知識を身に付けてもらったり、お金や金融などの知識を体系的に学べる教科の新設を検討したりするよう求めた。
